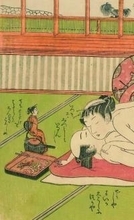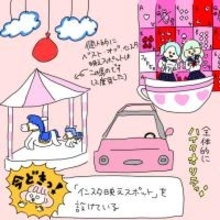多大な仕事を効率よく処理する能力が高い人は、「インバスケット思考能力が高い人」だと言われている。「インバスケット思考」とは元々アメリカ空軍の教育訓練法として確立された、多数の案件に優先順位を決めて取捨選択をし、限られた時間内で処理していく思考法のことである。「インバスケット」は和訳すると「未処理箱・未決箱」といった意味で、案件がランダムに入っているボックスを想像するとイメージがつきやすいだろう。
この考え方を学ぶ方法として取り入れられるのは、「インバスケットゲーム」である。これは、実際に架空の様々なタスクを用意し、どのように処理をするのかを考えながら身につける方法で、ゲーム感覚で楽しみながらできるのが特徴だ。もしかしたら就活生は、グループディスカッションなどで行った経験もあるかもしれない。短時間で多くのタスクを処理していくため、その人が普段どのように仕事を進めているか、判断基準や価値観はどうなのか、などを客観的に観察することができるのである。
さて、このインバスケット思考能力が平均的に高いと言われているのが、医療の現場で働く看護師たちである。看護師は、様々な症状をもつ患者から同時にナースコールを受けた時など、どう処理をするのか瞬時に考えて行動することが日々求められている。自然とこの能力が鍛えられているのであろう。
昨年の4月から働き始めた新人看護師Yさんは、先輩ナースから、「どうして今それをやってるの!?」と叱られることが多かったそうだ。
現場でも、得意な仕事から始める人、同僚に合わせる人、苦手な仕事からやっつけようとする人と様々な看護師がいるということだが、「できるナース」は、インバスケット思考能力の高さが際立つようだ。
Yさんは、「がむしゃらに取りかかると結局余計に時間がかかり、効率が悪くなるのだなと痛感しました。生死関わる患者さんや分単位で容態が変わる患者さんもいるので、こういった考え方は必須ですね!」と語る。
そんなインバスケット思考能力を鍛える上で重要だと言われるポイントは、3点ある。
■優先順位を設定する
第一に、多数の案件を処理する際には、「優先順位」を設定するということである。Yさんは、「新人ですし、率先してナースコールを取るようにしています。コールがいくつも鳴っている時には、どの患者さんを優先するのかの判断が必要です。患者さんの体調が急変している時に、他の患者さんの体調が変化することもあります。臨機応変にやるべきことを整理し、適切に対応することが求められていますね。」と語る。ばたばたとパニックにならずに仕事に取りかかるには、優先順位づけは大事なポイントとなってくるのだ。
■影響度の大きさで判断する
ただ、慣れていないとどの仕事も優先順位が高い、もしくは平等のように見えてしまうだろう。
これについてYさんは、「点滴や薬の準備をしてから先輩にダブルチェックをしてもらいます。チェックには先輩の時間を多く取ってしまいますし、出払っていてお願いできないこともあります。時間までに必ず準備が終わっていないと、他のナースの時間を奪うだけでなく、患者さんへの投与が遅れるなんて最悪の事態も引き起こしかねません。これくらいで終わるだろうと思っていても意外に時間がかかったりするので、早めに準備に取りかかるようにしていますね」とのこと。
Yさんが語るように、「どんな損失が出るか?」「どの範囲に影響するか?」と自問自答しながら取りかかると良いようだ。
■適切な人に割り振る
Yさんは、「ベッドから落ちた患者さんと人工呼吸器のアラームがなっている患者さん、両方を一度に自分で助けることはできません。でも片方を誰かに頼む、助けを求める、など仕事を振るという選択肢もありますよね」とのこと。一人では手に負えないからといって問題を放置するのではなく、「これは自分にしかできないことか?」を判断し「適切な人に割り振る」という選択肢があることも忘れないでおきたい。
Yさんのような看護師が活躍する医療の現場だけでなく、常に複数案件を処理しなくてはいけないのがビジネスの世界だ。「できる社会人」になるには、すばやい状況判断と意思決定が不可欠となってくる。
(あらみり)
■ 今回ご紹介した以外にも、恋愛術や生活の知恵など、ナースの意外な情報を大公開中!:ナースフル×ウーマンエキサイト特別企画ページ
■ 取材協力:リクルートの看護師求人・転職パートナー「ナースフル」