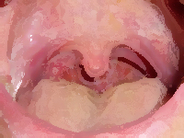「インターネットを使ったヘンな紙芝居をやります~」という声に誘われていくと、始まったのは「即席紙芝居」なるもの。
実はこれ、第15回メディア芸術祭でエンターテインメント部門審査委員会推薦作品に選ばれた、れっきとした1つの芸術作品だ。
会場に登場したのは、一見すると普通の紙芝居屋さん。だが、よく見れば自転車の荷台に取り付けられた舞台にはめ込まれていたのは、紙芝居ではなく、iPad!
昭和のエンターテインメントである紙芝居が最先端のデバイスで再現されるというのも斬新だが、それに加えて見せ方もユニーク。2枚の重なった絵を半分だけ見せてみたり、ゆっくり抜いてみたりと、まるで紙の紙芝居のように自在に操作しながら、場のコミュニケーションを操っていく。本のページをめくるような一般的なスライド操作とはだいぶ違う。
さらに驚いたのが、紙芝居の“即席”ぶり。たとえば、紙芝居(正確には“紙”ではないが……)を始める前に、その場にいた子どもの写真をiPhoneで撮影。すると、その子が話の中に登場し、重要な人物として活躍する。また、別の子との「何か欲しいものある?」「くるま!」という会話の後には、ちゃんと話の要所で車の画像が現れる。
つまり、その場に居合わせた人、そこでの会話によってのみ生み出される、1度限りの即席ストーリー、即興パフォーマンスなのだ。
イベント会場は電波状況が悪く、しばらくページをめくれないというハプニングもあったが、そんな状況も自然と会場の笑いを誘っていた。ただ見ているだけの紙芝居とちがい、参加している感が強く、周囲の人とのゆるい一体感のようなものが生まれてくるのだ。
即席紙芝居を企画しているのは、国立紙芝居の佐々木遊太さん。都内の科学館に勤める傍ら、近所の公園で、同じく国立紙芝居の佐々木慶子さんと共に紙芝居屋さんをしている。即席紙芝居の制作や即興の語りなど企画制作実演は遊太さんが担当し、諸規制の緩和や地域への理解といったインフラづくりは慶子さんが担当。即席紙芝居のほかに、昭和20~30年代の紙芝居も昔ながらの語りを継承し実演している。
2人の紙芝居を見るのは有料だ。カタヌキ兼紙芝居代として30~50円。昔の紙芝居屋のおっちゃんといえば、「お菓子を買わない子には見せないよ~」というスタンスが定番だったが、それと同じ。慶子さんいわく、
「お金のやりとりをするから社会になるし、子どもたちも盛り上がる。いろいろな知恵もついてくるはずです。現代の子どもたちが得にくくなっている、家庭や学校以外の居場所や、地域の大人との社会経験の場になってくれればと願っています」
もちろん、実施にあたっては行政にかけ合って公園の使用許可をとり、保健所から菓子行商鑑札を受けて指導にのっとって営業している。
「私たちの目的は、紙芝居屋さんを街角の風景に戻すことです」
と2人は強調する。昔は紙芝居屋さんも1つの職業だったが、いつしかさまざまな制約から生業として成り立たなくなってしまった。
ただ、遊太さん自身はもともと紙芝居師志望だったわけではない。
「以前からテレビやインターネットといった既存のメディアがしっくりこないと感じていたんです」
あるとき終電を逃して場末のサウナに泊まった遊太さんは、暮らしや職業の異なる者同士が、一緒にテレビを見て、同じタイミングで笑う状況に居合わせた。
「メディアがあることで、人が集い、皆で楽しむ場が生まれる。そんなメディアの在り方を志向するようになり、紙芝居に興味を抱くようになりました」
遊太さんは紙芝居師として経験を積みながら、今後の紙芝居のあり方を模索。そのなかで「インターネットを使って、個人的なことを皆で楽しむ」をコンセプトにした即席紙芝居が生まれた。
「即席紙芝居は、ほんのりとした共感の場を作品としています」
つまり、私がイベント会場で感じたあの一体感、独特の磁場こそが、作品そのものなのだ。
ちなみに即席紙芝居は遊太さんが制作したウェブアプリケーションで動いている。その場で撮影した子どもの写真を取り込んだり、子どもとの対話から得たキーワードを入力して画像検索で画像を取得する、といった仕組み。ストーリーのテンプレートは現在18種30話あり、もちろんすべてオリジナルだ。
「テンプレートの制作や、即興でつける語りなど、どうすれば子どもに受けるのか、表現として前例がないので、すべてが試行錯誤です」
なかには紙芝居の登場人物から子どもに電話がかかってくる話もあるという。
ネットというと1人で楽しむものだとばかり思い込んでいたが、知らない誰かと同時に楽しめ、共感できるメディアになりえるというのは目からウロコの体験だった。日本の文化である紙芝居の新たな形として、これからの展開も楽しみにしたい。
(古屋江美子)