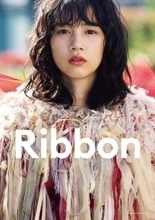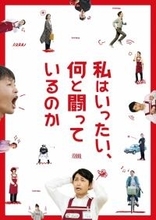佐一郎の周辺の人物も、そのモデルはだいたい見当がつく。息子の洋一郎(溝端淳平)は喜一郎の長男の豊田章一郎、甥の正二(椎名桔平)は喜一郎のいとこにあたる豊田英二と、歴代のトヨタの経営者をモデルにしていることはあきらかだ。また橋爪功演じる石山又造は、その名前を見ても、今回のドラマの原案の一つである本所次郎『小説 日銀管理』での同名の人物の役回りからいっても、喜一郎のあとトヨタ自工の3代目社長を務めた「トヨタの大番頭」石田退三を思い起こさせるのだが、ドラマの公式サイト「人物相関図」での紹介に《愛知自動織機社長。自動車に反対だったが、佐一郎の熱意で翻意》とあるのを読むと、喜一郎の妹婿で、豊田自動織機製作所の社長のほかトヨタ自工の初代社長も務めた豊田利三郎の立場にも近いような気がする。ドラマではおそらく、石田と利三郎のイメージを掛け合わせた存在として描かれるのではないだろうか。
このほか、ドラマに出てくる東京帝国大学工学部教授の隈沢和志(市川右近)のモデルは、喜一郎から請われて東大教授からトヨタ入りした隈部一雄でまちがいないだろうし、ドラマ中の日本銀行総裁・財部登(中村橋之助)は、終戦直後の日銀総裁・一万田尚登を、財部の秘書の山梨良夫(香川照之)は、やはり終戦直後に日銀名古屋支店長を務め、経営危機に陥っていたトヨタに2億円の融資を決断した高梨壮夫をそれぞれモデルにしていると思われる。
豊田喜一郎の生涯を描いた映像作品としてはこれ以前にも、1980年に公開された「遥かなる走路」(佐藤純彌監督・新藤兼人脚本)がある。喜一郎の役を6代目市川染五郎(翌年に9代目松本幸四郎を襲名)が演じたこの映画は、木本正次の小説『夜明けへの挑戦』(1979年)を原作にしている。木本はやはり映画化された『黒部の太陽』をはじめ、産業界を舞台にした実録小説を数多く著した作家だ。
原作はあくまで喜一郎を主人公としているのに対し、映画では、彼の父で自動織機を発明して現在のトヨタグループの礎を築いた豊田佐吉(劇中では田村高廣が演じている)の生涯にもスポットを当て、父から子へモノづくりの精神が継承されるさまがより強調されている。
具体的にいえば、喜一郎は父・佐吉の「これからは自動車だ」との遺言を継ぐ形で自動車事業に進出したと伝えられる。
これに対し、豊田家へ婿養子に入り自動織機製作所の経営を任されていた利三郎(映画では米倉斉加年が演じている)は、道楽ならともかく事業として自動車をやることをなかなか認めようとせず、たびたび喜一郎と衝突する。佐吉の遺志を貫こうとする喜一郎、その前に立ち塞がる利三郎という構図は、映画でも木本の原作でも変わらない。原作にいたっては利三郎が、妻の愛子までもが兄の喜一郎をかばって口ごたえするので、《所詮は俺には――この豊田という家の血は判らないのだろうか!?》と口惜しさを噛みしめる場面すらある。
しかしトヨタ創業前後について書かれた本をほかにもいくつか読んでいると、話はそれほど単純でもないらしい。佐吉の遺志を喜一郎が継いだという話は、たしかに彼自身がそのことを繰り返し記しているし、トヨタの社史でも強調されている。だが、亀田忠男『自動車王国前史』(1982年)は、佐吉受勲時における「芝居もどき」の話には懐疑的だ。じつはそれ以前から喜一郎は佐吉から何度も自動車をやれと言われていたらしい。むしろ、父からそう言われ続けながら喜一郎が数年間はためらって動かなかったことに、著者の亀田は注目している。
喜一郎が父から繰り返し言われながらも、すぐに自動車に手を出さなかったのは、すでに日本市場をアメリカのフォードをはじめ外国車が席巻していたからだ。はたしてこの状況で、国産車を製造して勝算はあるのか? これと前後して、喜一郎は自動織機特許の譲渡代金を得るため自らイギリス側と交渉を進めるなかで「世界の壁」を痛感していただけに、慎重にならざるをえなかったのではないか、というのが亀田の推測である。
利三郎と喜一郎の関係にしても、1930年11月に実業家・渋沢栄一の通夜に2人が同席した折、喜一郎が自動車事業に本格的に進出する旨を伝え、利三郎から合意を得ていたと喜一郎の秘書が書き残していたりする(和田一夫「正当性獲得と突出部依存による事業創造」、伊丹敬之ほか編『ケースブック日本企業の経営行動4』)。これが事実とすれば、利三郎はけっして頑なに喜一郎に反対していたわけではなかったことになる。
すでに1930年には、喜一郎は自動織機製作所内で小型エンジンの試作に着手していた。製作所内に自動車部が設置されたのは1933年、翌年1月には同社の臨時株主総会が開催され、定款の「会社の目的」に自動車の製造を加えることを決議、正式にゴーサインが出た。
本格的に自動車生産に乗り出した喜一郎らは、1935年に試作乗用車「A1型」を完成させる。しかしその直後、喜一郎は乗用車ではなくトラック生産優先へと方針を急転換した。これというのも、社内で乗用車製造への反対があらためて高まったことに加え、自動車製造が政府の許可事業になることが予想されたため、技術面でも販売面でも実績を上げねばならなくなったからだ。
販売に関しては、日本GM(米ゼネラルモーターズの日本法人)から、のちに「販売の神様」と呼ばれた神谷正太郎が引き抜かれ一切を任された。当時のトヨタのトラックは、まだ商品としては不完全だったが、セールスマンたちは日本の自動車産業を育てるためにもと売りこみに回り、故障が起きたときはいついかなる場合にも駆けつけて修理する体制を敷いた。
こうした努力の甲斐あって、1936年、国内の自動車産業の保護育成のためつくられた「自動車工業法」にもとづき、トヨタ自工は日産自動車とともに許可会社となった。
経営危機のなかトヨタ社内では労働争議が激化、喜一郎はその責任をとって1950年に社長を辞任する。直後に起こった朝鮮戦争で、トヨタは軍需トラックの生産により息を吹き返した。が、後任社長の石田退三から黒字が出るようになったと伝えられた喜一郎は、「それはトラックだけだろう。乗用車をやれんようなところは自動車会社とは言えん」とにべもなかったという。この頃、喜一郎は会社から離れて一人で構想を練り、乗用車の設計に取り組んでいた。
それでも経営が持ち直すと、1951年には首脳陣のあいだで「全部品を新規に設計した本格的な乗用車」の具体的な検討が始まり、翌年になると開発プロジェクトが始動する。同時期に喜一郎は社長に復帰するよう石田から説得され承諾していたが、その矢先、1952年3月に58歳で急死する(その3カ月後には長らく病床にあった利三郎も亡くなった)。
カリスマ的なリーダーを失ったあと、いかにトヨタは新しい乗用車「トヨペット・クラウン」を生み出したのか。
トヨタ独自の生産管理システムである「カンバン方式」が生まれたのも、乗用車の生産が本格化した頃のことだ。これはのちに副社長を務める大野耐一が、部品を無駄にストックしないという喜一郎の「ジャスト・イン・タイム構想」を踏まえて1950年代に採用したものである。当初大野が部分的に試行していたカンバン方式は、1960年代に入ると全社的に導入される。こうして着実に乗用車の生産台数は増え、「マイカー元年」と呼ばれた1966年には、トヨタでつくられる自動車のうち、乗用車の比率がついに過半を超えた。
喜一郎が偉大な技術者にして経営者であることはまちがいない。そのことはきっと今回のドラマを見ても(史実にもとづくフィクションとはいえ)わかるはずだ。しかし、喜一郎の活躍は利三郎をはじめ周辺の人々の存在を抜きにはありえなかっただろうし、彼の死後もその精神を継承しつつ、新たなものを採り入れて国産乗用車の普及を実現させた人たちがいた。くだんのドラマのタイトルが「リーダー」ではなく、複数形の「リーダーズ」となっているのも、そのような意味を持たせてのことではないかと私はにらんでいる。
「LEADERS リーダーズ」
脚本:橋本裕志
音楽:千住明
原案:『小説 日銀管理』(本所次郎著)、『トヨタ自動車75年史』
出演:佐藤浩市、香川照之、宮沢りえ、山口智子、橋爪功ほか
プロデューサー:貴島誠一郎、伊與田英徳
演出:福澤克雄
2014年3月22日(土)・23日(日)21時よりTBS系列にて放映
(近藤正高)