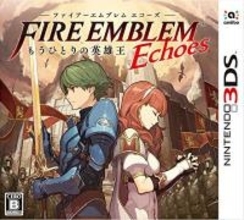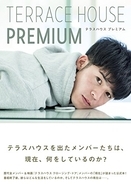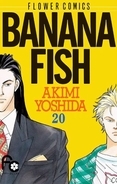著者は立命館大学映像学部の渡辺修司氏と中村彰憲氏で、渡辺氏は『ガラクタ名作劇場 ラクガキ王国』などを手がけた元ゲームクリエイター。
内容をざっと紹介すると、これまで曖昧だった「ゲーム性」という概念について、主に記号論の立ち場からメスを入れ、独自の定義を打ち立てています。「ゲームは現実世界と地続きの存在であるが、現実より挑戦意欲をかき立てる構造になっているため、ハマってしまう」・・・この構造のことを「ゲーム性」と呼んでいる、といっていいでしょう。
本書ではこの構造を「ルド」というモデルで可視化し、「パックマン」や「パズル&ドラゴンズ」をルドの連なりで分析するなど、ユニークな考察を進めています。しかしここでは内容や妥当性について、これ以上深掘りしません。というのも、筆者自身が編集協力でかかわっているからです。それよりも、少し俯瞰した視点で本書の位置づけについて紹介してみましょう。
そもそも「ゲーム性」の定義や、ゲームの研究が誰の得になるんでしょうか? 別に本書を読んでゲームが作れるようになる訳でもないのに。ここが本書のポイントです。
大前提として日本のゲーム業界では、専門学校が人材育成に対して一定の成果を上げています。業界的には賛否両論もありますが、専門学校の卒業生がゲームの開発現場で一定の割合を占めていることは事実です。そのミッションはシンプルで、学生を企業に就職させること。言い替えれば「ゲームを作れるようになる」ことがカリキュラムの骨子となっています(余談ながら海外では職業訓練的なコースを内在する大学も多く見られます)。
ところがゲームってトレンドがコロコロ変わるんですよ。典型例がソーシャルゲームで、ガラケー向けの「ポチポチゲーム」と、スマホアプリでは作り方が大きく違います。ポチポチゲームの作り方を学んで(そんな学校はないけど)就職できたとしても、技術の有用性が数年で下がっちゃうんです。その背景には絶え間ない技術革新があります。
だからといって企業は社員を簡単にリストラできない。アメリカでは全員クビにして、時流に即した社員を雇うところですけどね。そのため大学のカリキュラムも企業のニーズと結びつきやすい。産学連携が進む一方で、「人材使い捨て」型社会だとも言えるでしょう。
問題は専門学校が「今の人気ゲーム」の作り方を「表面だけなぞって」教えているように見えること。それよりも、どうせ長く雇用するのなら、より基礎的なことを学び、応用力を身につけ、将来にわたって活躍してくれる学生を雇用したい。そういった人材を育成しているのは大学・・・となるわけです。
でも、そういった学生は「ゲームを作った経験」があるわけではないし、全員が「ゲーム好き」というわけでもない。しかも昔ほどゲーム業界が輝いているわけではなく、優秀な学生を他の産業と取り合っている状況です。つまり大学として「よりゲーム産業に即した」学生の育成が求められている・・・はずです。
ところが、これが難しいんですね。専門学校なら答えがある。「今の技術」で「今のゲーム」が作れれば良いからです。でも大学が専門学校と同じことをしても意味がない。教員がゲーム開発について自ら研究し、その知見をもとに「未来のゲーム」を作り出せる人材を育成する必要があるわけです。
これがCGやプログラミングなど、過去の技術の蓄積が効く分野であれば、まだなんとかなります。ところがゲームデザインとなると困難です。過去の知見の蓄積がないからです。ゲームデザインは「発明」的なもので、個人の創造性に起因するところが大きく、学問のような積み上げが必要な領域とはそぐわない・・・そんな風に考えられてきました。
この「積み上げ」というのが学問の世界では重要です。どんな独創的で画期的な研究も、それだけではあまり評価されません。過去の学問体系とどのように接続されるか。それによって、真の研究に昇華する、といっていいでしょう。そこには「学問とは繋がりである」という価値観があります。巨人の肩に乗ることで、より遠くを見渡せるようになるのです。
もっとも、それだけに真に独創的な研究や、新しい研究分野が育ちにくい難点があります。ゲーム研究はその好例です。
そのため企業によっては自嘲気味に「ゲームの作り方を大学で教えられるわけがない。英語と数学だけ、しっかり教えておいて欲しい」といわれることもあるほどです。
こうした現状をかんがみて本書では、山のような先行研究の紹介が行われています。そして、ゲーム性を巡る探索が過去の知見とどのように接続されるかについて、たいへん丁寧に説明されています。渡辺氏のゲーム作りの知見がベースとなっていますが、それが丁寧にラッピングされている。「前例主義」「権威主義」といってしまえばそれまでですが、だからこそ学問的に説得力のある内容になっているといえるでしょう。
本書を読むとどんな得があるか。ゲームエンジンの普及で、3Dゲームっぽい画面を作って、キャラクターを動かすくらいなら、ホントに簡単にできるようになりました。ところが、そこから「ゲームをおもしろくする」ところで、多くの学生はつまずきます。「ゲームはなぜおもしろいか」について、ちゃんと考えた経験がないからです。
そのため学生制作といえば真似ゲーのオンパレードというのが普通です。
もちろん模倣を繰り返しながら、次第にオリジナルのゲームを作ってもらえればいいんですが、そこに何かの指針があればいいですよね。一方で教師側にとっても、そうしたテキストがあれば、より的確に学生を導くことができるでしょう。本書には、そのための知見がたくさん詰まっています。
ただ、ちょっと残念なのは、あまりに一歩ずつ丁寧に説明しているため、尻切れトンボ感が強いこと。紙幅の都合でラストがバッサリと切られた感じになっています。公式サポートページで解説記事がアップされる予定ですので、物足りなさを感じたらぜひ、チェックされることをオススメします。
繰り返しますが、本書は「ゲーム性」を巡る探索を、既存の学問のフレームワークを活用して整理した点が特徴です。元ゲームクリエイターの知見をベースとした学術書として、理想的な形だといえるでしょう。人によっては、まだるっこしく感じられるかもしれませんが、ゲームについてより深く知りたい人にオススメではないでしょうか。
(小野憲史)