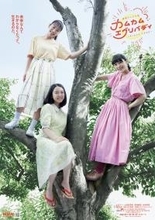生々しい愛憎や性、殺人などの描写は、小説や漫画なら大胆に描けても、実写になったとき、薄味なこともある。が、この映画は、濃度を保っている。主人公の花役の二階堂ふみと、花と愛情を交わす淳悟役の浅野忠信が色っぽい。ドロリと熱っぽい空気感を撮った監督は、『海炭市叙景』『夏の終り』などの熊切和嘉。ふたりの感情を、映像ならではのダイナミズムで描き出す。これを原作者はどう受け取ったのだろう。桜庭一樹に聞いた。
───映画を見て、いかがでしたか?
桜庭 小説から映画やアニメやラジオドラマ化するとき、テーマを生かすためには構成を変えなくてはいけないといつも思うんです。私は、小説の主人公の女の子・花を、不思議な価値観をもっているにも関わらず、読んだ人が、自分の事のように感じたり共感したりできるように書いたのですが、映画の場合は、花(二階堂ふみ)と淳悟(浅野忠信)のことを俯瞰で見て、現象としてふたりがいるというふうに見せようとしていると感じました。
───最初に、台本を読んで、意見を言ったりするものですか?
桜庭 最初に読んだとき、おそらく、ヨーロッパのノワール映画のようになるだろうと思ってOKしました。出来上がった映画を見たときも、脚本を読んだときのイメージに近かったです。私は、もっと静かなイメージをもっていましたが、役者さんによって、さらに激しい感情が入ったものになった気がしました。
───幸福な映画になったということですか。
桜庭 私は、元々、熊切和嘉監督作品が好きなんです。今から20年くらい前から「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」という、ぴあが主催している、映画の新人賞のようなものがあって。そこで賞をとると、お金を出してもらって、映画が作れるというシステムがあるんですね。熊切監督もそこの出身の方で、こうやって若い人がどんどんプロになっていくの、かっこいいなあと思って見ていたんです(編中:矢口史靖、園子温、李相日、深川栄洋、石井裕也などが出身者)。熊切監督の作品では『揮発性の女』(04年)が一番好きで。
───どういうところが好きなのですか?
桜庭 若い男が年配の女性のところに、最初は男が積極的だったのに、だんだん醒めてきて、女のほうが本気になっちゃうっていう、静かに空恐ろしい感じになって。ああ、辛い、辛いって(笑)。一回、見るのを休みたくなるくらいなのに、映画は止まらないという(笑)。最後、男が犯罪で捕まりそうになったとき、女がスクーターでやってきて「乗って」というと、男が乗ってくれるシーンがすごく好きなんです。「乗ってくれたー!」という瞬間の、女の幸せみたいなものが良くて。
───ずいぶん前からお好きだった監督ということで、これまで交流はなかったのですか?
桜庭 撮影の見学に行ったときが初対面でした。北海道の紋別での、流氷シーンの撮影のときです。そもそも、熊切監督が、北海道出身ということで、北海道をよく撮られていたこともあって、安心してお任せしたんですよ。流氷が来たら撮ることになっていた日の朝、ちょうど接岸したらしくて、二階堂ふみさんと藤竜也さんが流氷の上でやりとりするシーンの撮影がありました。
───寒くなかったですか?
桜庭 すごく寒かったです。小説を書く時点で取材に行ったことがあって、そのとき寒かった経験から、重装備で行きました。見学していて、書くのは簡単でも、撮るのは大変だなと思いました。当然ですね(笑)。
───文学でも、横や縦の視点移動が意識されているんですね。
桜庭 エンタメ作品を書くときは、気をつけています。放っておくと地味な描写になってしまうので。特に、流氷のシーンは重要なシーンで、ギリシャ悲劇やシェイクスピア劇のように劇的にやる必要があったんです。現代の日本が舞台だと、なかなか劇的なロケーションがないところ、流氷は格好の舞台でした。
───大変!
桜庭 監督は「二階堂が急にふと消えたんですよ」「ひとが落ちるときって、派手に落ちるのではなくて、無言で消えるんだと思いました」とおっしゃっていました(笑)。
───実際は意外と地味だと・・・。今度は、そういうリアルを書いてはいかがでしょうか(笑)。
桜庭 地味になっちゃって、「縦移動は大声で」って言われてしまいます(笑)。
───監督とは、いろいろ話をしましたか?
桜庭 ご挨拶したくらいです。印象的だったのは、監督が、私がすぐそばにいるにも関わらず、舞台俳優のようなものすごく大きな声で、「問題作にします!」とおっしゃって。さっき、挨拶したときは、「どうも、熊切です」と小声だったのに、「問題作にします!」だけ大声だったから、びっくりしました。あとで制作会社の方に聞いたら「あれは、まわりへのアピールだ」って(笑)。
───監督は、周囲へのパフォーマンスも、しないとならないんですね(笑)。
桜庭 オペラ歌手の声のようでした(笑)。
後編に続く。
(木俣冬)