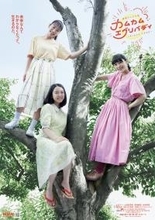旧約聖書の「出エジプト記」を元ネタにした映画です。
1956年、チャールトン・ヘストンとユル・ブリンナー主演の「十戒」と基本的には同じ。
エジプトで奴隷として働かされていたヘブライ人たちを救出し、紅海を渡ってカナンに向かう物語です。
監督は「ブレードランナー」や「グラディエーター」のリドリー・スコット。
聖書の「出エジプト記」は、全く知らなくてOK。全然違うから。
人が死にまくる、大規模パニック映画です。
たとえばエジプト人に「10の奇跡」が及ぶシーン。
災厄のドミノ倒し。追い打ちに追い打ちを重ねます。
一つ目は水が血にかわる。これをワニに食べられた人間の血で表現。
人喰い映画ファン必見。
血に染まった川から逃げたきたのはカエルの群れ。
道を歩けないくらい多い。寝ていたらベッド中カエルまみれになるシーンは見もの。
カエルの死体が山になる。ここからぶよ爆弾が大量発生。
さらに大きな虻が街中にあふれかえる。
エジプト人たちが全身を虻に覆われ、死んじゃうくらい。
虻が運んできたウイルスで家畜に疫病がはやって、バタバタと死亡。
刺された人の身体にははれものが生じます。
さらにでかい雹が降った上に、イナゴの大群が街中の食べ物を食いつくす。
リドリー・スコット監督「(脚本を)完全に書き直した。劇中の出来事が本当に起きたかもしれないとか、起きなかったかもしれないといったことを考慮しながらね」
『エクソダス:神と王』リドリー・スコット監督&クリスチャン・ベイル 単独インタビュー - シネマトゥデイ
災厄のピタゴラスイッチは、自然現象としても捉えられるんじゃないか?
カエルが腐ったら確かに虻が寄ってくる。イナゴが突然襲来することもあるだろう。
……いや、あまりにも数が多すぎるけどさ。
本来の「出エジプト記」13章では、神が光で照らして紅海まで民を導きます。ここを完全にカット。
40万の民を従え、モーゼ自身が道を選択しないといけなくなりました。
また、有名な紅海を渡るシーン。「十戒」と異なり、はっきりとは海が割れません。
だから、モーゼは迷ってしまう。
自分たちがエジプトを脱出できたのは「神の奇跡」だけなのか、「偶然」なところもあるのか。
モーゼ役のクリスチャン・ベイルは「彼は完全に人間だった。とても情熱にあふれていて、気まぐれで、自分本位の考えをしがちで、人生を通して多くの間違いを犯す(中略)彼はその時点で、極端に矛盾を抱えた人物になるんだ」と語ります。
神からの予言を受けたシーンはほぼない。
むしろそりが合わず、自分で決断しようとしちゃって、大失敗ばかり。
エジプト人がヘブライ人を奴隷として、残虐に扱うシーンが多々あります。
でもそれ以上に、エジプト人がごみくずのように死ぬ。
神にそこまで信仰もってないモーゼ。途中エジプト人側に同情してしまいます。
いくらなんでもやりすぎですよと。
一人の男が、とことんまで追い詰められた時どうなっちゃうのか。
それを表現するには、もう手に負えないよーってなるくらい、とことんド派手なディザスター・ムービーじゃないといけなかった。
「グラディエーター」でも男の苦悩を描いたリドリー・スコット。
今回はモーゼをヒーロー預言者ではなく、厄介事に巻き込まれてしまい「選択しきれなかった人間」として描いています。
矛盾とか丸無視で、面白いビジュアル作りにこだわるのも、なんともスコット監督らしい。
紅海で、エジプト軍が海に飲まれる前。
なぜかヒキの画面で誰も居ない中。小さく馬が一頭だけ走り抜けて、戻ってきた巨大な波に飲まれます。
波のとんでもないデカさは伝わった。よく使うサイズ比較用の万年筆みたいに。
でもその馬どこから走ってきたんだよー!
これでも飽きたらなかったのか、全く聖書にないパニックシーンが何度も出てきます。
あんまりにも豪快すぎて、悲惨を通り越して気持いいのなんの。
絵的な面白さへのこだわりが多すぎて、お腹いっぱいです。
ぐーっとカメラを引いて撮影した荒野の壮大さ……の中でばんばん人が死んでくのが痛快になっちゃう映画。
モーゼの悩みはとても大きい。
でも虫の大群も人の群れも、スクリーンの中ではあまりに小さくて、なんだか同じに見えてしまう。
(たまごまご)