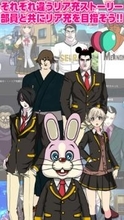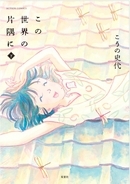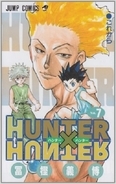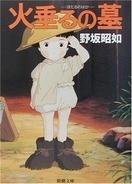そもそも女性アイドルはいまや男の独占物ではない。それは実際にアイドル、とくにメジャーなグループのコンサートに一度でも行けばわかる。というのも、そこに来る女性ファンの数は最近になって確実に増えているからだ。私の見に行ったかぎりでも、たとえば乃木坂46のコンサートに来る女性ファンには、いわゆるアイドルオタクのイメージとは違うおしゃれな子たちが目についた。それはグループのイメージをそのまま投影しているかのようだ。というか、同性のアイドルを応援する女性たちは、コンサートともなれば着るものなど身だしなみにはそうとう気を配って行くものらしい。
振付師・竹中夏海の新刊『アイドル=ヒロイン 歌って踊る戦う女の子がいる限り、世界は美しい』によれば、女性ファンのなかには応援するアイドルの衣装を真似して自作していく人もいるという。そういえば、私が昨夏行ったPerfumeのコンサートでもメンバーのコスプレをしたファンをちらほら見かけた。最近ではでんぱ組.incのように、ステージ衣装のレプリカを公式で発売しているグループもある。また衣装を真似しないまでも、推しているメンバーのカラーを「ドレスコード」と同じく意識しながら自分の衣装をコーディネートしてコンサートに行くという女性ファンは多いようだ。
本書の著者である竹中は、数多くのアイドルグループのダンスを手がける一方で、自身もまた大の女性アイドルファンである。アイドルの送り手と受け手、2つの立場での体験にもとづく本書の内容は、前出のコンサートでの身だしなみのような女性ファンと男性ファンの違いにせよ、両者の共通点にせよ、深くうなづけるところが多い。たとえばグループのなかのある特定のメンバーを応援する、いわゆる「推す」という行為についての次のような説明には、男性ファンである私も強い共感を抱いた。
《推しは選択肢の中からあえて選ぶなら、ではなく「この子じゃないとダメ」という何かが見つかったときにできるのだと思います。「AKBの中なら誰」ではなく、「この子のここが好き」になる。「推す」という行為の原動力は、まさにそういったところからくるのでしょう》
本書がとりわけユニークなのは、女性アイドルを応援する同性ファンが増えていることについて「美少女戦士セーラームーン」を補助線に説明しているところだ。先ほどの衣装の話に関していえば、セーラームーンもアイドルもその衣装は普段はとても着れないようなデザインであり、だからこそ女性の変身願望を掻き立てるという点で共通する。また先述のとおり現在のアイドルグループにはメンバーごとに担当カラーが決まっているところも多いが、セーラームーンではそれを先取りするように各キャラごとにカラーが設定されていた。
物語として見ても、セーラームーンとアイドルには意外にも共通点が多い。これについて竹中は古今東西のヒーロー物に共通する三箇条「不思議な出生」「怪物退治」「財宝の獲得」をあげて考察している。セーラームーンもアイドルも必ずしも自らの希望で戦士やメンバーになったわけではない。
アイドルの場合、敵や目標はグループごとに違ってくる。ここで竹中が例にあげるのは、自分の教え子であるアップアップガールズ(仮)=アプガだ。アプガはハロプロエッグ(ハロー!プロジェクトの研修生)を実質クビにされた7人で結成されたグループである。それゆえその目標も、まずは自分たちの強制卒業が発表された横浜ブリッツでの単独ライブを自力で満員にすることに定められた。それがクリアできたら新たな目標として、今度はハロプロの聖地・中野サンプラザを目指すことになる。昨年行なわれたアプガの中野サンプラザ単独公演のチケットは即日完売したという。
こんなふうにセーラームーンとアイドルを重ね合わせ、アイドルを戦士にたとえてみせる竹中の持論は、彼女自身が小学校時代にセーラームーンのミュージカルに出演した経験(これについては本書でもくわしく書かれている)に裏づけられたものだ。それだけに説得力がある。
竹中は本書の第一部の最後で、アイドルの寿命についても言及している。アイドルはごくかぎられた時間のなかで活動するものであり、いつかは引退するか卒業してアーティストなり俳優なりべつの次元に移行するか、グループなら解散するものだと思われていることが多い。
だが男性アイドルではSMAPがその常識を打ち破った。
《我々アイドルファンは、推しへと感情移入しているのです。おばさんになったら興味が失せる人ばかではない、推しているその子がこれからどう過ごしていくのか、許される限り見守りつづけたいのです》
竹中はまた、アイドル性というものを《技術論などの理屈を超えた「そのものの肯定」》と定義する。たとえばPerfumeなどは、出自はアイドルながらもはやその区分に収まらない存在となっている。しかし音楽性やパフォーマンスのクオリティがどれだけ上がろうとも、コンサートに来るファンは何よりもまず、あ~ちゃん・かしゆか・のっちという3人に会うことを楽しみにしている。そんなふうにファンを惹きつける魅力こそアイドル性というわけだ。結成から15年が経ち、構成メンバーをそのまま維持して全員が20代後半となったアイドル出身の女性グループという点で、Perfumeは現在唯一無二の存在だろう。インディーズ時代から見てきた私としても、彼女たちがどこまで活動を続けるのかぜひ見届けたい。
もちろん、メンバー交代が繰り返されるグループにだって魅力はある。女性アイドルの世界が全体としてより多様なものになっていけばいいのだと思う。
余談ながら、現在放送中のドラマ「問題のあるレストラン」の第4話(2月5日放送)では二階堂ふみ演じる元OLが幼稚園時代のセーラームーンごっこについて語る場面があった。考えてみれば、ひょんなことから集まった女性たちがレストランを開き、大手飲食会社を敵に回して戦うというあのドラマ自体がセーラームーンの物語と同じ要素で成り立っているといえる。アイドル好きの自分がなぜあのドラマにハマっているのか、『アイドル=ヒロイン』を読んでいて思いがけず気づかされた。
(近藤正高)