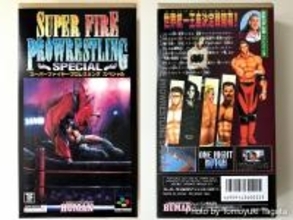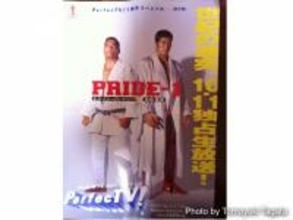264名が死亡した中華航空事故
1994年4月26日、台北発名古屋行の中華航空140便が名古屋空港の滑走路近くに墜落した。機体は大破、炎上し、乗員乗客264名が死亡、7名が重傷という大惨事となった。
この日の午後5時43分(日本時間)、台北国際空港を離陸した140便は、午後8時12分ごろ、名古屋空港に接近した。その1分後、管制塔に「着陸支障なし」という報告があったが、それからわずか2分後に「ゴーアラウンド(着陸やり直し)」と伝達が入った。
その直後、機体は急上昇し両エンジンから出火、そのまま飛行機は墜落。264名もの命が失われてしまったのだ。
中華航空事故の事故原因は?
事故後、調査委員会が調べた結果、墜落時に機体を操縦していたのは副操縦士であることが判明した。さらに着陸しようとした際、副操縦士の誤った操作で機首が上がり続けたことが最大の原因であることが分かる。
この副操縦士のミスに気づかずに機長が、操縦桿で機首下げを行ったため、機体はバランスを崩して急上昇。その後、失速して墜落してしまった。
これらから分かるように、この事故は操縦士による人為的ミスであったといえるだろう。だが、ミスを知らせる警告装置が装備されていなかったことなどにも問題があったともいえる。
調査委員会は最終的に「さまざまな要因が複合的に絡み合った結果、事故は発生した」と結論づけた。
コンピューターの進歩にともない、航空機の安全は向上し、事故もゼロになるかと思えた。しかし確かに安全は向上したのだが、一方でそれを操作する人間の理解不足といった新たな問題も生み出した。中華航空140便の墜落事故は、「コンピューターは絶対安全とは言えない」という教訓を我々にもたらしたのだ。