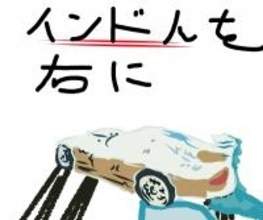何が起きた? 町が廃墟に
物語の主人公は青木照(テル)という中学生の少年。
修学旅行の帰りの新幹線に乗っていたテルは突然の大地震によって列車が横転し、トンネルの中に閉じ込められてしまう。
やがて崩壊するトンネル。ノブオは暗闇の中に消え、テルとアコは何とか生き延びて外に出る。しかし外には灰が雪のように降り注いでおり、街は廃墟となっていた。
一体、地上で何が起きたのか。テルとアコは、家族のいる東京を目指す。
天変地異に翻弄される人々の物語
『ドラゴンヘッド』がはじまったのは1994年10月。単行本が発売された1995年に阪神淡路大震災が起きたこともあってか、原因不明の天変地位と恐怖に翻弄される人々の物語は時代を象徴する作品として絶賛された。
地震や津波といった天変地異の描写が多い本作だが、当時鮮烈だったのは極限状態の中で露わになる人間の恐ろしさだった。
今では「心の闇」という言葉はかなり陳腐化したが、頭がおかしくなって全身にペインティングをして襲いかかるノブオの描写は今見ても鮮烈である。
天才と言われた「ドラゴンヘッド」作者
作者の望月峯太郎(現在は望月ミネタロウ)は、映画化された『バタアシ金魚』や『鮫肌男と桃尻女』などで知られる漫画家。偏執的ともいえる細かい描写は、デビュー当初から天才的と言われていた。最近では山本周五郎の小説「ちいさこべえ」を漫画化して、高い評価を受けている。
時代ごとに作風を大きく変えるのも望月の特徴で、90年代には、ある日、アパートの隣人を訪ねてきた長身の女に追い回される恐怖を描いた『座敷女』(当時はまだストーカーという言葉はなかった)で、突然ホラー漫画を描いて絶賛された。
『ドラゴンヘッド』は『座敷女』で試みた現代の恐怖をスケールアップさせた作品だと言える。
トンネルを抜け出したテルとアコは、ガスマスクをつけた少年と出会う。ここで登場するガスマスクは、地下鉄サリン時間が起きた際に自衛隊の化学防護隊がつけていたものだ。
行き詰まっていったストーリー
当時、望月峯太郎は、エア・ジョーダンのバスケットシューズやX-girlのTシャツといった流行りのアイテムを劇中に登場させていた。それはファンからはおしゃれな描写として評価されていたが、望月にとってはよりリアルな世界観を構築するために実在する商品や食べ物を描くのは当然だったのだろう。
ガスマスクの描写も、その延長上にあるものだったのかもしれない。第4巻では自衛隊から逃げ出した男たちにテルとアコが追われるのだが、その舞台となる廃墟の描写は明らかに阪神淡路大震災で崩壊した神戸の街並みの写真を参考にしている。
その結果、SF的なものではなく、自分たちの住んでいる世界の延長線上に存在するような鬼気迫る廃墟の描写に成功した。
しかし、そうやって現実の衣服や風景を劇中に取り入れていった結果、圧倒的なリアリズムは獲得したが、漫画としては、どんどん行き詰っていったと言える。
「ドラゴンヘッド」は作者も手に負えず?
天変地異のオチについては、富士山が丸ごと消滅するような火柱が上がって地震と津波が起きて、最後に東京にも火山らしきものが生まれたことが、とりあえずの理由として描写される。そんな絶望的な状況下でテルとアコが生きていくことを決意して物語は終わっていくのだが、今見ても、綺麗に終わったとは言えないラストだ。
また、物語が後半になるにつれて、明らかに説明台詞が増えていくのも本作の評価を下げている理由だろう。描写に定評のある望月ですら、『ドラゴンヘッド』のスケールに対して手が負えなくなっているのが、見ていて痛いほどわかった。
『ドラゴンヘッド』は、途中から隔週連載となったのだが、話がまったく進まなかったので、多くの読者は単行本で読んでいたのではないかと思う。
実際、休載も多かったため話はわかりにくかったのだが、今振り返ると、何が起きているのかわからない極限状況を延々と描き続けた本作の面白さは、続きがわからない状態で雑誌で読んでいた時が一番面白く、単行本でまとめて読むと、どうしても印象は変わってしまう。
2003年に妻夫木聡と、当時・松田聖子の娘として話題となっていたSAYAKA(現・神田沙也加)の主演で映画化されたが、ダイジェスト的な作りだったため、連載当時に感じた恐さは抜け落ちていた。
やはりあれは、リアルタイムで先がわからない中、読んでこそ成立した作品だったのだろう。
「ドラゴンヘッド」を今読み返したい理由
連載終了とともに忘れ去られていった本作だが、今回、読み返してみたいと思ったのは、2011年の東日本大震災以降の日本の状況が95年以降の阪神淡路大震災以降の日本の空気と、どこか重なるものがあるのではないか。と、思ったからだ。
だとすれば、『ドラゴンヘッド』も、違う読み方ができるのかもしれない。
再読した印象としては、インターネットも携帯電話も登場しないためか、一世代前の漫画だという印象は否めない。
しかし、トンネルの中に閉じ込められて外のことがわからない不安や、食料調達に困難しながら徒歩での移動を強いられる場面などは、逆に東日本大震災直後の混乱した空気を思い出した。
インターネットこそ登場しないが、テレビやラジオから時々聴こえてくる謎の声や、デマに翻弄される姿は、ここ何年かネットのSNSで体験してることにそっくりである。
90年代に置き去りにされた『ドラゴンヘッド』だが、むしろ今、一番読み返すべき漫画なのかもしれない。
(成馬零一)
ドラゴンヘッド(1) (ヤングマガジンコミックス)