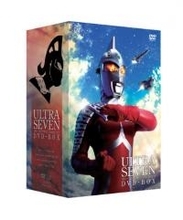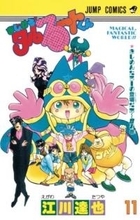長崎の雲仙普賢岳にて起きた大火砕流を覚えているだろうか? 死者、行方不明者合わせて43名、負傷者を9名出す大惨事になったが、この災害は報道の在り方を考えさせられる一つの大きな出来事でもあった。マスコミが大バッシングをくらうことになったこの災害を、改めて見てみよう。
雲仙普賢岳の大災害
長崎県の島原半島。雲仙市と島原市及び南島原市にまたがる形で、雲仙普賢岳は存在する。九州を代表する活火山で、周辺は雲仙温泉として観光名所としても有名であるが、記憶に残るのは、1991年に起こった大災害だ。
大火砕流により大規模な被害が発生したのは、1991年の6月3日だ。それ以前より周辺地域は噴火活動が活発だった。特に危険が訴えられるようになったのは、土石流被害が見られるようになった頃からである。これは降り積もった火山灰が豪雨により流されることで発生する現象で、マグマが噴き出す火砕流と共に、警戒されていた。
特に被害を受けていたのが、島原市と深江町で、境界線に一部位置する水無川へと土石流が流れこみ、これが一気に下流の有明海の方へと目がけ下って行く。最初の被害が見られたのは1991年5月15日でそれ以来、19日から21日にかけて連続的に発生している。島原市は度重なる避難勧告を出し、住人の避難は無事に行われていた。
5月20日に溶岩ドームの出現が確認され、日々拡大し続けた。
結果的に報道陣を始め、地元の人中心に結成された消防団など、多くの人の命が奪われてしまったのだ。
マスコミに対する問題点
被害の大きさとともに焦点となったのは、取材陣の取材体制についてだった。撮影ポイントである北上木場町の県道は、避難勧告地域のエリア内で、安全な場所だという認識の甘さが大被害に繋がった。また一部取材陣が、留守宅の電気を使って撮影に使う機材の充電をしたり、電話を無断使用したりといった問題も露わになっている。取材陣のモラルの低さが浮き彫りにされた。
この悪影響は取材関係者だけではなく、地元の住民にももたらされた。取材陣のマナーの悪さを注意する意味合いも含め、避難勧告エリア内で平然と取材を続ける記者たちのそばには、監視をする消防団員がいた。
普賢岳大火砕流の被害は、自然災害の恐ろしさを知る出来事であると同時に、報道の在り方についても議論されるテーマにもなった。後世、忘れてはならない事象であると言えよう。