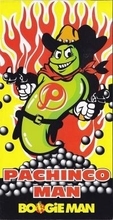大方の予想を裏切り、桂歌丸の後を継いで6代目司会者に就任したのは春風亭昇太であった。
遡ること25年。1990年代初頭、この昇太を含む期待の若手落語家を集め、落語ではなくコントや大喜利クイズなどをやらせるという実験的深夜番組があった。
「平成名物TVヨタロー」である。
若手落語家が番組の中心だった「平成名物TVヨタロー」
「平成名物TV」という冠をみて、おやっと思った方もいるであろうが、「ヨタロー」は、イカ天こと「平成名物TV三宅裕司のいかすバンド天国」の次の時間帯(より深い時間帯)に放送されていた。
夜中の3時とか3時30分のスタートだったので「イカ天」までは観た人もここまでは観ていなかったかもしれない。
司会は松尾貴史、早坂あきよ、そしてヨネスケ。番組の中心となったのは、関東の各党派から選ばれた3人1組の若手落語家たちである。
伝統ある落語協会から「落協エシャレッツ」、桂歌丸が現在の会長である落語芸術協会から「芸協ルネッサンス」、 円楽一門会から「円楽ヤングバンブーズ」、立川流から「立川ボーイズ」とそれぞれ名付けられた4組が、互いの党派のプライドをかけて争ったのがこの番組であった。
キレたヨネスケ、退出する騒動も
番組開始当初は、落語とは勝手の違うコントネタ作りに若手落語家メンバーは大いに苦戦。
審査を担当していたヨネスケがネタのあまりのひどさに「こんなものはテレビでオンエアしてはいけない。冗談じゃない」とキレて退出するといった騒ぎもあった。
そんな中、いち早く順応し、コントでも才能を見せつけていたのが立川ボーイズの面々である。
メンバーは、現在では著書「赤めだか」で知られ、最もチケットが取れない落語家と言われる立川談春、のちにシネマ落語などでも才能を発揮し兄弟子談春より先に真打ちとなった立川志らく、そして彼らの兄弟子朝寝坊のらく(のちに廃業・故人)の3人であった。
コントコーナーでは8割方立川ボーイズが勝利しただけでなく、大喜利のコーナーでも、志らくが今ならほぼオンエアできないような危険なネタで笑いをかっさらっており、この番組では圧倒的に立川流が強かった。
一目置かれた存在だった春風亭昇太
一方、芸協ルネッサンス所属だった春風亭昇太は番組開始前からすでに落語家として注目されており、一目置かれた存在であった。
コントコーナーでも芸協のネタは昇太が狂言回しとなるものが多く、冒頭彼が「相撲、それは日本の国技」「塾、それは学歴社会が生み出したもうひとつの教育機関」などと言って始まるのが常であった。
この時点では昇太はまだ二つ目で、年齢も30歳そこそこだったのだが(番組終了後の1992年に7人抜きで真打に昇進)、驚くべきことに現在とほとんど雰囲気がかわっていない。トレードマークのメガネも髪型も声もほぼ一緒である。女性誌は、美魔女や大高博幸先生のアンチエイジングのコツを探るより前に、彼に秘訣を聞いた方がいいのではないだろうか。
後に市議会議員になったメンバーも
落協エシャレッツの一員として番組後期に「明るい下ネタ担当」として活躍した三遊亭窓里は、現在落語家との二足のわらじで川越市議会議員を務めており、すでに6期目である。近年、30年近くにわたる妻のモラハラ・DVを理由に離婚したことでも話題になったが、当時の下ネタ連発の裏にそのような家庭環境があったとは驚きである。
余談ではあるが、当時、秋山豊寛さんが日本人初の宇宙飛行士として飛び立った際、宇宙からの中継をつなぐはずが、この「ヨタロー」のスタジオが数分間映ってしまうという事件があった。総集編でこのVTRを観た三遊亭窓里がすかさず下ネタで「ドッキングに成功」と返したことをよく覚えている。
「ヨタロー」は、若手落語家たちが、慣れないコントやバラエティに対し、おろおろとしながらも懸命に頑張っていた熱い番組であった。
番組最盛期には、一部出演者に10代の女性追っかけがつくほど人気が出たが、当時まさかこの番組から未来の笑点司会者が生まれるとは思ってもみなかった。
ちなみに、当時の出演者は、故人となった朝寝坊のらくを除き全員が真打ちとして落語家を続けている。
(前川ヤスタカ)
※イメージ画像はamazonより春風亭昇太2 26周年記念落語会-オレまつり