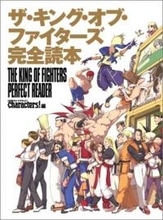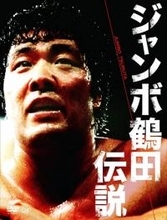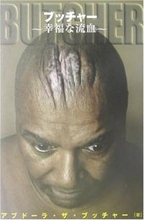何とも目を引くキャッチコピーではないでしょうか。まるで若者が、ありふれた日常会話的気軽さで“殺し”について語らうようなこの一文は、『バトル・ロワイアル』という映画の本質、そして、その背景にあった当時の社会状況までもが明晰に表現されているようです。
『バトル・ロワイアル』(バトロワ)が公開されたのは、今から16年前。藤原竜也、柴咲コウ、栗山千明、前田亜季、山本太郎など、今振り返ると錚々たる面々が出演するこの作品のテーマは、ずばり「中学生同士の殺し合い」でした。
凄まじい戦争体験をした監督の深作欣二
年に一度ランダムに選ばれた中学3年生のクラスが、新世紀教育改革法・通称「BR法」により、脱出不可能な無人島で最後の一人になるまで殺し合いをするという本作。
何とも突拍子もない筋立てですが、メガホンをとった深作欣二監督は太平洋戦争直撃世代。彼には中学時代、米軍の艦砲射撃で吹き飛んだ友人の遺体をかき集めたという、凄まじい実体験があります。
そのときに募らせたのは、「国家への不信」「大人への怒り」だったのだとか。国家という得体の知れないものの力で、人と人とが殺し合う理不尽さ……。それを痛いほど心に刻み込んだ監督だからこそ、この現実離れした空想話にリアリティを持たせることができたのかも知れません。
衝撃的な少年犯罪が立て続けに起こった2000年
しかしこの当時、「リアルな若者の殺し合い」の映画を上映するというのはかなりリスキーなことでした。理由は、2000年という年が少年犯罪の年だったからに他なりません。
5月1日には、愛知県豊川市で主婦殺人事件、2日後の5月3日には西鉄バスジャック事件が発生。どちらの犯人も、17歳の少年。さしたる私怨も憎悪もなく人を殺めた恐るべき若者が相次いで登場したことを受け、マスコミの報道は加熱。「キレる17歳」「理由なき犯罪世代」などと形容して、世間の恐怖心を煽っていました。
映画の規制を求める運動が起こる
こうした背景もあり、『バトル・ロワイアル』は公開開始前から「少年犯罪を助長する恐れがあるのではないか」と懸念されていました。当時の衆議院議員の石井紘基氏などは、本作の規制を求める運動を立ち上げ、国会で文部大臣へ映画に対する政府の見解を求める質疑を行ったほどです。
そのため、本作はR15+指定を受け、主人公たちと同年代の中学生が映画を観られない事態に。一番観てもらいたい層が劇場に来られないということで、深作監督は映倫と相当、やり合ったといいます。
ビートたけしが語った「暴力描写がグロテスクでなければならない理由」
確かに、本編はグロテスクなシーンの連続。草刈鎌で首を狩り、ボーガンで胸を貫き、ナイフでめった刺しにし、マシンガンで殲滅する……。作中何度、血しぶきが飛び散ったか分かりません。キャストの危機迫る演技の甲斐もあって、人が殺される場面は、かなり痛々しくみえます。
しかしながら、出演者の一人・ビートたけしはかつてテレビ番組で語っていました。「暴力シーンは痛々しくなくてはならない」と。彼のいうところによると、暴力描写というのは、観ている人にその怖さ・恐ろしさを伝えるためにあるべきだ、とのこと。だからこそ、彼の撮る映画は、暴力描写が過激なのだそうです。
一体、何が青少年の悪影響になり、好影響になるのか……。
マスコミで度々議論の対象となった『バトル・ロワイアル』は、報道によって逆に注目度が増し、興行収入31.1億円で、2001年度の邦画興行収入ランキング3位という大ヒットを記録。リスクを承知の上で、タイムリーなテーマに切り込んでいった深作監督をはじめとする製作者側の勝利といえるでしょう。
(こじへい)
※イメージ画像はamazonよりバトル・ロワイアル [DVD]