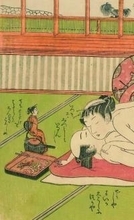“超合金の生みの親”のキャリアが一冊にまとまった
パイ インターナショナルが2月21日に、大作を発売しました。その名も、『オール・アバウト村上克司 スーパーヒーロー工業デザインアート集』(税込4,200円)なる一冊。

皆さん、村上克司氏はご存知でしょうか? 彼の肩書を一言で表すと、「工業デザイナー」になります。
では、駆け足で村上氏の半生を辿っていきましょう。カーデザイナーを目指していた村上氏ですが、物理的な条件から金属自動車を多く製造していた玩具メーカー「バンダイ」へ入社。そして10年後に退社し、家電やインテリアを手がける工業デザイナーの道を歩むこととなります。しかし、このフリー時代の体験は村上にとって厳しいものだったらしい。そして1年後、バンダイ時代の上司から誘われた村上はポピーへ入社。腹を決め、テレビキャラクターというジャンルで腕を振るうこととなります。
その後、村上氏は道なき道を歩み始める。TVアニメーション『マジンガーZ』を観た村上氏は、当時流行していたミニカーのコンセプトからインスピレーションを獲得。ディテールの効いた精巧感、そしてズッシリとした重厚感を取り入れて『超合金マジンガーZ』という商品にたどり着きました。
村上克司は“超合金の生みの親”です。

同書の構成・執筆を担当したタルカスの五十嵐浩司さんに、より詳しい解説をしていただきましょう。
「『超合金』はダイキャストを主素材にロボット玩具を作り出すという発想そのものが発明ですが、さらに村上さんはそこへ変形・合体という“機能”を盛り込みました。これでダイキャストの重量感、クールな手触りに加えてテレビと同じ変形や合体遊びができるようになります。テレビと同じデザイン、機能を備えた玩具で遊ぶことができる……今では当たり前のコンセプトを発明したのが、村上さんなのです。このスタイルは、現在も子ども向けの『スーパー戦隊ロボ』、大人向けの『超合金魂』にそれぞれ受け継がれています」
1975年、村上氏は『勇者ライディーン』にて遂に番組企画へ参加、主役メカニックに関する提案を行っていますが、これはテレビと玩具のギャップを生まないための企業努力の一貫です。
国内外から“村上克司作品集”の要望が寄せられていた
“村上克司作品集”の出版については、今まで国内外から数多くの要望が寄せられていたそう。しかし作品集の編纂には困難が伴う事情があり、なかなか企画を進めることができませんでした。
それでも、なんとかこのタイミングで出版したかった理由があるのです。
「来年2018年は、村上克司さんが工業デザイナーとして活躍を始めてから45年目となります。この機会を逃さずに今度こそ……という思いが、ついに本書の企画を実らせることになりました」(五十嵐さん)
それにしても、壮観です。『勇者ライディーン』から続く、伝説の工業デザイナーの仕事がこの一冊に凝縮されているのだから!



「村上さんご本人が厳選した作品を歴史順に見ることが、この一冊では可能となります。もちろん、多くの初公開作品も見どころです。
あの作品もこの作品も、あれもそれも村上克司の仕事だった!
こういう資料を手にすると、読者側の世代感によって興味が大きく異なっていくはず。ちなみに私は1978年生まれなのですが、やはり80年代前半の作品アートに熱くなります。特に熱くなったのは、こちら。

『宇宙刑事ギャバン』のデザインも、村上氏による仕事です。ギャバンのデザインは、村上氏がかねてより温めていたものが採用されたそう。「既存のヒーローとは異なる概念から生まれたギャバンは、1960年代のウルトラマン、1970年代の仮面ライダーに続くエポックメイキングと言える」とは、同書による解説です。いやー、当時はそういった背景を全く知らずに作品とだけ対峙してました。まぁ、当たり前なのですが……。
「本の最後には村上さんの作品年表もありますので、『こんな仕事もしていたのか!』という驚きも感じてもらえると思います」(五十嵐さん)
たしかに、アニマルモチーフを取り込むなどキャラクター性をより強化した『太陽戦隊サンバルカン』も村上氏の仕事で、『世界忍者戦ジライヤ』の敵・味方の多くは村上氏が提案していただなんて初めて知った! なんと全部、同じ人が手掛けてたんですね……。
もちろん記者とは別の世代にも、村上氏の工業デザインは深く浸透しています。ところで、工業デザイナーとしておよそ45年のキャリアを誇る村上氏のファン層の中心にいるのって、主にどの辺りの世代なのでしょうか?
「『超合金』に憧れた50代前半から、1990年代に村上さんが手がけられた『ゴジラVSメカゴジラ』『疾風!アイアンリーガー』『ウルトラマンパワード』のファン世代である30代前半まで、幅広い層が存在しています」(五十嵐さん)
村上克司の工業デザインアートの特徴とは?
村上氏の45年のキャリアについて一気に触れた今だからこそ知りたい。村上氏による工業デザインの特徴、ならではの要素として、どんなことが挙げられるでしょうか?
「工業デザインの発想からロボットやヒーローをアウトプットすることが、村上さんならではのデザイナー哲学です。村上さんはデザイン段階で立体を見据えた構築を行っており、デザインとしての良さと立体化した時の完成度が両立していることが特徴となっています」(五十嵐さん)
様々な作品を形にするために、村上氏は様々な壁を乗り越えてきました。
(寺西ジャジューカ)