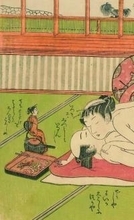幼児に読み聞かせをしていると、ふとしたときに笑ったり、驚いたり、ぽかんと口を開けたりとさまざまな反応を見せる。そうした幼児の反応は実に面白いものである。
ところで、笑ったり、喜んだり、驚いたりするということは、お話を理解しているということなのだろうか。知覚・認知に関わる脳機能に関する研究を行う、東京医科歯科大学 認知神経生物学分野の泰羅雅登教授に、幼児は絵本などのお話の内容をどこまで理解しているのか聞いてみた。
読み聞かせを受ける子どもの脳内では「心の脳」が活発に
泰羅教授によれば、幼児への読み聞かせの最中、幼児の脳内では次のようなことが起こっているという。
「読み聞かせを受ける子供の脳内では、私が“心の脳”と呼んでいる大脳辺縁系が活発になるという結果が研究によって得られました。大脳辺縁系とは喜怒哀楽を感じる部位です。幼児への読み聞かせは、幼児の感情を豊かにし、健やかな “心の脳”が育つために役立っているのではないかと分析しています」
幼児はどこまで話を理解できているのか?

ところで、1~4歳くらいまでの幼児は、絵本などの読み聞かせで、物語をどれくらい理解できているのか。
「言語発達は個人差が大きいので、幼児期にどのくらい意味を『理解』しているか、一概にいうことはむずかしいです。また、仮に意味を『理解』をしていたとしても、幼児でそれを確認するのは極めて困難です。物語の意味が『理解』できるのは本人の言語能力に依存するので、年齢が上がり、言語能力がついてくれば、当然『理解』は進むことになります」
確かに幼児は幼児だからこそ、それを理解しているかどうかの判定はむずかしい。では幼児が読み聞かせの最中、笑ったり、驚いたりする反応を見せるのはどういう理由があるのだろうか?
「読み聞かせが“心の脳”に直接はたらきかけているからです。言葉の意味を『理解』するのではなくて、読み手の語りの抑揚や、語調、語感を“心の脳”が『情動的』に感じ取っているからです。
『理解』の解釈を広げて、『情動的』に『感じる』ことを『情動的』に『理解』しているといってもいいのかもしれませんが、『理解』というには無理があると思います。」
幼児は、「情動的」に、物語を理解している可能性はあるようだ。とはいえ、それは理解と呼んでいいかどうかは分からないという。
幼児に読み聞かせをするとき、「意味分かってるのかな?」と感じるときには、“心の脳”で聞いているのだと思って、心・情動の成長を促すのに役立っているのだと思うのが良さそうだ。
(石原亜香利)
取材協力
東京医科歯科大学 認知神経生物学分野
泰羅 雅登(たいら・まさと)教授
http://www.tmd.ac.jp/cnb/index.html