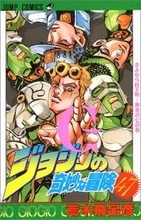この『涙活』に例を求めるまでもなく、いつの時代も「感動の涙を流したい」という需要は一定数存在します。本稿で紹介する『一杯のかけそば』も、まさにそんな「泣ける」コンテンツの一つでした。
日本中を感動の渦に巻き込んだ『一杯のかけそば』
1992年には、渡瀬恒彦主演で映画化もされた『一杯のかけそば』。
80年代後半に「読む人誰もが涙するという幻の童話」という触れ込みで、一大ブームを巻き起こした感動実話の内容は次の通りです……。
1972年、大晦日の夜。札幌のそば屋へ、2人の幼子を連れた貧相な身なりの女性がやってきました。注文したのは、150円のかけそば1杯だけ。苦しい懐事情を察した店主は、何もいわず、そばを1.5玉分に増量して提供します。美味しそうに1杯のかけそばを分け合う母と子。親子は父親を事故で亡くしており、3人にとって父の好物だったこの店のかけそばを食べることが、年に1度の贅沢だったのです。
その年から、毎年大晦日の晩にやってくるようになった母子。店主にとってもこの親子へそばを出すことが、12月31日の恒例行事になっていました。
しかし、ある年から母子はぱったりと来なくなりました。それでも、毎年、母子のために席を空けておく店主。そして時は流れて、最初に親子が現れてから14年後の大晦日。成人して医者と銀行員になった2人の子供が母親と共にやってきて、3杯分のかけそばを注文するのでした……。
衆議院予算委員会でも朗読される
なかなか良い話ではないでしょうか。
もともとは作者が全国を行脚し、口演で披露していた一杯のかけそばでしたが、1988年に書籍化されると、口コミでじわじわと人気に。1988年の大晦日には東京FMの『ゆく年くる年』で朗読され、1989年1月22日には産経新聞が取り上げます。
ついには、衆議院予算委員会審議の席で、大久保直彦・公明党書記長が竹下登首相への質問として引用するという、まさに社会現象ともいえる盛り上がりをみせます。
時はバブル最盛期。飽食の時代に対する警鐘、あるいは忘れかけた古き良き日本人の慎ましさ・人情を伝える逸話としての側面が、ブームに拍車をかけたことも見逃せません。
「涙のファシズム」と批判したタモリ
その後もしばらくは、中尾彬、武田鉄矢、森田健作らがワイドショーで日替わり朗読をしたり、作者の後援会が結成されたりと、一向に吹き止むことのなかったかけそば旋風。
しかしながら、このブームに疑問を呈するタレントもいました。タモリです。
感受性は人それぞれで、何が心の琴線に触れるかなど十人十色。にも関わらず、「これ泣けるでしょ?」という、感動の押し売りが無関心の人にまで次々と及んでいる事象が、タモリには奇妙な全体主義のように映ったのでしょう。
こうしたタモリの発言と呼応するかの如く、実話と銘打った「一杯のかけそば」の創作説が度々議論されるようになるなど、ブームは次第に沈静化していったのです。
すっかりケチがついてしまったせいで、創作だとしても良い話だった同作の価値が地に落ちてしまったことは、残念という他ないでしょう。
(こじへい)