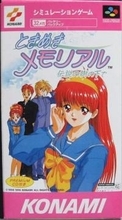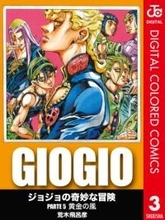何かといえば、これ、『聖飢魔II』の構成員(バンドメンバー)が使用する『悪魔用語』なるものです。
なんという芸の細かさでしょうか。しかも、設定倒れのイロモノではなく、歌唱・演奏・ライブパフォーマンス・閣下のトーク、あらゆる面において、超1級のエンターティナーなのだから、長きに渡って繁栄するのも頷けます。
『聖飢魔II』と同じにおいがした『カブキロックス』
そんな「悪魔」をコンセプトにした同バンドの地球デビューは、1985年のこと。それから5年後の1990年。『聖飢魔II』同様、アメリカの『KISS』リスペクトなビジュアルに、日本の伝統文化「歌舞伎」の要素を盛り込んだロックバンドが登場します。その名も『カブキロックス』。
デーモン閣下が地球制服のために地獄から襲来した悪魔だと自称すれば、こちらは、元禄3年(1690年)から現代へタイムスリップして来た歌舞伎役者だといいます。
初めて現世に降臨したのは、1989年10月14日。TBS系でかつて放送されていた深夜番組『平成名物TV 三宅裕司のいかすバンド天国』においてでした。
『TOKIO』の替え歌『お江戸-O・EDO-』をひっさげて登場
『イカ天』で彼らは、楽曲『お江戸-O・EDO-』を披露。
同曲は、沢田研二のシングル『TOKIO』のまんま替え歌(本人たちはカバー曲だと言い張っていましたが)。ところどころ、「TOKIO♪」⇒「OEDO♪」、「やさしい女が眠る街♪」⇒「やさしいおなごが眠る街♪」、「A to Z♪」⇒「イロハニホヘト♪」といったように、歌詞を変更してはいましたが、基本的にほとんどオリジナルと変わりません。
他にも、ライブ=狂言雷舞、曲目=演目、ギター=六味線、ベース=四味線、ドラム=洋太鼓などと、江戸時代風の呼称をあてることにより、コンセプト性を打ち出そうとしていました。
そんな彼らに対する『イカ天』審査員の評価は概ね低調。
TBS春の番組キャンペーンキャラクターにも抜擢された!
しかし、視聴者に与えたインパクトは絶大だったようで、『イカ天』出演以降、カブキロックスへはさまざまなメディアから出演オファーが殺到。ヤングジャンプで表紙グラビアを飾ったり、ボーカルの氏神一番がTBS春の番組キャンペーンキャラクターに抜擢されたりと、一時はものすごい持ち上げられ方をしていました。
そして、1990年5月21日。シングル『お江戸-O・EDO-』で、彼らはとうとうメジャーデビューを果たしたのです。
決定的だった、カブキロックスと聖飢魔IIの違い
『お江戸-O・EDO-』は売上20万枚のヒットを記録。その後も数曲リリースしましたが、いずれもパッとせず。結果、カブキロックスは、“『お江戸-O・EDO-』だけの一発屋”として、世間から認知されるようになったのでした。
どうして彼らはすぐに消えてしまったのでしょうか? おそらく最たる原因は、カブキロックスのフロントマン・氏神一番が「元禄時代生まれ」というコンセプトを、うまく使いこなせなかった点にあるといって良いでしょう。
たとえばテレビ出演の際、氏神の一人称は「拙者」であるはずなのに、油断して「俺」と言ってしまったり、江戸生まれなのについつい実年齢を答えたりと、要するにこの人、うっかりミスが多いのです。徹頭徹尾「吾輩は~」と言い、年齢を聞かれても、常に「実年齢+10万」を欠かさない閣下とは、えらい違いです。
「非常に不利だったと語る設定
また氏神は、友人の伊集院光へ「江戸時代という設定は、キャラを演じるうえで非常に不利だった」と漏らしていたようです。
たしかに、カブキ・江戸というコンセプトは、『聖飢魔II』が、「ゼウスの妨害=何等かのアクシデント」「改造手術=閣下の骨折」としたような、ユーモアある“遊び”があまり出来なさそう。
何はともあれ、今も活動しているカブキロックス。彼らが『あの人は今』的番組以外で取り上げられることは、果たして、この先あるのでしょうか……。
(こじへい)
※文中の画像はamazonよりNOW&BEST ~今昔詩歌集~