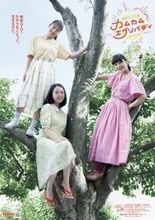聾唖の女が辿る、差別と暴力の旅路
開拓時代のアメリカ。小さな村で助産師を営む聾唖の女性リズは、年の離れた夫とその連れ子である息子、そして夫との間に生まれた娘と共に暮らしていた。
ある日、村の教会に新任の牧師が現れる。屈強な体と厳しい信仰心を持つ牧師は、村人と共に礼拝に来たリズに対して「汝の罪を罰しなければならない」と告げる。その礼拝で、突如として臨月の女が産気づく。難産となったため、やむなく母親の命を救うために子供を殺して取り上げるリズ。しかし、この事件をきっかけに、リズは村人たちから避けられるようになる。
リズと一家の生活は一変。自宅には子供を殺されたと逆恨みする父親が押しかけ、家畜の羊を皆殺しにされてしまう。さらに牧師は度々リズの家に現れ、一家に危機が及ぶまでに。牧師はなぜそうまでしてリズに執着し追い詰めるのか。果たして牧師は何者なのか。そこにはリズの壮絶な過去が関係していた。
タイトルの『ブリムストーン』は花の名前などにも使われている単語だが、元は「燃える石」を意味する古英語。「Fire and Brimstone」で旧約聖書などに登場する「灼熱地獄(Inferno)」の意味になるという。このタイトル通り、本作はまるで地獄めぐりのような過酷な内容だ。とにかく映画自体の構成がよく練られており、4章構成であることにきっちりと意味がある。というのも、『ブリムストーン』は2章以降リズの過去に遡って「なぜこうなったのか」を掘り返す構成をとっており、その章ごとに時系列が切り替わる仕組みなのだ。2〜3章にかけて、リズが直面したおぞましい過去が明かされることになる。
そこで描かれるのは、目を背けたくなるような女性への過酷な差別と暴力だ。厳格で暴力的な父親によって妻や娘はバシバシ鞭打たれ(なんせ鞭がすぐ横にある環境で生活しているのだ)、口答えできないように金属製の変なマスクを付けさせられる。娼婦たちは歩いているだけで暴言を吐かれ、一方的な契約によって娼館(劇中に登場する娼館の名前がよりによって「Inferno」で、タイトル「Brimstone」の意味ににかかっているのが上手い)に縛りつけられているから逃げ出すこともできない。観客はリズと共に、そんな地獄を巡る旅に出る。希望が生まれては粗暴な男たちによって潰され、抵抗といえばこれ見よがしに首をくくって目の前で死んでやる程度のことしかできない。
更にいえば、差別の構造が存在するのは男女間だけではないことを『ブリムストーン』は示してみせる。
この暴力まみれの地獄のようなアメリカを生き延びた女として、リズを演じるダコタ・ファニングの見た目は猛烈に説得力がある。ダコタ・ファニングの風貌は、見た目で年齢がわからない。少女のようでもあるし、角度によっては老婆のようでもある。めちゃくちゃな修羅場をくぐった人間特有の老け方に見えるのだ。しかも子役からの叩き上げなので演技が上手い。リズは話すことのできない役柄だったが、声が出せないのに手話だけでがっちり感情を表に出していた。今までアメリカの安達祐実とか言ってヘラヘラしていたが(多分そんなことを言っていたのは筆者だけだと思うけども)、本当にごめんなさいと言いたい。すいませんでした!
説得力のあるバイオレンス、そして最後に残る希望
『ブリムストーン』には暴力的なシーンが多い。
特にリズたち女性が振るう暴力は説得力抜群だ。なんせそれに至るまでの凄まじい境遇の描写がこれでもかと積み上げられているので、彼女らが銃や刃物を手にとって命がけの抵抗を試みるシーンでは「いけいけ!いてもうたらんかい!」と手に汗を握ってしまう。彼女らの暴力からは、はちきれるような高揚感と、その裏にあるやり場のない怒りと悲しみがはっきり見えるのだ。
そして重要なのが、男は殺すことができるという点である。劇中、まるで亡霊や怨念のようにリズを追い詰める牧師だが、人間である以上どんな男でも撃てば穴が空いて死ぬし切れば血を出して死ぬ。女たちにとって最後の希望はその一点である。それを知っている男たちは、男を殺した女に対して極めて残酷になることも『ブリムストーン』は描写する。しかし、暴力こそが最後の一手である以上、女たちは後も先もない最終手段として、怒りと共にそれを躊躇なく選択していく。この暴力の取り扱い方には舌を巻いた。
かくして、西部の荒野に血風吹きすさぶ暴力まみれの一大叙事詩が立ち現れる。
【作品データ】
「ブリムストーン」公式サイト
監督 マルティン・コールホーベン
出演 ダコタ・ファニング ガイ・ピアース エミリア・ジョーンズ カリス・ファン・ハウテン ほか
1月6日より全国順次ロードショー
STORY
開拓時代のアメリカ。家族と共に暮らす聾唖の女性リズの元に謎めいた牧師が現れる。リズに執着し、執拗に彼女を追い詰める牧師は、とうとうリズの家族にまで危害を及ぼす。牧師とリズの間には、秘められた過去があった。
(しげる)