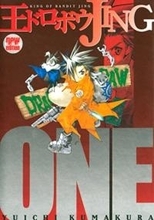子どもの頃、憧れのヒーローは“巨人の背番号8”だった。
「4番サード原」を追いかけながらプロ野球を覚え、大人になると「原監督」の采配を楽しんだ。

反逆のヒーロー・原辰徳
リリー・フランキーが名著『おしゃれ野球批評』(DAI-X出版)の中で書いた傑作コラムでこんな描写がある。たいした職もなくふらついていた20代のある日、友人としみったれた定食屋に入る。無愛想なオヤジが今日も不味いトンカツを揚げている。そんな店の隅に置かれた油まみれのテレビから流れる野球中継。終わっている空間、その空間が悲しいかな似合ってしまう自分。その時だ。突然、カウンターの中のオヤジが「うるるあぁぁぁっ!! やったぁぁぁぁー!!」なんて雄叫びを上げる。身を乗り出して狂喜乱舞するオヤジ。油まみれのブラウン管の向こうでは、原辰徳がダイヤモンドをゆっくりと回っていた。逆転ホームランだったようだ。
なんて完璧なシーンなんだろう。これが70年代の王や長嶋ではちょっと違う気がする。90年代のゴジラ松井や由伸でもないと思う。しみったれた定食屋のテレビでさえない男たちの心を揺さぶるのは、“80年代の原辰徳”が最もよく似合う。チャンスでポップフライを打ち上げ、周囲からボロクソに叩かれながらも土壇場で劇的なホームランをかっ飛ばす。俺たちまだ終わってないのかもなあ……。スマートで野球エリート的なイメージとは真逆で、現役時代の原はボンクラ野郎どもが感情移入できる反逆のヒーローだったのである。
厳しい状況にも耐え続けた現役晩年
突然だが、そんな原辰徳の90年代中盤を知っているだろうか? 92年神宮球場でのあの伝説のバット投げホームラン以降の背番号8、年齢的に35歳を過ぎたあたりの93年から95年の原は現役晩年の厳しい時期だった。ドラフトで松井秀喜が1位指名され、FA移籍で中日から落合博満がやって来る。ヤクルトから広澤克実やハウエルも加入した。いわば80年代は常に巨人の顔だった男が徐々に主役の座から外れていく斜陽の季節。93年はプロ入り以来続けてきたシーズン20本塁打以上の記録も途絶え、初の規定打席未到達。
手元の95年9月21日付の日刊スポーツ一面を見ると『やめるな〜ッ原』の大見出し。「涙の380号、お立ち台で絶句…事実上の引退宣言」と書いてある。前日の中日戦で76試合ぶり(!)の第4号アーチを放った原に対し、東京ドームの客席から当時はまだ珍しいスタンディングオベーションが起こった。試合後のヒーローインタビューでは「たまに出ても、これだけのお客さんが声援を送ってくれて……」と涙する37歳の若大将。球場全体を包む大歓声。巨大補強をした当時の長嶋巨人において4番人気投票アンケートをスポーツ番組で取ると、テレビ3局ともぶっちぎりで原がトップだった。なのに開幕後は競争すらさせてもらえず出番を失い、自身の打順で「代打一茂」をコールされ、チームメイトですら「あんな扱いはない」と怒りを覚える状況でも原は耐えた。
今、自分があの頃の原の年齢に差し掛かりふと思う。もしも、自分が窓際に追いやられ以前のように仕事ができなくなったら、背番号8と同じように振る舞えるだろうか……と。野球選手でも営業マンでも、バリバリの現役プレーヤーとして最前線で戦えるのは10数年だろう。
例えば、転職希望を会社に伝えると引き継ぎの関係で最後はメインの仕事から外されることも多々ある。「えっこれまで会社に貢献してきたのに最後コレ?」なんて思いがち。でも見る景色が変わると意外な発見があるかもしれない。自分の置かれた立場や年齢を受け入れ、次のステップへの準備期間と数カ月我慢するのも長い人生において無駄にはならない気がする。そう「夢の続きがある」と引退試合で宣言した1995年の原辰徳のように。
史上最年少で野球殿堂入りを果たした松井秀喜は『原辰徳-その素顔-』(三修社)の中で、現役晩年の原先輩に対してこんな思い出を語っている。
「引退される年(95年)は、心中穏やかではなかったと思いますけど、文句をひと言も言わず、じっとベンチに座って、グラウンドに声を出して、チームを応援しているんです。

【プロ野球から学ぶ社会人に役立つ教え】
誰だって歳は取る。“中年の反抗期”に陥らないようご注意を。
(死亡遊戯)