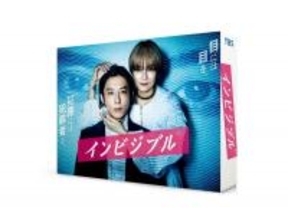「どこにもない国」というタイトルだけ聞くと、ファンタジーのようなイメージを思い浮かべる。

難民となった日本人
終戦時、満州に在留した日本人は150万人とも170万人ともいわれる。戦争末期のソ連侵攻により傀儡国家「満州国」は崩壊、日本政府もGHQ(連合国総司令部)の支配下に置かれていて対処できず、現地の人々はまったく行き場をなくし、危険にさらされた。暮らしていた国を失い、母国からも見捨てられた満州の日本人は、まぎれもなく難民であった。「どこにもない国」というタイトルからはそうした意味も読み取れる。
そんな過酷な状況にあって在満日本人を帰国させるべく立ち上がったのが、今回のドラマの主人公である丸山邦雄(演じるのは内野聖陽)をはじめとする3人の人物だ。終戦直後の混乱のなか同胞を救うべく命がけで行動した人たちがいたことを、きっと多くの人がこのドラマで知ることになるだろう。しかし本作は、単なる英雄譚や美談に終わることなく、なぜ彼らは危険を冒してまで動かざるをえなかったのか、その背景などにも迫ることになりそうだ。大森寿美男は次のように意気込みを語っている。
《三人の功績を題材にしたドラマは、未知の歴史を知る機会になり、視聴者は感銘を得るでしょう。しかし、脚本家としては、単なる歴史の美談として話をつくりたくありません。彼らが成し遂げた行為の背後にあったリアルな感情を、登場キャストの言動に滲ませるのが脚本家としての野心です》(洋泉社MOOK『満洲 NHK特集ドラマ『どこにもない国』を巡る』)
本作で時代考証を担当する歴史学者の加藤聖文(人間文化研究機構 国文学研究資料館准教授)もまた、視聴者に向けてこのような希望を述べている。
《満洲を研究対象にしている者の立場からいえば、この作品を、単純に「満洲で悲惨な目に遭う人びとを帰国させた偉人がいてよかった」というドラマとして受け取っていただきたくないように思います。ある日、突然、日本という国が消滅したら、私たちはどうなるか? 無国籍の難民です。ご覧いただく方には、ぜひそこに想像力を働かせていただきたい》(前掲書)
日露戦争から「満州国」建国まで
ここで今回のドラマの舞台となる満州について振り返っておきたい。日本が中国東北部に進出したのは、1905(明治38)年、日露戦争の講和条約(ポーツマス条約)により、ロシアから関東州(遼東半島の先端部分)の租借権や南満州における鉄道経営権などの権益を獲得したときだ。同年には国策会社として満鉄(南満州鉄道株式会社)が設立される。満鉄は単なる鉄道会社ではなく、沿線地域(満鉄付属地)において役所の役割を果たすなど政治的・軍事的性格を強く持っていた。翌06年には、関東州の政務や満鉄の業務の監督にあたる関東都督府が設置される。この都督のもと、関東州と満鉄付属地の守備のため置かれた陸軍部は、のち1919(大正8)年に関東軍として独立する。
1931(昭和6)年には、関東軍が満州事変を起こし、東北部全域を支配下に置き、翌32年には、中国・清王朝の最後の皇帝であった溥儀を皇帝に立てて「満州国」を建国する。満州国は満州族・漢族・蒙古族・朝鮮族・日本人の平等・融和(五族共和)を謳ったが、その実体は、日本の軍人や官僚、財閥などが実権を握る傀儡(かいらい)国家だった。
満州国では、日本国内でも当時まだほとんど実現されていなかった大規模な都市計画のもとインフラ網が整備された。また、「満州産業開発5ヵ年計画」にもとづき、地下資源開発や製鉄所の建設など重工業化が推し進められる。ドラマの主人公である丸山邦雄が勤めていた昭和製鋼所も、満州国の産業の根幹を担った企業の一つだった。
満州にはまた、昭和恐慌により疲弊した国内の農村を救済するため、大勢の農民が派遣された。新天地での生活再建に希望を抱きながら移住した農民たちは「満蒙開拓団」と称され、満州北部のソ連との国境地帯に入植する。
住民の保護対策をとらなかった関東軍
しかしすべては太平洋戦争末期の1945年8月9日に始まるソ連軍の満州侵攻によって崩壊する。ソ連はこれに先立ち、同年4月に日ソ中立条約を破棄。5月になると沖縄戦が熾烈さをきわめ、本土決戦も現実化しつつあった。こうした状況を背景に、関東軍は大本営(戦時・事変における最高指導機関)の命令を受けて完全に戦時態勢へと切り替え、ソ連に対し、満州東南部と朝鮮半島北部を防衛するためのラインを定めた。このとき、全満州の4分の3にあたる北部および西部はソ連侵攻時には放棄することになったが、そこに住む開拓民や民間邦人には、その措置が知らされることはなかった。対ソ戦に備えてはまた、7月までに、満州にいる日本人の成人男性のうち、行政や警備・産業などに必要な者をのぞいた15万人を召集する、いわゆる「根こそぎ動員」が行なわれる。
一方で、関東軍は、在満日本人を保護するための対策を結果的にとらなかった。じつは、関東軍内部では、2月に「関東軍在満居留民処理計画」を策定し、ソ連国境周辺の老幼婦女子の退避と青壮年男子の召集の方針が立てられ、戦時態勢に移行した5月以降、その実施が検討されていた。しかし大本営がこの計画に対し、現地民の動揺を招き、ソ連軍の侵入を誘発する恐れがあると反対し、計画は頓挫してしまう(加藤聖文『「大日本帝国」崩壊 東アジアの1945年』中公新書)。
こうして住民に対してまともな保護対策がとられないまま、満州へのソ連侵攻が現実のものとなる。満州国の首都・新京(現在の長春)では、日本人居留民に対し8月13日までに避難するよう命令が出たが、長年蓄えてきた全財産をわずか数日で処分して逃げ出すわけにもいかず、結果的に満州にとどまる理由も愛着もなかった軍人家族が真っ先に避難列車に乗り込んでいくことになる。
ソ連軍は暴虐のかぎりを尽くし、関東軍が交戦を停止したあとも、大量殺戮や略奪、暴行が止まなかった。太平洋戦争末期から終戦直後における満州での民間人犠牲者は、日ソ戦での死亡者を含めて約24万5000人(うち開拓団員は約8万人)にのぼった。この数は東京大空襲や広島の原爆、さらに沖縄戦をしのぐ(『「大日本帝国」崩壊』)。ソ連との戦争ではこのほかシベリア抑留や中国残留孤児の悲劇も生まれた。ソ連との停戦と前後して満州国政府や関東軍、満鉄など中枢機関がことごとく消滅するなか、満州に取り残された人々は各地で日本人会を結成して自衛にあたることになる。
スタッフが語る前編の見どころ
在満日本人の引揚がようやく端緒についたのは、終戦から半年あまりが経った1946年3月、ソ連軍が満州から撤退を開始し、代わって中国の国民政府軍が進駐して以降である。引揚は米軍の輸送用船舶を貸与されて行なわれたが、そこにいたるまでには知られざる男たちの尽力があった――というのが、今回のドラマ「どこにもない国」のテーマということになる。
重いテーマだけに、ドラマ化にあたり制作者たちは苦心したようだ。演出を手がけた木村隆文シニア・ディレクターによれば、《ドラマである以上、エンターテインメントとして楽しめる作品でなくてはなりません》と、前編で《三人が満洲を脱出するところは、ハラハラドキドキするスリリングな冒険活劇のように》描いたという。また、中村高志チーフ・プロデューサー(制作統括)は、前編で留意してもらいたいシーンとして《雪降る奉天の町並み》をあげ、上海でのロケで《多数の中国人エキストラの協力の下、過酷な状況から引き揚げを急がなければという切迫感を表現できたと自負しています》と語っている(以上、引用はいずれも『満洲 NHK特集ドラマ『どこにもない国』を巡る』)。
なお、中村は大河ドラマ「風林火山」(2007年)のプロデューサーでもあり、このとき一緒だった脚本の大森寿美男と主演の内野聖陽と再び結集して本作を手がけることになった。
(近藤正高)