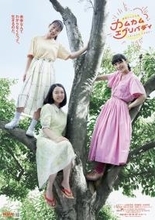無法状態となった満州
先週放送の前編は、前半からショッキングな場面も多かった。まず、主人公の丸山邦雄(内野聖陽)が日本の敗戦を知り、日本へ帰る方法を探るため、住んでいた鞍山から新京(現・長春)へ向かう途中、奉天(現・瀋陽)で足止めを食う。すでにソ連軍の支配下に入っていた奉天では、兵士による略奪や婦女暴行が横行していた。丸山もそこで、日本人の女性がソ連兵に連れ去られる光景を目の当たりにする。このとき止めようとした夫が射殺され、妻もあらかじめ用意していた毒をあおって自殺してしまう。そして目撃した丸山もまた身ぐるみをはがされ、命からがら家族の待つ鞍山に戻ったのだった。
鞍山でも、丸山の勤務していた満州製鉄(モデルは昭和製鋼所)がソ連軍に接収され、重要な機械類がソ連本国へと搬出する作業が続けられていた。彼は会社の事務室に行くと、電話も電信も手紙も、あらゆる通信手段がすでに断たれたことを知る。
住んでいた国を失い、外部からも完全に隔絶された満州の日本人。丸山は自分の家族を含め人々を何としてでも日本へ帰したいと思い立ち、満州製鉄の理事長だった岸本綾夫(片岡鶴太郎)に相談する。このとき岸本は元陸軍大将という経歴から、中国共産党に戦犯として逮捕されていたが、丸山は親しくなったソ連軍の将校に頼みこんで、3分間だけ面会の時間をもらう。
丸山が新甫と会って一緒に行動を始めてからまもなくして、岸本綾夫は処刑される。なお、岸本は東京高等工商学校(現・芝浦工業大学。新甫は同校のOBだった)の校長や東京市長を歴任した人物である。マンガ家・手塚治虫は彼の義理の甥にあたる。
リアリストと理想主義者
さて、今回のドラマの原案である『満州 奇跡の帰還』 >(ポール・邦昭・マルヤマ著、高作自子訳、柏艪舎)には、新甫八朗もまた満州脱出を真剣に検討していたことから、丸山と会うとすぐ意気投合したと書かれている。これに対し、劇中の新甫は、最終的に協力を約束するものの、その前に丸山を少し疑う。戦時中に徴兵され、敗戦後、朝鮮北部から命からがら逃げてきた新甫には、理想で押し通そうとする丸山の考えはあまりに現実を知らないと思えたのだ。
満州で財を築いた実業家である新甫は、劇中、リアリストとして描かれる。常に理想を語る丸山を新甫が「学者」と呼ぶ場面も何度かあり、そこには揶揄とも敬意ともつかないものを感じさせた。
ともあれ、新甫を通じてさらに武蔵正道(満島真之介)という中国語の堪能な青年も加わり、丸山たちは動き出す。まずは日本に渡り、政府と実質的な統治者であるGHQ(連合国総司令部)に、満州の惨状を訴える必要があった。そこで3人はあらためて奉天に赴き、人々の様子を見て回る。
街頭では行き場をなくした人たちが寒さに凍えていた。そこへさらに、麻袋を衣服代わりにかぶった人たちが現れる。この人たちは「麻袋(マータイ)部隊」と呼ばれた満州北部からの避難民だった。
先週の記事でも書いたとおり、満州を防衛していた関東軍は、ソ連軍の侵攻を前に、ソ連国境に近い満州北部は放棄するとあらかじめ決めていた。「麻袋部隊」の人たちは、そんな見捨てられた地域から、多くの仲間を喪い、身ぐるみをはがされながらやっと奉天にたどり着いたのだ。しかし奉天も、もはや安全な場所ではなかった。ドラマでは、避難所となった小学校で、多くの病死者が出て、まとめて埋葬される様子も出てきた。きっと現実はもっとひどいものであっただろう。
信念に生きる男の心からの叫び
このあと3人は、ソ連の制圧された満州からいかに抜け出し、中国国内を通って日本へと出港するか話し合う。当時、中国では、日本との戦争が始まって一旦は中断した国民党と共産党による内戦が再開しようとしていた。すでに共産党軍は日本の降伏直後よりソ連軍を後ろ盾に満州へ乗り込んでいる。一方の国民党はソ連との関係が悪化し、アメリカに接近しつつあった。丸山たちはこれに乗じて、国民党の協力を得ることで、脱出ルートを確保することを思い立つ。
幸いにも、武蔵の人脈を介して出会った国民党軍の参謀長・劉萬泉(りゅうまんせん)は親日家で、3人が中国国内を通行できるよう旅券を用意するとともに、護衛役として2人の青年将校をつけてくれた。
丸山は妻と子供たちを信頼する大連カトリック教会のレイモンド・レイン司教に預け、日本に向けて出発する。このとき不安を隠せない新甫の妻・マツ(蓮佛美沙子)に、丸山の妻・万里子(木村佳乃)は「私たち女性のほうが何倍も戦う力は強いのよ」などと言って励ます。しかしその万里子もまた、丸山を見送る前夜、彼から「神様にはいつも感謝してるよ。君のような強い人と出会えたことを」と言われ、「忘れないで。弱いから祈るんです」と真情を打ち明けるのだった。
命がけの脱出行に出た丸山だが、新甫と武蔵が財力や人脈を使って先導するのに対し、彼は道中で足手まといになることすらあった。途中、乗り換えのため降りた山海関では、便所を探していると、国民党軍の兵士に捕まってしまう。このとき、丸山は、銃口を向けられながら、劉参謀長から渡された旅券を見せて九死に一生を得た。旅券を見るや敬礼する将校に、御礼を言いながらその場を退出する内野聖陽の動きがいかにもコミカルで、それまでの緊張を解きほぐす。
だが、このあとさらなる試練が待ち受けていた。その原因をつくったのもまた丸山である。
だが、丸山の信念は揺るがなかった。翌朝、処刑されようかというときに、彼はレイン司教がマッカーサー宛ての陳情書を書いてくれたことを思い出す。すぐに現地に駐留している神父が呼ばれ、丸山は英語で強く訴えかけた。
「レイン司教は満州に残留する日本人のために懸命に尽くしてくれています。ポツダム宣言の第9条には『日本国軍隊は完全に武装を解除させられたのち、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的生活を営む機会を与えられる』とあります。それなのになぜ一般の日本人がいまも戦場に置き去りにされているのですか? アメリカ軍はすみやかに全ての外地居留日本人を解放すべきです! レイン司教はそう願っています。ここにいるのはその使者です。
まさに理想と信念を追究し続けてきた男の心からの叫びであった。こうして疑いは晴れ、釈放された彼らはついに日本行きの船に乗り込む。
もっとも、丸山たちが秦皇島で米軍に拘束され、一晩軟禁状態ですごしたのは事実ながら、処刑寸前まで行ったというのはあくまでフィクションらしい。それでもこの場面からは、史実を超えて、丸山邦雄という人物の信念、情熱がひしひしと伝わってきた。
この場面のヒントとなったのはおそらく、現実の丸山が新甫と武蔵に語って聞かせたという米大統領のリンカーンと無名の女性のエピソードではないか。その女性の夫は、南北戦争で出征し、任務中に居眠りをしたことを理由に処刑を言い渡される。これを知った彼女は赤ん坊を抱きながらホワイトハウスに赴き、リンカーンに夫を助けてくれるよう懇願する。話を聞き終えたリンカーンは何やら走り書きすると、それを陸軍省に持っていけば夫は許してもらえると言って女性に渡したのだった。丸山はこの話をしながら、《我々も、ひたむきに任に当たれば、きっと天が味方してくれるはずだよ》と語ったという(『満州 奇跡の脱出』)。
ショーケン演じる吉田茂に注目
史実ではまた、丸山が実際にレイン司教に書いてもらったのは、マッカーサーへの陳情書ではなく、丸山たちがすみやかに帰国できるよう経由地の天津駐留の神父に頼んだ手紙と、在東京ローマ法王使節ポール・マレラ大司教に対する紹介状だったという。丸山はこれらの書類とともに、もう一通、教会に妻と子供たちを預けて出発する際、一人の修道女から渡された手紙を満人服に縫いこんでいた。修道女の手紙は、時の日本の外務大臣・吉田茂の娘である麻生和子に宛てたものだった。
麻生和子は、カトリック教徒だった母の吉田雪子(つまり吉田茂の妻)の影響で、自らも洗礼を受けてカトリックに入信していた。ちなみに彼女の息子で現財務大臣の麻生太郎も「フランシスコ」の洗礼名を持つカトリック教徒だ。吉田茂もまた、1967年に亡くなったあと受洗し「ヨゼフ・トマス・モア」という洗礼名を与えられている(「CHRISTIAN TODAY」2017年10月12日)。
今夜放送の「どこにもない国」後編では、その吉田茂が登場する。演じるのが萩原健一と知ったときには正直、似てないと思ったが、予告編を見たところ、かなり本人に寄せている。演出の木村隆文シニア・ディレクターによれば、萩原は《吉田茂になりきろうと一生懸命で、ビジュアルはもちろん、声まで似せて、役づくり》したという。また、中村高志チーフ・プロデューサーも、脚本の大森寿美男も口をそろえて、丸山たちが吉田に対し、満州居留民の帰還を詰め寄るシーンを、ドラマの核心に据えたと語っている(洋泉社MOOK 『満洲 NHK特集ドラマ『どこにもない国』を巡る』)。はたして両者のバトルがどんなふうに描かれるのか、今夜の放送も見逃せない。
(近藤正高)