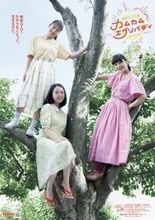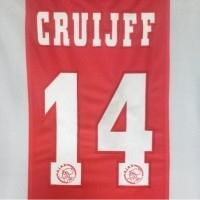東京から伊豆に引っ越してきた内気な少女「てこ」こと、大木双葉(CV:茅野愛衣)。
美しい伊豆の海と自然を舞台に、女子高生2人の友情を中心とした、優しい物語が描かれていく天野こずえの大人気コミック「あまんちゅ!」。
2016年7月には、天野のもう一つの代表作である「ARIA」シリーズのアニメなど、数々の名作を生み出してきた佐藤順一総監督の下、テレビアニメ化。
多くのファンの指示を集め、第2期「あまんちゅ!〜あどばんす〜」の制作も決定し、4月7日には第1話が放送された。

新キャラクターも登場する第2話の放送を前に、佐藤総監督インタビューを公開。
前編では、第1期制作時のエピソードを中心に語ってもらった。

第2期では、楽しさの中にある切なさにもフォーカス
──第2期の放送開始に先駆けて、3月中旬には第1話の先行上映会も開催されました。ファンの皆さんに第2期を届けることができた感想を教えてください。
佐藤 初日の会場で「『あまんちゅ!』をまだ観たことがない人はいますか?」と質問したら、1人もいなかったんですよ。第1期を観てくださった人が本当に楽しみに待っていてくれたことを実感しました。(第2期は)「楽しいは無限大」をテーマに「明るく楽しい『あまんちゅ!』」という方向だった第1期とは、少し角度を変えています。というのも、今の視聴者の皆さんは、楽しさだけでなく切なさとかも求めているのかなと思ったんですよね。第2期は少しそちらの方向に舵を切っているので、第1期から観て下さっているファンの方はもちろん、新しい層にも広がるのではないかなという期待をしています。
──ドラマの起伏をより大きくするというイメージでしょうか?
佐藤 第1期ではひたすら楽しい日々を描いてきましたが、その日々にもいつかは終わりがくるのかなという予感は、ぴかりもてこも感じていると思うんです。

──第2期について詳しくうかがう前に、第1期のお話から伺いたいのですが、「あまんちゅ!」をアニメ化するにあたって、特に大事にしようと考えたことを教えてください。
佐藤 まず一つには、天野こずえ先生の描かれる原作の空気感をそのまま写し取ろうということがありました。それは、ファンの人それぞれに感じ方が違うかもしれないので、最大公約数的なものが抑えられているかは分からないのですが。「ARIA」の後、「あまんちゅ!」の連載が始まった時、天野先生も作品の方向性を少し変えてきたなと思ったんです。「ARIA」はヒーリングコミックと言われているように、とにかく穏やかで、日々の小さな幸せを見つけていくような作品でしたが、「あまんちゅ!」は、もう少しアクティブ。コミカルな味も「ARIA」より多いなと感じました。そのあたりは、アニメも合わせた感じです。映像的なことで言えば、なんといっても風景の美しさですよね。一番難しかったのもそこです。特に、海の表現は手書きだけでは(作業量の)限界があるのでCGも使っているのですが、CGにも限界はあって。海の美しさをどこまで描けるのかは、試行錯誤もしたし大変でした。
──同じ自然でも、空や山などよりも海の方がさらに難しいのでしょうか?
佐藤 アニメの歴史上で見ても、すごくリアルに海の表現を描けている作品は、なかなか無いと思います。どこかでアニメの表現に落とし込まないといけないんですよね。CGだともう少しリアルな方向にも寄せていけますが、リアルにやりすぎると、アニメーションのキャラクターとの相性が悪くなったりもして。一番良い折り合いを見つけるのは難しかったです。
一番難しかった映像表現はレギュレーターから出てくる泡
──「ARIA」の舞台は、水の都ヴェネツィアがモデルとなった「ネオ・ヴェネツィア」でした。海が見えるのと、海の中にもぐるのとでは、描写の難易度は大きく変わるのでしょうか?
佐藤 「ARIA」の時は難易度を下げるために、鏡面のような波立たない海にして、チャプチャプと波打ったりする表現は極力やらないという判断で描いていたんです。でも、「あまんちゅ!」の舞台は砂浜や海岸なので、寄せて返す波を描かないわけにはいかないんですよね。水の表現の中でも、一番表現が固まるのに時間がかかったのは、レギュレーターから出てくる泡でした。映像を見てもらえると分かるのですが、水中の空気の泡って、口から出た時にはモヤモヤした球体なんですけれど、水面に向かって上がっていくと、だんだんお皿のようになっていくんですよ。第1期を作っていく中で、セル(手描き)の絵に合わせて泡らしく見せる CGさんのスキルも上がっていったので、2期ではそこも最初から上手く表現できています。その他、CGの苦手なところはセルで描くという使い分けも、第1期の制作を通して確立されました。

──CGの苦手な水の表現というのは?
佐藤 砂浜に波がザブザブ来ていて、キャラクターの足にその波が当たっているところなどですね。そういった、水とキャラクターの境目がゆらゆら揺れたりする表現は、3Dでは相当難しくて、セルでやるしかない感じです。
──この作品は、「ぴかり」こと小日向光と、「てこ」こと大木双葉の2人を中心とした物語ですが、第1期の中で、この2人を描く際、 特に意識されたことなどを教えて下さい。
佐藤 主人公は基本的にぴかりなんですけれど、てこが引っ越してきて、伊豆やダイビングのいろいろなことを知るという物語の構造上、描写の軸は、どうしてもてこになる。ぴかりはてこを導く立場なので、「ARIA」でいう(主人公の)水無灯里の位置にいるのは、てこなんです。第1期に関しては、その構造にあまり逆らわず、ある意味、てこの物語になっても良いかなと思い、後半に向けて(てこが)どんどん成長して、明るくなっていくように描きました。とはいえ、ぴかりを導き手としてだけ描いてしまうと、実在感が薄くなり過ぎてしまう。ああ見えても、悩んでいることなどもあるだろうし、それをどのように見つけて描くかは全編通してのテーマでした。ぴかりの描写では、いくつかポイントがありましたが、中でも最終回(第12話)で、てこに対して「ありがとう」と話すところは一番大きなポイントかなと思います。てこにとって、ぴかりはかけがえのない友達なんですけれども、それはぴかりにとっても同じなんですよね。

嫌だと思った事も考え方次第で変わるという大事なテーマ
──ぴかりは、すごく明るくて良い子ですが、クラス中の人気者という感じでもないんですよね。
佐藤 そうなんですよ(笑)。そこにも何かあったりするのかな、と想像はしているんですけどね。
──アニメオリジナルのセリフやシーンに関して、原作者の天野さんの監修は、どのような形で入っているのでしょうか?
佐藤 シナリオもコンテも観ていただいていて、何かあれば仰ってくださいという形なのですが、ありがたいことに「ARIA」の頃からわりと信頼していただいていて。「これは違います」といったご指摘があることはほぼ無いんですよね。もしかしたら、我慢してくださっているのかもしれませんが(笑)。
──てこの描写に関しても、特に重要だったシーンやエピソードがあれば教えて下さい。
佐藤 前の学校の友達を大切にしているという思いは、てこの軸になることだと強く意識していました。
(丸本大輔)
後編に続く