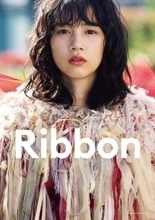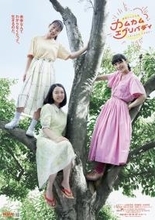私もこの機会に『NINAGAWAマクベス』を観に行った。
蜷川は同作の演出にあたり、役名もセリフもシェークスピアの戯曲『マクベス』(小田島雄志訳)そのままながら、舞台を大胆にも日本の戦国時代に置き換え、出演陣もこの時代の衣装で登場させた。さらに舞台上には巨大な仏壇が設置され、そのなかで物語が繰り広げられた。いずれの趣向も演劇史に残るもので、私も以前から話には聞いてはいたが、映像を通してとはいえ実際に目にすると圧巻だった。

舞台から遠くても楽しめる蜷川作品
先ごろ刊行された蜷川幸雄『身体的物語論』(徳間書店)所収の蜷川の「ラスト・インタビュー」でも、冒頭、この2015年の『NINAGAWAマクベス』のことが話題にのぼった。このとき、聞き手の木俣冬が《コクーンの2階の一番後ろのほうから観ても、蜷川さんの作品は楽しめます。(中略)舞台の隅々までいろいろ工夫があるので》と感想を伝えると、蜷川は次のように返している。
《若いころ、走り回っていたのがいいのかな。客席のてっぺんまで走って、全体を見ていたからね、下から上まで。体力あったから。安い席で観ている人でも楽しく見られるようにしたいなっていう気持ちはあったんだよね》
このインタビューの前年、蜷川は体調を悪くして入院し、移動にも車椅子を使うようになっていた。そのため、若いころのように自由に動き回ることはできなくなったものの、それでも長年の経験から、客席のてっぺんから舞台がどう見えるかということはわかると語った。
ラスト・インタビューは、『NINAGAWAマクベス』の公演が終わったあと、『ヴェローナの二紳士』の稽古中に行なわれた。蜷川はこのあと『元禄港歌―千年の恋の森―』を演出し、さらに翌春には自伝的戯曲『蜷の綿』の上演が予定されていたが、残念ながらその準備の途中、2016年5月に80歳で亡くなっている。
『身体的物語論』は、蜷川が生前、2012年に創刊された雑誌「マグナカルタ」で「日本人の身体」というタイトルで連載していた談話(本書「CHAPTER 1」に収録)を中心にまとめられたものだ。書籍化にあたっては、前出のラスト・インタビューと2010年のインタビューをあわせて収録するとともに、本書を企画・構成した木俣が資料的な意味合いで「最後の少年 ~蜷川幸雄が描いた7人の次世代~」という文章を寄せている。
「大きな物語」の必要性を訴え続ける
本書では、岡田利規や藤田貴大などといった若い世代による演劇のほか、ミュージカル『テニスの王子様』やAKB48、美術家の村上隆や会田誠、映画監督の園子温や三池崇史、自ら舞台化を手がけたカズオ・イシグロや村上春樹の小説についてなど、同時代のさまざまな文化が話題にのぼる。蜷川の関心の広さ、歳をとってもなお衰えない好奇心に驚かされる。
若い世代による新しい動きに対し、蜷川は頭ごなしに否定したりはしない。かといって、何でもかんでも肯定して、ものわかりのいい態度を示すわけでもない。そういったものが出てくる背景などをきちんと理解したうえで、疑問に思うことは率直に指摘した。
蜷川がとくに懸念していたのは、「小さな物語」に人々が安住してしまうことだった。演劇の世界でも2000年代以降、隣接するごく小さな枠のコミュニケーションを描く物語が一世を風靡したが、これに対し彼は一貫して「大きな物語」の必要性を訴え続けた。
《神や歴史、民族や伝統などを包括した大きな物語の終焉が語られて久しいですが、本当に大きな物語はなくなったのかといえばそんなことは決してない。むしろ今、現実では大きな物語が次々生まれ続けている。
そんな時代だからこそ、演劇も文学もむしろ《大きな物語を作ることによって、ようやく人間の想像力と現実が拮抗できるようになるのではないか》と蜷川は主張したのだ。
声の小さい俳優が豹変した瞬間
本書の「CAPTER 1」では、もとの連載のタイトルに掲げられたとおり、日本人の身体について、蜷川が演出家として約半世紀にわたり俳優を見てきた経験から語られている。それによれば、《現代の若者たち――主に三〇歳以下の人たちの姿形や皮膚感はみんな似ていますね。一様にヒョロッとやせていて、重心が高く、肌質がツルツルしていて表情が単調。それから声が小さい》という。
かつて蜷川と一緒に舞台をつくってきたのは、それぞれ強烈な個性を持ち、デコボコ、ザラザラとした皮膚感覚で、他人と触れ合うと摩擦を起こしそうな俳優ばかりだった。それとくらべると、ツルツルして、いかにも敵をつくらなさそうな身体を持ったいまどきの若い俳優は物足りないものがあったろう。しかし一方で蜷川は、そのなかから、他人とぶつかったり葛藤しながら自分を変えていく者が現れることを期待していた。「さいたまネクスト・シアター」の内田健司(けんし)はそんな若者の一人だった。
さいたまネクスト・シアターは2008年、蜷川が芸術監督を務めていた彩の国さいたま芸術劇場で、若手俳優の育成を目的に結成された劇団だ。内田健司はその2期生として加入したものの、当初は俳優として強烈なものもなく、目立った役にもつかなかったという。それが2013年に上演した『ヴォルフガング・ボルヒェルトの作品からの九章―詩・評論・小説・戯曲より―』で、最初は小さな役だった内田を、蜷川がちょっと衣装を脱がして演じさせてみたところ、がぜんよくなった。《内田の、やせこけてガリガリの裸が、世間から疎外されている若者にぴったりに思えた》というのだ。
内田は普段はしゃべらず、いっさい大きな声を出さないので、蜷川からはしょっちゅう注意されていたという。しかし、その彼が『カリギュラ』では豹変する。
《カミュの言語を与えると、途端に……なんというのか、自分のなかのものが台詞に乗って、吐露されていく。彼には、しゃべる言葉がなかっただけなんですね。自分の内面に適応する、ひっかかる言葉がなかった。つまり、戯曲を差し出す、ぼくらの問題だった。それが、今回、よくわかりました》
蜷川は本書のべつのところで《人間は、主役やテーマを背負う役をやると必ず成長するし、周囲の評価も変わってくる》と語っているが、内田はまさにこのケースにあたる。
内田はその後、2015年に彩の国さいたま芸術劇場で上演されたシェークスピア作・藤原竜也主演の『ハムレット』で、ハムレットの死後、次世代を担う王子として登場するフォーティンブラスを演じている。蜷川は内田のフォーティンブラスについて、当時の新聞連載で「世界中に例のない新しいものができた」と自負してみせた。
演劇は生ものだからいい
蜷川が演劇に興味を持ったのは、高校時代に観たある舞台で、突如として俳優が「戦争は嫌です」と叫びながら客席を走る姿に衝撃を受けたのがきっかけだという。演劇では、俳優がいきなり客席を走り回るだけで生々しいものが生まれる。
《下世話な言葉や、匂い立つような表現が飛び交う、生ものとしての演劇に対して、ネットメディアに慣れ過ぎている人は免疫がないから、ウェーッと気持ち悪くなるかもしれない。でも、ぼくは断固、観客をウェーッと言わせたい。現実では紛争でだって殺人でだって、血がドクドクドクと流れている。それを隠ぺいするな。現実を直視しろ。演劇とはそれを突きつけるメディアなんです》
あらゆる文化にアンテナを伸ばしながらも、蜷川幸雄の本領はやはり生身の人間でしか表現できない演劇にあった。ラストメッセージともいうべき『身体的物語論』に収められた数々の言葉から、あらためてそう思い至った。
(近藤正高)