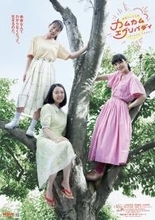前週に広島、長崎の原爆記の日、数日後に終戦記念日があるということで、特に戦争のことを意識させられる12日に放送された第5話。キーワードは「普通」だった。

水原哲の異常な食卓
昭和19年12月、すず(松本穂香)の幼馴染、水原哲(村上虹郎)が突然北條家にやってきた。重巡洋艦・青葉に水兵として乗り組んでいたが、米軍の攻撃を受けて損傷し、呉の軍港に帰投していた。入湯上陸で上陸した哲は、自分の実家ではなく、すずの嫁ぎ先にやってきたのだ。
これは当時としても普通の行動ではない(むしろ当時のほうが今より拒否感が強かっただろう)。哲が持参した米や缶詰を見て、サン(伊藤蘭)や径子(尾野真千子)がなんとなく宿泊を許してしまう描写があるが、むしろ家長である円太郎(田口トモロヲ)が不在だったからという理由のほうが大きいと思う。円太郎が哲を追い返すことができたかどうかはわからないが……。
周作(松坂桃李)が帰宅して食卓を囲んでいるときも、「すず」と呼び捨てにして「相変わらずぼーっとしとるのぉ」をディスりまくり、何か粗相があれば「連れ帰ったりますわい」と豪快に笑う。夫である周作が心穏やかであるはずがない。何か言い返そうとするが、その前にすずがお盆で哲の脳天を一撃!
それにしても、周作たちが水兵たちに因縁をつけられたとき、割って入って頭を下げることができるような哲が、なぜこのようなことを言ったのだろうか? 食卓をよく見ると、哲の前にある茶碗のごはんがまったく減っていなかった。食事も喉を通らないほど異常な心境だったのだろう。哲はすずから反撃されてやりとりが一通り終わってから、ようやく最初のひとくちを食べていた。
「この世界で、普通で、まともでおってくれ」
周作は哲に「あんたをここに泊めるわけにはいかん」と告げ、哲を納屋に送り出す。そしてすずにあんかを持っていくよう促す。戸惑いながら母屋を出ていくすずの前で、鍵をかけてしまう周作。すずがわずかに一歩、戸のほうに踏み出すのは動揺している証拠だ。周作は戸の前で思いつめた表情を見せる。それを見た径子は一言「あんたも複雑じゃね」。
周作は妻のすずが哲と一晩をともにすることを認めたことになる。死地に赴く哲に、最後に思いを遂げさせようとしたのだろうか? それだけではないだろう。周作はリン(二階堂すず)との関係について、すずに負い目があった。また、すずが不妊だったということも影響しているかもしれない(後のシーンですずが言及する)。径子の「複雑」という言葉がそれらを表している。いずれにしても普通ではない。
哲はすずを抱き寄せて囁く。
「すずは……すずはぬくいのう。やわいのう。甘いのう」
哲のすずへの愛情がじんわりと表現されている。一方、唇が重なる直前、すずは「うちはいつか、こういう日が来るのを待ちよったんかね。そんな気がする」とつぶやく。濃密で甘い。松本穂香と村上虹郎はともに21歳だが、どちらも本当に良い演技。
すずは哲から身を離す。周作への怒りが収まらなかったのだ。哲はすずにこう言う。
「普通じゃのう、すずは。当たり前のことで怒って、当たり前のことで謝りよる。
「……」
「ずーっと、この世界で、普通で、まともでおってくれ。わしが死んでもな」
人々を異常な状況に追いやる戦争という時代
原作には、哲がすずに自分の置かれている環境が「普通ではない」ことを語るシーンがある。家が貧しいので海軍に志願した兄の「当たり前の理想」。兄が死んだので代わりに海軍志願兵になった自分の「当たり前のユメ」。命を懸けて戦うという軍人の「当たり前のつとめ」。時代の流れにしたがって、「当たり前」だと思ってやってきたのに、哲を待っていたのは異常な状況だった。
「ほいでも、ヘマでもないのに叩かれたり 手柄もないのにヘイコラされたりは 人間じゃのうてワラやカミサマの当たり前じゃないかのう わしはどこで人間の当たり前から外されたんじゃろう それとも周りが外れとんのか ずっと考えよった」
戦時下というのは異常な状況だ。一部の人間が絶大な権力を持ち、軍人は崇められるが軍隊の中では理不尽な行為が横行してあっけなく命を散らし、庶民は一方的に蹂躙されて犠牲になる。哲はその異常な状況の最前線にいた。わけもわからず殴られながら艦隊勤務を続け、目の前で多くの仲間が戦死する。
「わしが死んでも、一緒くたに英霊にして拝まんでくれ。笑うてわしを拝まんでくれ。それができんようなら、忘れてくれ。な」
「英霊」が祀られている靖国神社への参拝が話題になる終戦記念日の近くに、このセリフをぶつけてきた製作者の心意気を感じる。「英霊」なんてものは一部の人間が都合よくつくり出した概念にすぎない。「英霊」というガワを剥げば、一人ひとりに生活があり、思いがあり、好きな人がいる。そういう人たちが戦争に巻き込まれて死んでいく。好きな人と一緒になりたい、一緒に過ごしたいという気持ちは踏みにじられる。
哲が風呂に入っているとき、すずがいつも歌っていた「山の向こうへ」を歌う。
「ともに生きる人に 何処にゆけば会える 上る坂をはねのけて 下る坂を笑う あの空の向こう どこか二人の家がある」
死地に赴く哲の心情を思いながら読むと胸が詰まる。
23年ぶりとは思えない仙道敦子
すずの兄・要一(大内田悠平)が戦死した。悲嘆に暮れる浦野家の人々。要一の遺影を見て、祖母のイト(宮本信子)は無力感を漂わせて言う。
「悔しいねぇ。……って、言うちゃあいけんのか」
国のために人が死ぬ。国のために自分の気持ちは押し殺さなけばいけない。異常な時代ということだ。
遺族は骨箱の中を見ることも許されていなかった。しかし、母のキセノは「うちは開けて見たよ」と言い放つ。
空襲警報が鳴り、慌てた十郎(ドロンズ石本)は骨箱を落としてしまう。要一の骨箱には骨ではなく、石ころしか入っていなかった。戦争は一つの命が石ころに置き換えられる。それを暴くのが空襲警報というのが皮肉だ。
「あの要一が簡単に死ぬるわけなかろ!」と言い、それまで気を張っていたキセノが声を号泣する。仙道敦子は23年ぶりの女優復帰とは到底思えない。
それでも悲しいだけでなく、すずと周作の夫婦ゲンカでくすっとさせたり、北條家で全員が風邪で寝込むというコントのようなやりとりでホッとさせるところが良い。遊女役の唐田えりかも好演していた。現代編の意義はまだよくわからない。
本日放送の第6話では、ついに呉に空襲が始まる。北條家の人々もバラバラに……。今夜は10時からの放送なので注意。
(大山くまお)
「この世界の片隅に」
(TBS系列)
原作:こうの史代(双葉社刊)
脚本:岡田惠和
演出:土井裕泰、吉田健
音楽:久石譲
プロデューサー:佐野亜裕美
製作著作:TBS