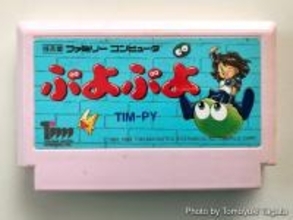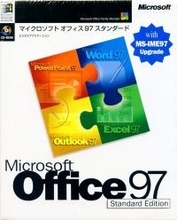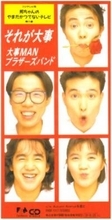1枚20円という絶妙な価格設定は子どもですら安いと思っていたのだから、親にとっても1枚買い与えておけば買い物中は黙らせておくことのできる都合の良いアイテムだったに違いない「カードダス」を覚えているだろうか。
バンダイから登場したカードダスは、主に駄菓子屋やスーパーの入り口付近に設置されていた、10円玉を2枚投入してハンドルを回すとカリカリと音を立てながら1枚のカードが排出されるカードの自動販売機だ。
SDガンダム、聖闘士星矢といった80年代後半から90年代前半に人気を集めたタイトルのカードダスが流行したが、中でも当時の少年を特に夢中にしたのは、ほかでもないドラゴンボールカードダスだった。ちなみに筆者の実家には600枚を超えるであろうドラゴンボールカードダスがいまだに眠っている。
バトルよりキラカード集めに夢中!
ドラゴンボールカードダスは、カードに設定されたポイントにより勝敗を決するカードバトルが楽しめる仕様となっており、数多く集めることでより楽しめるものだった。しかし、当時小学低学年だった筆者は“友達とカードでバトルができる”ということはなんとなく理解していたものの、インターネットもない時代にそのルールやバトルシステムについての詳細を調べる術がほとんどなかった(調べようともしなかった)こともあり、カードバトルの全貌を知ったのは恥ずかしながらごく最近の話だ。
筆者の場合はカードバトルを楽しむというより、単純に好きなものをコレクションするのが楽しかったからこそドラゴンボールカードダスに小遣いをつぎ込んでいた。そして、特に心惹かれたのには理由があった。それがキラカードの存在だ。キラカードとはその名の通り光り輝くカードのことで、ノーマルカードを引いたときとは違い、出現したときのテンションの上がりっぷりといったらなかった。「小学生当時の土曜日が“半ドン”だったのが第2土曜日が休みになった」くらいの喜び具合だと言えばおわかりいただけるだろうか。
当然、キラカードはレアだ。キラカードをより多く所有している者こそが、仲間内の小さな小さなヒエラルキーの頂点に立つことができた。カードダスは登場当初、カードダス20という20円で1枚のタイプのみだったが、いつしかカードダス100という100円で5枚が出てくるタイプも登場したが、友達とともにカードダスを購入する日々、とある法則を発見した。
「キラカードは300円ごとに1枚出現する」。
20円タイプにしろ100円タイプにしろ、必ず300円に1枚、キラカードが出てきたのだ。友達たちはもちろんこのことを知らない。200円をつぎ込んでやめる者もいる。一方自分は次がキラカード出現のタイミングだということがわかる。この法則を発見してからの筆者は飛ぶ鳥を落とす勢いでヒエラルキーのトップに登りつめた。金ならぬキラカードでものを言わす社会の厳しさを、ドラゴンボールカードダスで学んだのだった。
どんどん進化するキラカードの種類
一口にキラカードといっても、その種類はシリーズを重ねるごとに様々なタイプが登場した。一見ノーマルカードに見えて、実は剥がすとキラカードが出現する隠れキラ、表面だけでなく裏面にもキラキラ輝く両面(ダブル)キラ、2枚を並べることで1つの画になるキラカードなど、どのキラカードも子どもたちにとってまさに宝とも言えるものばかりだった。
すでに持っているキラカードを引き当ててしまった場合は、その場にいる友だちと即時交換交渉会が開催された。かぶってしまったカードがただのキラか、剥がしキラか、両面キラかによって交換に要するカード枚数が違うなど、子どもながらにその価値、レア具合でシビアな交渉が行われていた。
筆者は週刊少年ジャンプでドラゴンボールが連載終了となったと同時に自然とドラゴンボールカードダスの収集からも卒業してしまった。そういうタイミングだったのか、カードダスも設置台数が日を追うごとに減少していった。
しかし、2000年代になって再び状況は変化した。カードを使ってバトルするデジタルカードバトルゲームとして、カードダスは華麗に復活したのだ。今なお人気コンテンツのひとつとして子どもたちが夢中になっている様子を見ると、なんだかとても微笑ましい気持ちになる。
(空閑叉京/HEW)