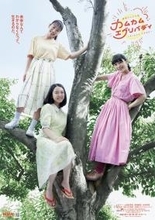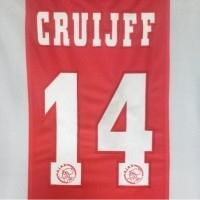かつて「神童」と呼ばれながら、フランクスを動かせなくなった少年ヒロは、2本の角が生えた謎の少女ゼロツーと出会い、二人でゼロツーのフランクス「ストレリチア」に乗ることになる。そして、叫竜との戦いを続けながら、仲間とともに、隠されてきた世界や人類の真実を知っていく。
『THE IDOLM@STER』(監督、キャラクターデザインほか)などで知られる錦織敦史監督を筆頭に、アニメ界を代表するクリエイターが多数集結。2018年1月から全24話が放送されたオリジナルロボットアニメ『ダーリン・イン・ザ・フランキス』(以下、『ダリフラ』)。

豪華特典が収録&封入されたBlu-ray&DVDシリーズは現在第7巻まで発売中。11月28日には最終第8巻が発売される。
そこでエキレビ!では、テレビアニメの監督2作品目で、初めての完全オリジナル作品の制作に挑んだ錦織敦史監督にインタビュー。企画のスタートから最終回まで、ネタバレも気にせずがっつりと語ってもらった。

監督という立場の大変さを改めて気づかされた日々
──放送終了からしばらく時間が過ぎました。今、振り返ってみて、『ダリフラ』を制作していた日々はどのような時間でしたか?
錦織 今回は自分が声をかけて参加してもらったスタッフも多かったので、そのプレッシャーがすごく大きかったですね。原案としてシリーズ構成と脚本にも関わっていたので、なかなか全体に手が回りきらないというか……。企画を動かし始めてから、オリジナルでSFのロボット物を作るのが物量的にいかに大変か気づいて、これはやばいなと。そういったプレッシャーや物量との戦いがずっと続いたので、結構追い詰められましたね(笑)。
──最初に仰った「プレッシャー」について、もう少し詳しく教えてください。
錦織 僕らくらいのキャリアになると、監督やキャラクターデザインを任せられたりする人がいっぱいいるんです。その人たちにわざわざスタッフとして参加してもらうからには、この作品から、それなりの何かを持って帰ってもらいたいというか。満足感ややりがいというか、他のアニメとはまた違う感情を受け取ってもらいたい、みたいな思いが結構あったんです。
この世界での10人の立場がどう変わっていくのか
──錦織監督がこの企画の当初から描きたいと思っていたものを教えて下さい。
錦織 まず、ロボットアニメをやりたいという気持ちがあったんですよね。
──群像劇よりも先に、ロボット物という構想が先にあったのですね。
錦織 群像劇は、初めて監督をやった『THE IDOLM@STER』(以下、『アイマス』)でも手ごたえを感じていたので。今度は日常ものにおける群像劇ではなく、もっとケレン味のある世界観の中で、若者がもつ生命力を描きたいという気持ちがありました。僕が日々、漠然と思っていることが全体的に入っている作品になったと思います。とはいえ、「これを伝えたい!」みたいにテーマから作っていった作品ではなくて。この世界の中に、それぞれの課題を背負った10人のコドモたちを配置して、キャラクターが動き出した時にはそこを掘り下げていけるような形で作っていきました。そこでは『アイマス』での経験が生きたのではないかと。『アイマス』では自分で物語の構成を組んだ時、意図してなかったところで、キャラクターが自然と動き出して、物語の終盤に導いてくれた経験があって。点と点が結びついて線になっていった。それを発見した時、すごく面白かったし、そんな中にこそ自分がやりたいことが入っていると思えたんですよね。
──『アイマス』の成功体験を生かしたのですね。
錦織 ミツルとココロの話も、父親と母親になるアイデアは最初からあったのですが、あそこまで複雑な話になるとは、最初は思ってなかったんです。でも、市川(蒼)君と早見(沙織)さんとの芝居や、この世界の空気感の中でだんだんとキャラクターが成長していった。『その先』を僕たちも見てみたくなったんだと思います
──最初はパートナーでもなかった2人は惹かれあい、オトナが生殖能力を失った世界で子供を産み、新しい世界のアダムとイブのような存在になりました。
錦織 そういう意味では、自分と一緒に成長していった作品ですね。その他の展開についても、ゼロツーを巡る大まかな全体の構成はもちろん決めていたのですが、あまり話を細かく決め込み過ぎず、作っていきながらスタッフとのディスカッションで生まれたものを、どんどん入れていきました。ただ、そのお話をどうやってロボットに結びつけるかも難しかったところです。どれだけの頻度で戦闘シーンを入れられるのかという制作現場のキャパシティの問題もロボットアニメには付き纏うので。今、メカやアクションを描けるアニメーターは貴重ですからね、アクションを描いても捌ききれるとは限らないんです。

──アイドルアニメで、何話に1回なら激しいライブができるか、といった話と似ていますね。
錦織 まさに、そうですね(笑)。『アイマス』の時も、この回で1曲分のライブをやるためには、こっちの回のライブを少し短めにしたり、あまり動かさずに止めで繋いだりして、とかやっていたので、同じようなことをしているなと思いました。
コドモたちだけでオトナになることはできるのか
──人類と叫竜人(叫竜を作った存在)の戦いに、宇宙からの侵略者VIRMも関わっているという壮大な世界観も魅力ですが、世界観設定も時間のかかったポイントなのでは?
錦織 世界観自体は最初からあまり変わっていないんです。ただ、その世界観をコドモたちやロボットにどう絡めていくかについては四苦八苦しました。第三者があまりいないから、主人公たちの半径5メートルくらい(の出来事)を見せるカメラと、全体を俯瞰した(世界観を見せる)カメラしかなくて。カメラの距離が離れすぎているせいで、その二つの結びつきが見い出せず、設定が単なる設定として流れてしまっていたんです。最初は設定をもっと見せる方が良いのかなとも思っていたのですが、主人公たちに感情移入してもらうことの方が大事だと思ったので、コドモたちにカメラを寄せるようにして、世界観は、あくまでも物語の中の装置として機能させる形に切り替えました。この作品に第三者があまりいないのは、大人のいない世界を描きたかったから。手本になる人がいない世界の中、コドモたちだけでオトナになることはできるのか、という話をやってみたかったんです。
──ゼロツーやヒロたち13部隊の人数を決める際も紆余曲折はあったのでしょうか?
錦織 ロボット(フランクス)が5体か6体かは迷ったのですが、6体で(パイロットが)12人になると多いなと思ったので、5体で10人にしました。それでも常に10人出るのは多いから、ロボットは1度に3体しか出動できないとかの条件を付けようと思ったりもしたんです。でも、これは僕のクセかもしれないのですが、群像劇の場合、キャラクターにヒエラルキーを付けず、できるだけフラットに扱いたくなるんですよね。

──たしかに、10人の中で極端に影が薄くなるキャラクターはいませんでした。
錦織 最初は、話の展開によっては(ヒロとゼロツー以外の)誰かが死ぬこともあるかもしれないなと考えていました。でも、全員をしっかりと描いていったので思い入れも強くなって……。それに、ゼロツーに関するラストの展開は決めていたから、その前に他の誰かを脱落させることが僕にはできなかったんです。周りからは事あるごとに「ゴリ君(錦織監督の愛称)は優しいから」って言われちゃうんですけどね(笑)。ただ、その結果、ゼロツーが地球を守るために命をまっとうする代わりに、他のコドモたちは地球でしっかり生きていくという構図ができました。人間になりたかった女の子に引っ張られる形で、死ぬために生まれてきた人間たちが生きていこうと思うようになるという話のラインが見えてきた時、これさえしっかりと描ければ、他のことは無くても良いくらいだって思えたんですよね。
──10人でいこうと決めた段階で、個々のキャラクターの個性や描かれるドラマもある程度は固まっていたのですか?
錦織 最初からガチガチにキャラクターを固めていたわけではなくて。まずは、いろいろな若者の姿や抱える問題を描きたいと思って、配置していきました。最初はテンプレ気味なキャラ付けとバランスから、少しずつ解像度を上げていって。イチゴみたいに猪突猛進でワーッと行って、ワーッと泣く子だったり。ゴローみたいに、自分を犠牲にしてでも周りのことをを気にしてしまう今の男の子っぽい子も入れてみたり。エッチな子もいれば、太っている子もいるだろうし、同性愛の子もいるかもしれないな、と。
(丸本大輔)
後編に続く
(C)ダーリン・イン・ザ・フランキス製作委員会