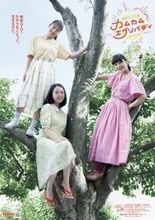出演は『笑点』の司会でおなじみ春風亭昇太師匠と、昇太さんのお弟子さんで『ポンキッキーズ』の司会を務めていた春風亭昇々さん。入場料はなんと無料! 会場には抽選で招待された小学生とその親、合計約100人が詰めかけた。

昨今は空前の落語ブームとも言われるが、小学生が生で落語を聞く機会はなかなかない。そんな中、第一線で活躍する超一流の話芸を至近距離で聞くことができる「こども落語会」はとても貴重な存在だ。筆者の6歳の娘も初めての落語体験をキャッキャと楽しんでいた。
「伝統があるんです! でも、そう見えないでしょ?」
まずは昇太師匠と昇々さんが登場して、初めて見る子どもたちのために「落語とは何か?」を簡単にレクチャー。
「落語は座布団の上で、ひとりでやるお芝居なんです。世界に日本しかないんですよ」という昇太師匠の説明に親からも感心の声が上がる。
「座って喋っているので、立っている人でも寝ている人でも演じることができるんです。落語は正座という日本の生活様式があったから生まれたものだと言われているんですよ」(昇太)
「250年ぐらい前、江戸時代のお寺が発祥と言われているんです。だから紫色の座布団を使うんですよ」(昇々)
「伝統があるんです! (自分たちを指さしながら)でも、あまり伝統があるように見えないでしょ?(笑)」(昇太)
落語は伝統芸だけど庶民のためのものだから、見て、聞いて、笑ってもらうのが一番と語る昇太師匠。この言葉で子どもたちもグッと気分が楽になった様子だった。

オナラネタと「時そば」で子どもたち大爆笑
昇々さんの演目は「転失気(てんしき)」。落語に詳しい方なら、すぐにオッと思うだろうが、これは「オナラ」の噺。
目論見通り(?)オナラのくだりになってからの子どもたちは爆笑の連続。知ったかぶりのくだらなさ、「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」なんて言葉まで知って、子どもたちはちょっと得した気分にもなったんじゃないだろうか。
昇太師匠は昇々さんのネタ選びを「賢いというか小賢しい」と評して(主に親たちを)笑わせつつ、ネタ選びは前もって決めるのではなく当日に決めること、だから後から出る人はベテランで腕のある人じゃないとダメなんだという落語の豆知識を披露。なるほど!
演目はご存知「時そば」。何よりおいしそうかつダイナミックにそばの麺をすする場面に子どもたちの目は釘付け。マイクもないのに、ど迫力で麺をすする音が会場に響きわたり、子どもたちも圧倒されていた模様。同じことを繰り返して数をごまかそうとする男のマヌケさも子どもたちの爆笑を誘っていた。

「時そば」も「転失気」も子どもにわかるようにアレンジしたりせず、演じていたところが印象的だった。「さかずき」「文(お金の単位)」など初めて聞く単語も少なくなかったと思うが、子どもなりに江戸時代の風景に想像をめぐらしながら聞いていたんじゃないだろうか。
「落語を遊びのひとつとして捉えてもらえるからいい」
落語会の後、あらためて昇太師匠にお話をうかがった。まずはネタ選びと演じ方で心がけていることについては、
「お客さんが子どもなので“見て楽しいネタ”を選んでいます。具体的に言うと食べるシーンなどですね。
「子どもたちの顔を見ていると、楽しんでもらっているな、という気がします」と手応えを語る昇太師匠。「子どもはお父さんやお母さんの反応を見ているんですよね。だから、お父さんやお母さんが楽しそうにしているのを見て、一緒になって笑ってくれている子どもが多かったような気がします」。
なるほど、「子どもはわかるかな?」なんて心配せず、大人が率先して楽しめば、子どもも一緒になって楽しむようになるのだろう。最後に「こども落語会」の意義についてもうかがった。
「高校生などに落語を聞いてもらう“学校寄席”という活動は、かなり昔から落語会全体で取り組んでいましたが、ある程度の年齢になってくると落語がお勉強の一環になるんですよね。『こども落語会』の場合は、落語を遊びの中のひとつとして捉えてもらえるので、そこがいいところだと思っています。日本文化に触れるとか、そういう大仰なことを言うのではなく、単純に楽しんでもらえればうれしいですね」
「こども落語会」が開催された神田明神のある神田は、江戸幕府の御典医だった漢方医・浅田宗伯より譲り受けた処方をもとに、堀内伊三郎が「御薬さらし水飴」を1887(明治20)年に発売した浅田飴の創業の地。
元気な子どもの笑い声の応援を目的に「こども落語会」を主催した浅田飴の堀内邦彦社長は「こども落語会」の冒頭の挨拶でこのように語っていた。
「弊社の浅田飴はのどと声の薬ですので、声でつながるイベントを通して、声に関係する伝統や文化を応援するお手伝いをしています。こども落語会では、おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、そしてお子さまと落語を通して盛り上がっていただければ幸いです」
まず大切なのは落語を通して親子で一緒に盛り上がって楽しむこと。
(大山くまお)

協力:さばのゆ(須田泰成)、経堂こども文化食堂