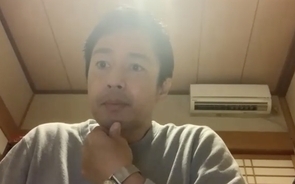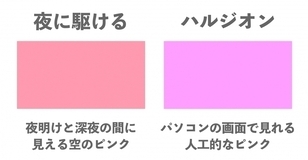――【柳原陽一郎】インタビュー前編より
一人一人がローカル志向でいいんだと思う。なにもグローバルにならなくても。
──それにしても『小唄三昧』は、いろんなスタイルの音楽が入っている作品ですね。
柳原:今回、音楽的にはローカリズムだと思う。昔から、音楽が洗練されて突然売れ線に変わった結果、残念に思うことが多くて。本当に音楽は洗練される前に戻ったほうがいいって思う。特に今回は、今のグローバリズムな世の中を揶揄するような内容の歌が中心になってるから、ロックだなんだっていうより、それ以前の音楽の力をお借りして歌おうかなって思いましたね。
──ローカリズムということだと、小唄もアイリッシュもフォークソングもカントリーも仲よく並ぶ感じになりますね。
柳原:ホントにそう思う。一人一人がローカル志向でいいんだと思う。なにもグローバルにならなくても。どこかから花を持ってくるんじゃなくて、ウチの畑で育った花を自分の力でみなさんにお届けしますっていうことでいいと思う。
──今までの柳原さんの作品も、おおむねそうだったような気がするのですが。
柳原:そうね(笑)。
──今回には借り物感はあるのですか。
柳原:ありますね。今回は全曲、歌詞から書いているんだけど、曲の構造はどこかから借りてきてる感じはするから。変な言い方かもしれないけど、今回は昔からある建物を借りて、その建物に自分の言葉を入れていった感じというか。「21st Century Complex Blues」はプロテストフォーク、「歌手はうたうだけ」はブルーグラス、「やなちゃんのワカンナイ節」は説経節、「洗脳時代」は70年代ロック、みたいに1個1個借りていった感じがする。
──洗練される前の音楽の形をお借りして、自分の畑で育てた花を飾ったみたいな感じですか。
柳原:そうそうそう。
──今作には、これまで聴いて影響を受けた音楽のスタイルが、そうとう素直に入っているとも言えますか。
柳原:そうかもしれない。だから自分のなかで「生きなっせ」は正直言うと、“たま”時代に作った「夜のどん帳」「はこにわ」とあんまり変わらない。「土下座節」は喜納昌吉とチャンプルーズだし。「アラビヤ小唄」は昔の芸者さんが歌うような感じをイメージしたし、「機関車ポンコツ」は久保田麻琴さんみたいな感じを頭に置いてメロディーを書いたブギウギだから。ホントに全部借りてますね。そう思うと『三文オペラ』の逆かな。『三文オペラ』は曲があって僕が歌詞を書いたわけだけど、今回は自分の歌詞があって、それをリスペクトしてる音楽のスタイルに当てはめていった感じ。

──そういうこと、今までにありました?
柳原:ないない。もちろん、この曲はジョン・レノンみたいにしようってイメージすることはありましたよ。でもここまで自覚的にやったことはないかもしれない。だからあたかもその曲を知っているような感覚で書いてました。「アメリカンポーク」なんか、「キンクスならこうやるな」と思って書いてたし。たぶん全曲最初から、曲を作る前に小唄風、キンクス風みたいに“なになに風”っていうのがあったのかもしれない。「エリアマネージャー」だったらサイモンとガーファンクル風とかね。「スカボロフェア」を歌う人が「エリアマネージャー」歌ったら面白いなって。
──仮のアルバムタイトルが『世界のやなちゃん』だったそうですが、そう思うと当たらずとも遠からずですね。
柳原:そうそうそう。そうだね(笑)。
──もしかして今回はコンセプトアルバムだったのでしょうか。
柳原:あぁそうかも! 今までは結果こうなりましたっていうアルバムだったけど、これは初のコンセプトアルバムかもしれない。なんか中期のビートルズっぽいもんね、バラツキ感が。今気づいたけど、グローバリズム反対のコンセプトアルバムだね。でもグローバリズムに背を向けろって言ってるのに、やってることは世界の音楽だという(笑)。よく思うんです、ローカルがローカルとつながればいいのに、なぜそれがAmazonになっちゃうの?って。で、そうなると、そこから外れたものはいつの間にか抹殺されていくわけ。小唄、端唄、地唄、唖蝉坊……ないことになっちゃう、メディアにも登場しなくなるし。それって実は大危機だと思うんだよね。
──そういう想いがあればこその曲という曲も今回は多そうですね。
柳原:ほとんどそう(笑)。だって今までだったら「生きなっせ」とか、正直すぎて歌う気にならなかっただろうし。ローカリズムっていうコンセプトがあったから、ドドンパいいじゃないですか、日本じゃないですかってことになったわけで。
──そうしたことが『三文オペラ』を経て『らぶ あんど へいと』を経て『小唄三昧』に実を結んだわけですね、リスペクトする音楽の形を借りて。
柳原:そうだと思います。そういう意味ではライ・クーダーとかのやり方に近いのかもしれないね。ただね、普通の人はレゲエが好きだったらレゲエのアルバムを作るんだろうし、アイリッシュ音楽が好きならアイリッシュで全部固めていくんだと思う。だけど、すいません、僕はそうはならないんだよね。

──好きなものがありすぎるのではないですか。
柳原:どうしても幕の内弁当を作りたがる人間なのかね。だけど言い訳じゃないけど、この『小唄三昧』は自分のなかではすごく統一感のあるアルバムっていう気がするし、自分に正直だと思う。
──その統一感というのは音楽のスタイルではなく、柳原陽一郎として統一されているということなんでしょうね。
柳原:そうそうそう。すごく私っぽいなって。だからかな、すごく好き、このアルバム。
――【柳原陽一郎】ロバート・B・パーカーの小説が世界に対してどう接していけばいいのかを教えてくれた/マイ旬