昨夜(2月17日)放送の第5回では、「“ノーベル賞会社員”〜科学技術立国の苦闘〜」と題し、2002(平成14)年にノーベル化学賞を受賞した島津製作所のエンジニア田中耕一がとりあげられた。
番組では田中のノーベル賞受賞後の“苦闘”を追うとともに、基礎研究に対する国の運営交付金が年々減少し、民間企業でも研究所があいついで閉鎖されるなど、平成の30年間を通して日本の科学技術研究が厳しい状況に追いこまれていく過程を浮き彫りにした。平成時代に自然科学分野でノーベル賞を受賞した日本出身者は18人を数えるが、受賞対象となった業績の大半は昭和に成されたものであった。田中もまた、昭和の終わり、1985年の発見(論文発表は2年後)に対しノーベル賞が授与されている。
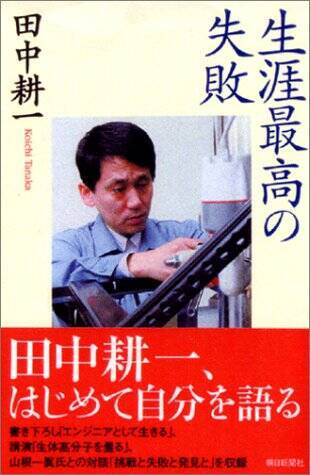
偶然からたどり着いた発見がノーベル賞をもたらす
ノーベル化学賞の受賞対象となった田中の業績は、タンパク質にレーザーを当てて、丸のまま取り出す(イオン化する)技術の開発というものだ。今回の番組ではこの技術がCGを使ってわかりやすく解説されていた。
生命の基本となる物質であるタンパク質は複雑な分子構造から成り、分析のためそのままレーザーを当てると、分子がバラバラになって壊れてしまう。壊さずに取り出すには、レーザーに対し何らかの緩衝剤が必要だ。当時25歳だった田中は、緩衝剤となる物質を見つけるため実験を繰り返す。実験開始から半年後、田中は緩衝剤として試そうとした二つの物質に誤ってグリセリンを混ぜてしまった。彼は以前の実験で、グリセリン単体では効果がないことを確認していた。このときも期待できないと思ったものの、あえて実験してみる。果たして、グリセリンを混ぜた緩衝剤により、初めてタンパク質の分析に成功したのだった。
一つの偶然からたどり着いたこの発見が、17年後、田中にノーベル賞をもたらす。だが、番組中のインタビュー(聞き手はキャスターの国谷裕子)での発言によれば、くだんの発見当時「ノーベル賞に値することをやっていたとは、私自身思っていなかった」という。それだけに受賞が決まったときは戸惑いも大きかった。受賞後、一躍時の人となった彼はマスコミに追われ、すっかり疲弊してしまう。何とかメディアを遠ざけ、新たに掲げた目標は、タンパク質の分析技術を発展させ、「一滴の血液から病気を早期診断する技術」を開発するというものであった。
アルツハイマー病早期発見の糸口をつかむまで
島津製作所は「田中耕一記念質量分析研究所」を新設すると、田中を所長に据え、研究費として毎年1億円の資金を用意した。しかし5年経っても、思うような成果が生まれず、彼はプレッシャーを覚えるようになる。
そのさなか、田中に転機が訪れる。2009年、科学研究への競争的資金の拡充を掲げる国のプロジェクトで、田中の研究が名だたる研究者とともに選ばれたのだ。このプロジェクトでは、研究に対し5年の期限で、1年あたり7億円の資金が投じられ、田中にはさらなる重圧がのしかかることにもなった。彼は会社の外に活路を求め、国内外の研究機関に自ら足を運び、助言を求める。さらに若い研究者の声にも耳を傾けた。こうして新たにつくった人脈から、大学への研究を断念せざるをえなかった20名あまりの若者を雇用し、そこでがんや認知症にかかわりのあるさまざまなタンパク質の分析に挑んでいく。
このとき雇われた若手研究者の一人である金子直樹は、アルツハイマー病に関するアミロイドベータというタンパク質の研究を田中から命じられた。アルツハイマー病は、脳に蓄積されたアミロイドベータが神経細胞を傷つけることで発症するといわれる。金子は与えられた3年の任期中、血液中からアミロイドベータを抽出することに研究者生命をかけた。
とはいえ、血液中に含まれるタンパク質は1万種以上におよび、そのなかにごくわずかしかないアミロイドベータを取り出すのは不可能ともいわれた。金子はそれ可能とするため、50種類ほどの化学物質を幾通りにも組み合わせて特殊な溶液をつくり、アミロイドベータとの相性を試していく。その組み合わせは数万通りにものぼるという。気の遠くなりそうな作業の末、ついにアミロイドベータの抽出に成功する。だが、このとき、アミロイドベータとは別に未知のタンパク質も抽出されていた。
田中はこれについて医療の専門家に調査を求め、分析データを国立長寿医療研究センターに持ち込む。その結果、この未知のタンパク質こそアルツハイマー病の早期発見の鍵を握る物質であることがあきらかになった。
健常者の場合、血液中のアミロイドベータは未知のタンパク質より多く含まれる。これに対し、脳に異変のある人の血液では、アミロイドベータが未知のタンパク質より少なくなっていた。
昨年2月、イギリスの科学雑誌『ネイチャー』でこの研究成果が発表されると大きな反響を呼び、田中は再び世界的に注目される。この成果もまた、ノーベル賞を受賞した業績と同様、偶然の発見がもたらしたものであった。しかし田中は「偶然も強い意志がもたらす必然である」との信念を抱く。
日本人はイノベーションを狭くとらえすぎる?
今回の番組の終わがけ、田中耕一は、イノベーションという言葉が日本では技術革新と訳され、あまりにも狭い意味でしかとらえられていないと指摘した。彼に言わせると、イノベーションとは本来、色々な分野の人が集まって、新しい結合、新しい解釈をすることだという。ゆえに「あるときは失敗と思われることも、別の分野ではすごい発見になるかもしれない。もう少し柔軟に、広く解釈すれば、イノベーションはもっとたやすくできる」と。
研究者としての田中の足跡は、まさに広い意味でのイノベーションの実践そのものであった。彼は以前から、研究者には、自分の専門や所属する団体を越えてつながっていくことが大事だと説いてきた。10年ほど前の雑誌のインタビューでは、こんなふうに語っている。
《日本の研究者は自分の研究を俯瞰して横につなげる、あるいは他分野を理解し、相手に理解してもらうよう対話していく能力が不足している。ただそれは、訓練が足りないだけだと思うんです。(中略)特定の分野を深掘りするだけではどうしても掘り進める断面が狭くなる。関心を広げて横の研究とつなげれば、断面積が広がり、思わぬ新しい視点が獲得できる可能性があります。その異分野融合でも自分の研究を俯瞰することが必要です》(『日経ビジネス』2008年4月7日号)
島津製作所では、横の連携をつくっていくため、各部署が研究内容を披露しあう発表会を年に1回開いているという。会社の外とのつながりでいえば、田中のノーベル賞受賞につながった英語による論文は、このころ質量分析の分野において世界有数の研究拠点であった大阪大学の教授に強く勧められて執筆したものだった。アルツハイマー病に関する画期的な発見も、国立長寿医療研究センターとの連携なしにはありえなかっただろう。
今回の番組では、田中がノーベル賞受賞後、ほとんどマスコミには登場せず、沈黙を保ってきたことが強調されていた。しかし彼は世の中に対し完全に沈黙していたわけではない。自身の研究について一般にも知ってもらうべく、ときにはビジネス誌などの取材にも応じてきた。作家の瀬名秀明との対談では、《受賞をきっかけに、自分のことを説明する立場になりました》と話している(『週刊東洋経済』2004年9月18日号)
同じ対談で田中はこんな話も明かしていた。それはノーベル賞を受賞する年、2002年に出向先のイギリスから帰国したときのこと。
《私は周りの人に褒めてもらって自信を持つことができ、自分にも何かできそうだと思えた。他の人にも持っているポテンシャルに気づいてほしいと考えています。何かきっかけになるものがあるといいのですが》(前掲)
自信のなさは、人々の相互理解の不足もあるはずだ。田中が重視する「他分野を理解し、相手に理解してもらうよう対話していく能力」は、研究者にかぎらず、私たちにも必要なのではないだろうか。
(近藤正高)
※NHKスペシャル「平成史スクープドキュメント 第5回 “ノーベル賞会社員”~科学技術立国の苦闘~」はNHKオンデマンドでも配信予定

























