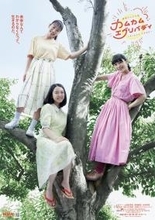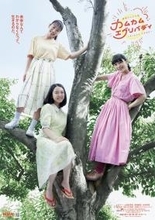55時間におよぶインタビューから書かれた伝記
時は東西冷戦下。アメリカとソ連の両大国は宇宙開発で熾烈な競争を繰り広げていた。
アメリカの宇宙開発を題材とした映画にはすでに、マーキュリー計画の7人の宇宙飛行士を描いた「ライトスタッフ」や、アポロ13号の飛行士らが月に向かう途上で事故に遭いながらも無事に地球に生還するまでを描いた「アポロ13」といった傑作がある。いずれも宇宙飛行士たちがチームワークにより困難に挑む姿が描かれ、高揚感に満ちていた。だが、「ファースト・マン」は、人類史に残る偉業をとりあげながら、その描写は高揚感からはほど遠い。むしろアームストロングという人物の孤独感が先に立ち、悲壮感すら漂う。
映画のなかでライアン・ゴズリングが演じるアームストロングは、国家的使命を帯びるとともに、個人的には娘や親友を亡くすなど、さまざまなものを背負い込む。それでありながら感情を人前で(家族にも)あらわにすることはほとんどなかった。逆にいえば、そういう人だからこそ人類初の月着陸という重大なミッションを成功させることができたのだろう。
さて、この映画には原作がある。歴史学者のジェイムズ・R・ハンセンによる『ファースト・マン 初めて月に降り立った男、ニール・アームストロングの人生』という伝記がそれだ。

アームストロングは月着陸を成功させたあと、1971年にNASAをやめ、大学で航空宇宙工学の教授を務めたほか、実業界でも活動した。しかし、自身の宇宙飛行については沈黙を保ってきた。2000年にハンセンが彼の伝記を書くと決意し、連絡をとってきたときも、いったんは断ったという。しかし、約2年後に伝記執筆の許可を出し、のべ55時間におよぶインタビューに応えた。同書は家族や関係者にも徹底取材したうえで書かれ、2005年にアメリカで出版される。2007年には日本語訳がソフトバンク クリエイティブから出た。
私も、2012年にアームストロングが82歳で亡くなった際、彼について記事を書くにあたり本書をおおいに参照している。それが今回、映画公開に合わせ、河出書房新社から文庫化された。文庫版は、著者のハンセンが、アームストロングが亡くなるまでのエピソードなどを加筆のうえ、全体的に内容を整理して昨年出版した新版を新たに訳したものだ。
最初に月に降りるのは誰か? 順番をめぐって騒動が勃発
上・下巻にわたってアームストロングの誕生から亡くなるまでをくわしくつづった本書には、興味深いエピソードがいくつも出てくる。
アポロ11号の飛行に関しては、それまで多くの謎がつきまとった。たとえば、アームストロングが月面に降り立った瞬間に口にした「これは人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな跳躍だ(That's one small step for man, one giant leap for mankind.)」という有名な言葉について、本来、彼は「“一人の”人間にとっては(for “a” man)」と言うつもりだったのに、なぜ“a”が抜けてしまったのか? あるいは、月面でのアームストロングを撮ったスチール写真はたった5枚、それも体の一部とか後ろ姿とかそういうものばかりで、正面からはっきりと彼をとらえた写真は1枚も撮られていないのはなぜなのか? 本書はそうした謎に、当事者の証言から解答を与えてくれる。
なかでも私が面白く読んだのは、アポロ11号でアームストロングに続いて月面に降り立ったバズ・オルドリンについて、その降りる順番をめぐる“騒動”の顛末だ。
オルドリンはもちろん今回の映画にも登場するが(演じるのはコリー・ストール)、どうも空気を読めないというか、思ったことは口にせずにいられない人物として描かれている。アームストロングの親友だった宇宙飛行士が訓練機の墜落事故で死亡したあと、同僚らと集まった際も、オルドリンは唐突に事故原因について話し始めて顰蹙を買う。
月面に降り立つ順番をめぐるエピソードは映画には出てこないが、この話からはオルドリンの複雑な性格がよく伝わってくる。
アポロ11号の副パイロットに選ばれた当初、オルドリンは自分こそが最初に月面に降り立つ人間だと確信していたという。だが、そのうちに最初に降りるのはアームストロングに決まったとの噂が伝わってきて、オルドリンを戸惑わせる。さらに、NASAは現役の軍人ではなく民間人のアームストロングを先にしたがっていると聞くや、彼は怒りを覚えた。
オルドリンは数日じっくり考えた末、アームストロングに直接掛け合うも、はっきりした答えは返ってこなかったという。仲間の宇宙飛行士たちにも不満を訴えたが、裏工作をしているのかとかえって誤解を招いてしまう。
オルドリンに言わせると、自分が苛立っていたのは、決定が延び延びになり、噂や憶測の的になったり、周囲から「どちらが先になるのか」とたえず問い詰められたりして困っていたかららしい。彼がようやく納得したのは、アポロ計画の飛行乗組員運用責任者のディーク・スレイトン(映画ではカイル・チャンドラーが演じている)から、たぶんアームストロングが先になるだろうと伝えられてからだという。このあと、オルドリンは最後のダメ押しとして、アポロ計画室室長のジョージ・ローのところへ行くと、「どんな決定が下されてようが喜んで従う」と伝えている。
まもなくしてローは記者会見で、アームストロングが最初に月面に降りると明言した。この発表に、オルドリンはすぐに納得したとのちに語っているが、アポロ11号のもう一人の乗組員であるマイク・コリンズ(彼は月着陸船には乗らず、母船で待機した)は、「まもなくしてオルドリンの態度は陰気で内向的な方向に大きく変わった」と証言し、NASAの何人かの高官も、彼はひどくがっかりしたと回想している。
“ファースト・マン”はやはりアームストロング以外に考えられなかった
NASAはなぜ、アームストロングが先に月面に降りると決めたのか? オルドリンの認識によれば、月着陸船のなかではパイロットである彼が右側に座り、アームストロングがハッチの開く左側に座ることになる。月に着陸してから二人が場所を入れ替わるのは現実的ではないとの理由から、最終的に順番が決定されたという。アームストロングもこれについてはオルドリンとほぼ同じ認識を持っていた。
しかし実際には、アームストロングが“ファースト・マン”に選ばれたのは、そんな技術的な理由からではなかったようだ。先述のスレイトン、ローを含む4名の責任者は非公式会合において、最初に月に降り立つのはアームストロング以外にいないと、彼を選んだという。この会合に出席した一人、飛行運用責任者のクリス・クラフトは、《もし[引用者注:アームストロングに]『君は生涯、世界一有名な人物になる』と言ったら、『それなら最初に月に立つ人間にはなりたくない』と答えていただろう。反対にオルドリンは必死で名誉を欲しがり、黙って成り行きに任せることなどなかった。ニールは何も言わなかった。自分からスポットライトに当たりに行くような性分ではなかった。控えめで穏やかな話しぶり、そして勇敢なニール・アームストロングが、私たちにとって唯一の選択肢だった》と話している。
結局、オルドリンは、無事に月面着陸を成し遂げてからも悩み続けたらしい。それでもミッションに彼の感情が悪影響を与えることはなかった。これについて、著者のハンセンは、《アームストロングの冷静な性格がそれを許さなかったからだ。もし(中略)対立も辞さないような人間が船長だったら、オルドリンとの関係はミッションに大きな痛手を与えていたかもしれない》と書く。
当のアームストロングは、誰が先に降りるかは別の人が決めることだと、さほど気にはしていなかった。また、決定にあたって技術的以外の要因がかかわっていたことを知ってからも、最大の決め手となったのは、あくまで着陸船の工学的問題だと信じ続けたという。
この騒動からは、オルドリンとアームストロングの性格の違いが浮き彫りとなった。オルドリンの性格は、読むからに取っつきにくいが、人間的な興味もかき立てられる。もし、彼を主人公に「セカンド・マン」という映画をつくったら、また違ったアポロ11号のドラマが描かれるのではないだろうか。
(近藤正高)