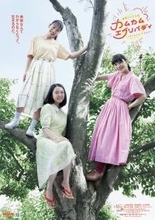男性の#Me Tooもあっていい
「ぼくたちの離婚」(角川新書) は「ぼくたち」とあるように、離婚した男性側の視点のみで書かれた本だ。離婚経験者の言い分を丹念にインタビューしていった著者・稲田豊史も離婚経験者ということで、当事者の当事者のための本である。そこには女性側の言い分はいっさい入ってない。
私は離婚どころか結婚も経験してない女で、この本の当事者とはまるでかけ離れた者ではあるが、それでも大変おもしろく読めた。ああそうか、男性側はこういうふうに感じているのかという参考にもなって。

「ぼくたちの離婚」(角川新書)
他人の不幸は蜜の味。いざ、記事にしてみたら、やっぱり公開しないでほしいと言ってくる人もいるような、ぎりぎりの秘めやかな出来事が書かれているだけはあり、客観的に読んでもおもしろいし、当事者として読んでも、「あるある」として共感できるだろう。
家族制度というものにより、我々は「家族」が必須のように刷り込まれている。「家族」に生まれ、成人すると「結婚」して「家族」をつくる。その繰り返し。
掲載されている13のケース(そのうちのひとつは似た境遇のふたりの対談)はすべて男性側に共感し、お気の毒に思えるように書いてある。離婚とはかなり体力気力を使うことと聞く。実際、何人もの知人が一様にそう言っていたことを私も聞くし、なかにはあんなに大変だったから再婚は絶対したくないなんていう話も聞く。離婚に至るまでに疲れ果て、傷ついた彼らの言いたいことを傾聴するカウンセリング的な趣向で取材が行われ文章が綴られ、著者はそれを、取材対象のひとりの発言からとって「供養」と呼ぶ。
●家族を背負えないぼくたち
●妻が浮気に走った理由
●こわれた伴侶
●業と因果と応報と
……の4章からなっていて、1章は、一般的なルールに則って結婚したものの「家族」という概念に興味がなかったため、それを維持できなかったパターン。2章は、文字通り、妻の浮気に悩まされたパターン。
中で私は、浮気妻とメンヘラ妻のエピソードが面白く読めた。やはり「浮気」と「メンヘラ」はテッパンだと実感した。とりわけ面白かったのが、メンヘラ妻に振り回されたふたりの男性の傷をなめあう対談。エピソードとそれに対する実感が生き生きと語られテンポよく読める。
夫と妻、お互いの話をすり合わせ、離婚の原因を論理的に探るという類の本ではないから、キャラクターが明確に印象的に魅力的なエンターテインメント化することで、供養にもなるというものなのだと思う。
メンヘラ妻の言動は理解できない異様なもので、でも理屈で理解してはいけないのだと離婚した男たちは言う。これはもう、この本に登場する男性の証言の数々にも当てはまるであろう。ただただこの人たちの感じたことを受け止めるしかない。これは夫婦に限らず日常の人間関係にも示唆的な話だと感じた。
すっと心に入ってくる理由
さて、この本、とても読みやすいし、どのケースもすっと頭に入ってくる。
ケース1 サブカル好き 中堅広告代理店勤務
ケース2 新聞記者志望から編プロ勤務
ケース3 中堅出版社文芸編集者
ケース4 ウェブメディアディレクター
ケース5 音響会社勤務の音響エンジニア
ケース6 編プロ経営者
ケース7 全国紙の新聞記者
ケース8 ITベンチャー企業 CEO
ケース9 映画配信を営む会社勤務
ケース10 イラストレーター、漫画家
ケース11 ネット界のカリスマ
ケース12 グラフィックデザイナー、アートディレクター
ケース13 IT 会社のソフト開発者
会社員、フリー、経営者とは立場は違うものの、ほぼクリエイティブなお仕事だ。著者と世界の近い人達だ。離婚も結婚もしてない女の私が、この点だけ、当事者たちと近づけた。
あくまでざっくりだが、おそらく、趣味、考え方、生活環境など大まかに似ているように思う。それが「家族」という形に慣れないことや、子供が要らない気持ち、生活費は別々でいいという考え方、メンヘラな女性への興味など、どこか傾向が似てくるように思う。私もその前提が理解できたし、周囲にこういう人いっぱいいるなあと親近感をもって読めた。
年齢層の違いや、違うジャンルのお仕事をしている人たちをここに多彩に盛り込むよりも、読者の層を、同じようなタイプに絞り込み、繰り返し、同じような状況を重ねていくことで、内容の強度を高め、より共感力を強める。企画の巧さを感じる。
WEB サイト・女子SPA!で連載されていた企画だからの人選もあるだろう。それによって、平成を生きたサブカルやカルチャーが好きな文系の三十、四十代の男子の浮遊する家族観、恋愛観、結婚観、さらに女性観というものが浮き彫りにもなってくる。ある種の時代をみごとに切り取ったこの本が成功したら、また違ったグループの「ぼくたちの離婚」を出すことも可能だろう。
(木俣冬)