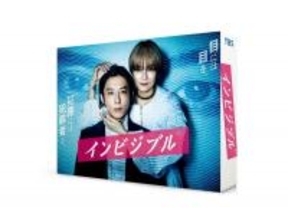「配信中毒」バックナンバーはこちらから
今回紹介するのはネットフリックスにて配信されているドキュメンタリー『チャック・ノリスvs.共産主義』である。なんのこっちゃというタイトルだが、別にチャック・ノリスがド正面から共産主義と戦うわけではない。
独裁政権下のルーマニア、しかし人々は違法ダビングビデオで映画を見る!
1985年、ルーマニアは独裁者ニコラエ・チャウシェスクとその政権による厳しい情報統制の渦中にあった。海外旅行はおろか、海外の映画やテレビ番組も視聴禁止。テレビといえば2年前にようやくカラー放送が始まった国営のルーマニア・テレビのみで、しかもその放送時間は1日に2時間のみ。内容はチャウシェスクを讃える番組とニュースと社会主義映画程度である。80年代のルーマニアには、映像メディアでの娯楽が存在していなかったのだ。
だがしかし、ルーマニアの人々は無理矢理映画を見ていた。違法にダビングされたVHSが、アンダーグラウンドで人づてに流通していたのである。新車が買えるほどの金を払ってテレビとビデオデッキを買った奴が自宅でこっそりと上映会を開き(もちろん金を取る)、ルーマニアの人々はそこでアメリカをはじめとする西側の映画を見ていたのだ。時代は80年代、アメリカではブロックバスター映画をはじめとして娯楽大作が量産されていた。もちろんそれらの映画は当局の摘発対象であり、秘密警察に見つかったらタダではすまない。にも関わらず、ルーマニア人は逮捕の危険を冒しながら外国映画を見ていた。
ではそれらのビデオはどのようにして出回り、どうやって見られていたのか……というのを追った作品が、『チャック・ノリスvs.共産主義』である。
『チャック・ノリスvs.共産主義』では、元々イリーナは国営テレビの映像翻訳者だったことが明かされる。日本で言えばNHKの職員が違法アップロード動画の編集をやっていたようなものである。職場では海外の映画やアニメの内容を、秘密警察向けに翻訳し内容を解説するような仕事をしていたイリーナが、なぜ地下流通の違法VHSの吹き替えに従事するようになったのか、『チャック・ノリスvs.共産主義』では再現ドラマを交えつつ当時の状況を説明する。
もう一人のキーパーソンが、テオドール・ザムフィールという男だ。この男、ルーマニア国内で流通していた違法VHSの総元締めのような人間である。自ら国境を超えて海外映画のビデオを仕入れに行き、毎週新作をヤミ流通に回していたという、違法ビデオのブローカーなのだ。彼がダビングしたビデオをルーマニア国内のバイヤーが買い付けてまたダビング、さらにその下の業者がダビング……という形で流通したため、一般市民が見る頃には画質はヘロヘロで再生も途切れがちという代物になっている。しかしそれでも、ルーマニアの人々は必死になってそれを見た。
大変なのは間違いないけど、ちょっとだけルーマニア人が羨ましい
イリーナとザムフィールの孤軍奮闘と同時に、『チャック・ノリスvs.共産主義』では当時その違法ビデオを見ていた人たちの思い出も語られる。とにかく彼らが口を揃えて言うのは、「映画の本筋も気になったけど、それ以上に背景の店の中や走っている車とかが気になった」という点だ。当時のルーマニアが経済的にも大変厳しく、店にも品物が全然ない状態。それが異常な状況であることを隠すため、チャウシェスクと政府は必死になって海外からの映像を締め出していたのである。
にも関わらず、ルーマニアの人々は違法ビデオによってそれらを見た。そこから「どうもおれたちの生活はおかしいらしい」という認識が広まっていったのである。1989年にはルーマニアでも革命が起こり、チャウシェスクは処刑される。違法ビデオはその原動力、とまで言えるかどうかわからないけれど、発端の一つになったのは確かである。ブローカーと国営テレビの職員が逮捕に怯えながら細々と翻訳・流通させた違法ビデオが、独裁政権を転覆させた(のかもしれない)ということで、『チャック・ノリスvs.共産主義』というタイトルはその現象を言い表している。
しかしそれにしてもルーマニアの人々がちょっとだけ羨ましいのは、そういう状態で見た『ランボー』や『トップガン』や『ナインハーフ』や『ターミネーター』は、めちゃくちゃに面白かっただろうな……という点だ。人づてに誘われる、真夜中の上映会。息をひそめてチャック・ノリスのピンチを見守り、映画を見た翌日には思わずロッキーの真似をしてしまう。
もちろん、自由に海外の映画を見られるのが一番いいに決まっているし、独裁政権なんて真っ平御免である。しかし、「初めて映画を見たのは、友達に誘われて行ったアパートの上映会だったなあ……」と違法ビデオの思い出を語るルーマニアの人たちは、なんだかそんなに悪い思い出を語っているように見えないのだ。つらいことだらけだったチャウシェスク時代だからこそ、映画の面白さが何倍も増幅されたんじゃないか……そんな風に見えるほど、彼らは昔見た映画のことを楽しそうに喋る。
結果的にはその強烈な映画体験や好奇心や異国への憧れが、回り回って一国の政治体制を転覆させたわけで、まったくバカにしたものではない。それだけ娯楽を規制することは難しくしょうもなく、そして娯楽を求める心は強いのである。強烈な映画の力を実感した気分になれるドキュメンタリーだった。
(しげる タイトルデザイン/まつもとりえこ)