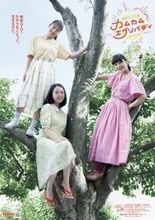たった2人で戦線を突っ切り、友軍を助ける命令書を配達せよ!
タイトルの通り、『1917』は1917年4月6日から7日にかけての1日の間を描いた作品である。舞台は第一次世界大戦真っ只中の西部戦線。
エリンモア将軍から2人に命じられたのは、翌朝に控えている友軍デヴォンジャー連隊の前進を中止する命令書を、伝令として届ける任務だった。敵であるドイツ軍は前線から後退したものの、それが実はイギリス軍を引き寄せるための罠だったことが航空偵察によって判明。しかし電話線は切断されており、攻撃中止を伝達する手段がない。このままではデヴォンジャー連隊の1600名は、周到に準備されたドイツ軍の砲撃と防御陣地に阻まれ全滅してしまう。おまけに、デヴォンジャー連隊にはブレイクの兄ジョセフも所属していた。
攻撃中止の命令書を携えたブレイクとスコフィールドはイギリス軍の最前線に向けて歩き、たった2人で塹壕と塹壕の間の無人地帯へと飛び込む。ドイツ軍は撤退したと聞かされているが、それは前線の塹壕だけの話。命令書を届けるには無人地帯を抜けて塹壕を超え、さらに農地や廃墟を超えた先にある森林地帯を目指さなくてはならない。タイムリミットまでは、すでに1日を切っている。いつどこで敵に遭遇するかわからない道のりを、2人は急ぎ歩き始める。
全編ワンカットでの撮影が話題となり、第92回アカデミー賞でも撮影賞、視覚効果賞、録音賞の3冠を獲得した『1917』。確かにワンカット撮影の効果は高く、第一次大戦の前線を縦断していく2人の兵士の動きをシームレスに体感できる。塹壕から壕内の地下空間、さらに後方の砲兵陣地やその後ろにある広大な農地と、ブレイクとスコフィールドが歩いていくにつれて変わる地形や構造物のグラデーションを、途切れることなく見せてくれるのだ。
没入感が強く、また戦場から後方にかけての状況自体が見せ場となる映画なので、どれだけ実際の第一次世界大戦を再現できたかが鍵となる。『1917』ではそういったディテールに関しても全力を傾けており、イギリス軍の穴を掘っただけの塹壕と、ドイツ軍の土嚢をみっしり積み上げコンクリートで補強した塹壕との対比など、風景や服装のディテールはてんこ盛りである。
特にイギリス兵たちの服装や装備品は見所のひとつ。ウールの制服の上に革製ジャーキン(前閉じで裾が長めの、袖のない胴着)を着たブレイクとスコフィールドは、それぞれP1914とP1908という異なる装備を着用しているし、部隊や兵士によってガスマスクケースを吊り下げる位置が違っているのも面白い(ブレイクとスコフィールドは邪魔になるから背中に回しているが、トラックに乗った別部隊の兵士は規則通りに胸の前にぶら下げてたりする)。
袖章がついた将校用制服と一般兵の制服との違いや、セーターやトレンチコートを着込んだ前線の歩兵たち、おそらく私物であろうニットのタイを締めたカンバーバッチなどなど服装の細部は見どころだらけである。加えて銃の持ち方も昔のライフルの構え方になっていて嬉しい限り。敵の砲弾の炸裂の仕方がショボかったのが残念だったけど、「とにかく頑張って塹壕と歩兵の服装をちゃんとしないとこの映画は死ぬ!」という気合いと危機感は強く感じた。
しかしまあ、どこまでもサム・メンデスというのは意地悪ですね……
前述のように、この映画にはドイツ兵があまり出てこない。第一次世界大戦らしい絵面である「機関銃の弾幕に向かって突撃し、バタバタ倒れる歩兵」とか、「塹壕の上を乗り越える戦車」とか「複葉機による対地攻撃」とかも出てこない。
『1917』の監督であるサム・メンデスは、大変意地の悪い映画監督である。監督デビュー作である『アメリカン・ビューティー』も相当意地悪な映画だったが、湾岸戦争を題材にした戦争映画『ジャーヘッド』も意地悪極まりない作品であった。海兵隊のスナイパーとして厳しい訓練に耐え抜き、ついに迎えた実戦の機会が湾岸戦争。しかしすでに現代の戦争は狙撃兵1人の手に負えるようなものではなくなっており、主人公スウォフォードはとうとう一人も敵を殺さず実戦で一発も撃たないまま帰国するという、戦争映画らしいカタルシスが皆無な一本である。
『ジャーヘッド』と『1917』には、似通った要素が見られる。どちらにも歩兵が2人だけで誰もいない戦場を移動するシーンがあり、そして「攻撃が中止になる映画」である。湾岸戦争と第一次世界大戦という巨大な戦争を題材にしながらも、大軍勢のぶつかり合いを描写することを徹底して避け、ほぼ無人の戦場を歩兵2人がトボトボと歩き、決定的な攻撃は行われない……。どちらも戦争の映画であり、兵士の装備や生活のディテールを執拗に描写しながらも、戦闘を見せて観客を満足させようという意図がどこにもない。
更に言えば、状況が進むに従って伝令たちが戦う相手は「戦争という状況そのもの」になっていく。この映画にはドイツ兵の姿はほとんど登場せず(なんせ映画が始まった時点で大体撤退しちゃってるのだ)、出てきたとしても遠くからとか、ちらっと映ったりくらいである。
しかし2人の前には、ドイツ兵以外にも地形やら疲れやら避けようがないトラブルやらが立ちふさがる。前線を離れるにつれてわかりやすい第一次大戦のディテールは薄くなり、戦争をめぐる状況自体の中をふらふらになって歩くことになる。特定の作戦名や人名ではなく「1917」という年数だけがタイトルになっているのは、「1917年の西部戦線」という状況とそれに立ち向かうことになってしまった人間自体を扱った映画だからなのではないかと思う。
『ジャーヘッド』も、湾岸戦争の映画でありながら湾岸戦争を主題とした映画ではなかった。戦うために猛訓練を強いられ人間としての根本を叩き直されながらも、結局実戦ではろくに活躍の機会を与えられない海兵隊員たちの無意味さと、現代の軍隊のいびつさにフォーカスした作品である。だからこそタイトルは海兵隊員を指すスラングの「ジャーヘッド」だった。
同じように『1917』も、個人の思いを背負いボロボロになっても必死で走り続ける伝令と、その行為の無意味さを描いた作品だ。なんせ第一次対戦が終わるのは1918年の11月であり、一回の攻撃を中止して1600人を助けたところで、その後もずっと戦争が続き兵士たちが大量に死んだことを我々は知っているのである。
というわけで『1917』はまことに意地の悪い、サム・メンデスらしい映画である。それでも必死になって走った伝令がどうなっちゃうのかを最後まで見ると、この意地の悪さがしみじみと染み渡るような感じがある。没入感がミソなので、できるだけ大きい画面と立体的な音響で見るのがオススメ。
【作品データ】
「1917 命をかけた伝令」公式サイト
監督 サム・メンデス
出演 ジョージ・マッケイ ディーン=チャールズ・チャップマン マーク・ストロング コリン・ファース ベネディクト・カンバーバッチ ほか
2月14日よりロードショー
STORY
1917年、第一次大戦下の西部戦線。イギリス兵ブレイクとスコフィールドは、ドイツ軍の罠にはまりかけている友軍を助けるため、攻撃中止の命令書を届ける任務を言い渡される