この予習は必須!【鎌倉殿の13人】北条泰時の生涯と実績をたどる。御成敗式目だけじゃないぞ:前編
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では坂口健太郎さんの好演で人気の高い泰時。昔から栴檀双葉とはよく言ったもので、名宰相はその若き日から片鱗を見せていました。
今回は鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』より、泰時の青年時代を垣間見ていきたいと思います。
■頼家の不興を買った泰時、地元の伊豆北条へ
時は建仁元年(1201年)9月22日、泰時は第2代鎌倉殿・源頼家(演:金子大地)の側近である中野五郎能成(なかの ごろうよしなり)に話しかけました。
蹴鞠に興じる頼家たち(イメージ)
「御所(頼家)の蹴鞠についてですが……確かに蹴鞠は奥深く、ハマってしまうのも解らないではありません。しかし8月の台風で八幡様の神門が倒壊し、民も飢饉に苦しんでいます。そんな中、京都から遊び人を招くというのはいかがなものでしょうか。
一昨日(9月20日)には星が降り注ぐ天変も起きております。まずはこれが凶兆でないか、司天(してん。お抱えの天文学者)に確かめさせてから蹴鞠を始めても遅くはないと思うのです。かつて亡き大殿(頼朝)もご生前、建久ごろに同じような天変が出現した時は謹慎されたと言います。
貴殿は御所とご昵懇ですから、どうかこの辺りをお口添えいただけないでしょうか」
「……」
泰時の言葉を聞いた能成は、無言でうなずくとその場を立ち去りました。
……そんなことがあって、しばらく経った10月2日。泰時の元へ、僧侶の親清法眼(しんしょう ほうげん)が訪ねてきます。
「本日は貴殿にご忠告があって参りました。しばらく地元の伊豆北条でご静養された方がいいのではないでしょうか」
「と、言いますと?」
「実は拙僧、中野殿が御所に貴殿のご進言を耳打ちされていたのを聞きました。どうも話を捻じ曲げて伝えたようで、御所のご不興を買ってしまったのです」
「左様で」
「ですからほとぼりが冷めるまで、しばらく地元へおいでになった方がよいかと思います」
これを聞いて、泰時は答えました。
「それがしはただ愚見を述べただけのこと。ちょうど伊豆北条に急用があるので、明日にも鎌倉を発つつもりでおりました」
泰時は蓑(みの)や笠などの旅支度を取り出して、言葉を続けます。

後難を考慮し、忠告に釘を刺しておく北条泰時(イメージ)。
「勘違いしないでいただきたいのですが、これは決して貴僧の忠告に恐れをなした訳ではありません。本当にお怒りをこうむったのであれば、日本中どこにいようが同じことですから」
「……左様で」
親清法眼が本当に親切で忠告したのか、それとも忠告の体で泰時を鎌倉から遠ざけたかった(陥れたかった)のかはわかりません。
もし忠告を真に受ける形で鎌倉を離れていたら、よからぬ噂を立てられた可能性も考えられますが、泰時は(意識してかせずか)これをきっぱりとかわしたのです。
かくして10月3日の卯刻(午前6:00ごろ)、鎌倉を発った泰時は一路北条の地へ向かったのでした。
■債務者たちが見ている前で……
ちなみに、泰時が「急用」と言っていたのは強がりではなく、本当に大事な用がありました。
「さて、どうしたものか……」
10月5日に伊豆北条へ到着した泰時は、その「急用」を片づけるための段取りを組みます。
実は領民たちへ貸しつけていた種籾(たねもみ)の取り立てを、父・江間小四郎義時(演:小栗旬。北条義時)に命じられていたのです。
昨年は凶作だったため、今年の春に作付(さくつけ。田植え)する稲の種籾を五十石ばかり貸しつけたところ、8月の台風によって今年も不作。
年貢すら満足に納められない状況ですから、とうぜん種籾なんて返せません。返済期限が迫る中、もう首が回らないから夜逃げしようか……そんな領民たちを、何とか思い留まらせねばなりません。
一計を案じた泰時は翌10月6日、本件の債務者数十名をすべて館に招集しました。みんな呼ばれる心当たりがあり過ぎるので戦々恐々、種籾を返せ戻せと責め立てられるのだろうと気が気ではありません。
しかし出てきたのは飯に酒。
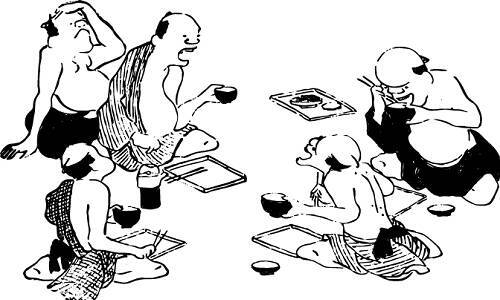
お言葉に甘えて大いに飲み食いする領民たち(イメージ)
「本日はお忙しい中、ようこそお集まり下さいました。お席に用意してある飯や酒は気持ちですので、どうぞお上がり下さい」
そして債務者全員の借用証文を持って来ると、みんなが見ている前でこれを焼き捨てたのです。どうしてでしょうか。
「皆さんが苦しいのは重々承知……そこでただいま証文を焼き捨てたとおり、春に貸しつけた種籾についてはなかったことといたします。もし今年が豊作であったとしても、改めて返せとは申しません」
泰時はさらに一人あたり一斗(約15キロ)の米をお土産に持たせたと言います。負債を帳消しにしたばかりか、生活支援の米まで配るとは……領民たちは感謝感激、神さま仏さま泰時さま……とばかり手を合わせたということです。
「……話は分かった。しかし、なぜそうした?」
10月10日、鎌倉へ戻ってきた泰時は、義時に訊ねられました。我が家だって決して楽ではないのに……恨みがましい義時に、泰時は答えます。
「はい。領民たちに返済能力がない以上、いくら取り立てようが返って来ないからです。
「なるほど。では、一人一斗の米を与えたのは?」

恩を売るなら、気前よく(イメージ)
「もちろん債務の帳消しだけでも十分に太っ腹とは思いますが、さらに生活支援の米を与えることで恩を売り、彼らの逃亡や犯罪を防ぐ効果が期待できます」
「ふむ」
「恩を売られた相手は、こっちが思っているほど恩を覚えていないもの。せっかく恩を売っても、中途半端ではすぐに忘れられて売り損です。そこで此度はこれまでにない恩を大盤振る舞いしたのです。この投資は、きっと何倍にもなって回収できるでしょう」
「言われてみればもっともだ。太郎よ、でかしたぞ」
「ははあ……」
かくして領民は生活を立て直し、泰時は大いに名声を高めることとなったのでした。めでたしめでたし。
■終わりに
建仁元年十月大六日癸未。江馬太郎殿昨日下着豆州北條給。當所。去年依少損亡。以上『吾妻鏡』が伝える泰時の名君エピソードを紹介してきました。去春庶民等粮乏。央失耕作計之間。捧數十人連署状。給出擧米五十石。仍返上期。爲今年秋之處。去月大風之後。國郡大損亡。不堪飢之族已以欲餓死故。負累件米之輩兼怖譴責。挿逐電思之由。令聞及給之間。爲救民愁。所被揚鞭也。今日。召聚彼數十人負人等。於其眼前。被燒弃證文畢。雖屬豊稔。不可有糺返沙汰之由。直被仰含。剩賜飯酒并人別一斗米。各且喜悦。且涕泣退出。皆合手願御子孫繁榮云々。如飯酒事。兼日沙汰人所被用意也。
※『吾妻鏡』建仁元年(1201年)10月6日条
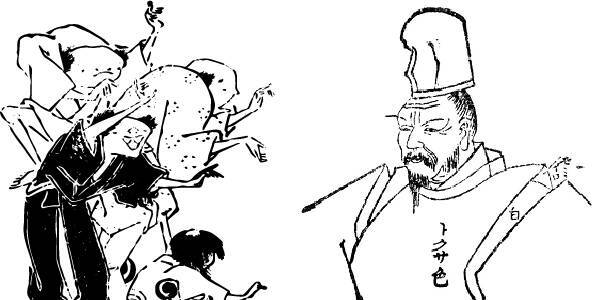
泰時を讃える民衆たち(イメージ)
しかしこれには元ネタがあり、中国大陸の古典『史記』『戦国策』に登場する馮驩(ふう かん。紀元前3世紀ごろ)のエピソードを『吾妻鏡』編者がほぼそのまま流用(パクリ?)した可能性があります。
もちろん泰時がこれらの漢籍に学び、馮驩を意識・実践した可能性もあるため、一概に創作と断定はできません。
これは北条びいきの『吾妻鏡』編者が泰時のすごさをアピールするために創作したのか、あるいは単に当時世の中に広まっていた伝承を収録した可能性も考えられます。
でも、ただ泰時≒北条氏の凄さをアピールしたいのであれば他の執権たちにも色々盛り込めばいいのですし、やはり「泰時ならそのくらいやってくれそう」という伝承の下地となる活躍があったのは確かなようです。
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」はいよいよ本番。父の背中を見て育った北条泰時が、これからも著しい成長を魅せてくれるのを楽しみにしています。
※参考文献:
- 細川重男『頼朝の武士団 鎌倉殿・御家人たちと本拠地「鎌倉」』朝日新書、2021年11月
- 五味文彦ら編『現代語訳 吾妻鏡 7頼家と実朝』吉川弘文館、2009年11月
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan





















![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



