相反する要素を内包したバンド
SOPHIAというバンドをひと口で語るのはなかなか難しい。筆者は2000年前後、取材のために彼らの音源をよく聴いたし、ライヴは何度も観てきた。リアルタイムで熱心に追いかけていたファンに適わないのは当然としても、今でもそれなりに彼らのことはイメージできる。
1995年にメジャーデビューしたばかりの頃は、活きのいいポップバンドという印象であった。当時、彼らを見聴きした人のイメージもそこから大きくかけ離れたものではなかっただろう。いわゆるビジュアル系の枠に入れられることがあったかもしれないが、あまたいたバンドの中でも、とりわけカラフルな印象はあったと思う。メジャーデビュー作である1995年のミニアルバム『BOYS』『GIRLS』から始まり、その翌年1996年のシングル「ヒマワリ」「Early summer rain」からアルバム『Kiss the Future』、さらには1997年の1stフルアルバム『little circus』、シングル「街」、そして「君と揺れていたい」辺りまでは、ポップでカラフルなバンドという初期のイメージは、そう大きく変わらなかったと思う。
問題(?)は、1998年のシングル「ゴキゲン鳥 ~crawler is crazy~」、そしてアルバム『ALIVE』からであろう。それがバンドの本質であったのか、進化であったのかは分からないが、少なくとも音源においてはかなり変化を示した。「ゴキゲン鳥」では歌詞でシニカルな表現も使用。ロックバンドらしいと言えばロックバンドらしいものではあったものの、その反面、それまでのSOPHIAっぽいかと言われると(少なくともその当時は)微妙なものではあっただろう。サウンド面も歌メロはキャッチーでありつつ、サイケデリックなキーボードの音色が耳に残る、ひと口にポップとは言い難いアンサンブルを構築した。
続くアルバム『ALIVE』では、そのタイトルがずばり主張しているように“生きること”に向き合う姿が露呈された。
20年も前のことなのでさすがに細かなところは思い出せないけれど、『ALIVE』以降も彼らのライヴが何か大きく変わった記憶はない。映像演出などは増えていたように思うが、それにしても(例えばシアトリカルなパフォーマンスを見せるというような)抜本的な変化はなかったはずだ。松岡充(Vo)は軽快なトークで観客を楽しませていたし、他のメンバーにしても口を開かないなんてことはなかった。MCでは大いに笑わせ、演奏のダイナミズムで大いに盛り上げた。
唯一変わったのは『ALIVE』リリース後のライヴではアンコールをしなくなったこと。やって当たり前のようにアンコールされたりしたりすることをメンバーが嫌ったからだと聞いたが、真摯に自身のライヴを考え抜いた結果だったのだろう。最初は戸惑いを見せていた観客もアンコールなしには次第に慣れていった。音源での表現は変化したが、ライヴステージにおいては、そのアンコールの排除以外、バンドとしてのスタンスは一切変えなかったことは今もよく覚えている。ちなみに、今回紹介するアルバム『マテリアル』のレコ発ツアーでは全ての都道府県を周りであり、その後、2度、全都道府県ツアーを行なっている。
つまり、SOPHIAは単にポップなバンドだったかと言えば、それは違っていて、アルバムをリリースする毎にメッセージが深化し、それに伴い音楽性も進化してきたバンドだとは言える。しかしながら、ライヴバンドとしてのスタンスはまったくと言っていいほど変わらなかったと思う。ことライヴパフォーマンスで言えば、ポップであり続けたという言い方もできる。例えば、『マテリアル』にも収録されているシングル「黒いブーツ ~oh my friend~」は、歌詞のモチーフからするとセンチメンタルに傾く内容ではあるし、キーボードの音色と旋律がそこに拍車をかけているようなシビアと言えるナンバーではある。しかし、ライヴにおいては会場全体がモンキーダンスで大合唱という光景が見られた。松岡もそれをよしとしていたし、“むしろ「黒いブーツ」だからこそ、みんなで歌ってほしい”という主旨のことを言っていたことを思い出す。
冒頭で“ひと口で語るのはなかなか難しい”と言ったのはその辺もある。ライヴはその場にいる全ての人にとって楽しい空間であることは間違いないけれども、そこで表現されることは必ずしも楽しいことばかりではない。そんな相反する要素を内包したバンド。SOPHIAにはそうした形容ができるのかもしれない。ひと口で語れないがゆえに前段がだいぶ長くなった。以下、本題。
より生々しく、リスナーに迫る
『ALIVE』で“生きること”に向き合ったSOPHIAが、その精神、哲学、音楽性をさらに追及したと言えるアルバムが『マテリアル』である。『ALIVE』もそうであったように、本作にもポップなSOPHIAの要素はほとんどない。いや、『ALIVE』と比べたら『マテリアル』はまったくポップではないと言い切ってもいいかもしれない。本作はミドルテンポのM1「大切なもの」から始まる。イントロは民族音楽風とも言えるパーカッションの響きからリズム隊が入り、そこにエレキギターのキャッチーなリフが奏でられる。そして、歌詞は松岡の独白とも思えるような言葉が並ぶ。
《何を探してんだろ この俺の心とやらは》《何かに憧れて/何かを傷つけて/見つけたもの 何処に置いたっけ》(M1「大切なもの」)。
浮遊感のあるキーボードの音色が、その茫漠として気持ちを代弁するかのように背後で鳴り続ける。ギターがエッジーではあるものの、さすがにアルバムの1曲目としては派手さに欠けるが、だからこそ、余計に彼らの決意を感じるところではある。
それはM2「航海」も同様。アップテンポではあるし、メロディー展開を考えれば、いわゆるビートロックに仕上げても何らおかしくない感じではあるが、あえてそれを拒んでいるかのようなアンサンブルである。細かく刻むハイハットを多用するドラム。ざらついた音を聴かせるアコギ。バンドのポテンシャルがグッと広がったことが伺える楽曲と言える。
《そして僕は壊れかけのこの船で いつかの様に風吹くのを待って/流れ行く暮らしに安らぐ度に 癒える事なき赤く開く傷を/情けなくなる程のつくり笑顔の中に 見えぬ振りして逃げそうになるけど/次の向かい風に迷わず行かなきゃ この風が生まれる何もないあの場所へ…》(M2「航海」)。
歌詞は上記のような内容だが、後半、演奏は突然カットされて、協和しないハーモニカと鍵盤との音でアウトロを迎える。航海の先行きを暗示しているかのような不穏な終わり方。バンドの表現力が豊かになったと言ってもいいだろう。
M3「Place~」はのちにシングルカットされたナンバー。歌メロが壮大な印象のミドルバラードで、歌詞はM2を補填するかのような前向きさを湛えている。演奏は派手さこそないが、いい意味で歌を邪魔していない。
…と、矢継ぎ早に1~3曲目を解説してみたが、アルバム冒頭に、俗に云うJ-ROCK、J-POP的な楽曲は皆無である。M3はシングル曲であるからJ-ROCK、J-POPであると言えばそうなのだが、少なくとも、8ビートで、分かりやすいギターリフがあって、サビはキャッチーで、歌詞はラブソングで…というところがまったくない。『ALIVE』で払拭された(払拭した?)初期のポップなイメージが完全になくなったことを、改めてバンド側が宣言しているかのようだ。
M4「せめて未来だけは…」でようやくアップチューンが登場するが、これとてひと筋縄ではいかない。何と言うか、全体のバランスが妙だ。とにかくギターが奔放に暴れている印象が強く、ヴォーカルもところどころエフェクトがかかっている。冒頭こそ一発録りを思わせる勢いが感じられるものの、間奏では寸劇風の女性のモノローグが聴こえてきて、不思議な世界観を演出している。思考が取り留めもなく巡っているような歌詞は面白いというよりも、やはり不穏だ。
そんな、来るべき未来を皮肉交じりに描いたと思しきM4に続くのが、M5「黒いブーツ ~oh my friend~」というのも興味深い。ファンならばご存知だとは思うが、「黒いブーツ」は事故死した松岡の友人をモチーフとした内容である。M4、M5と続くことで、より生々しく、リスナーに“人生”を問うているようにも感じられる。
《いつかお前が言ってた人生に/もしも勝者と敗者がいるのなら/お前は俺に何て言うのかな 聞こえない》《oh my friend 聴かせておくれよ/俺よりぶっとんだ お前の詩を/oh my friend 守っておくれよ/嘘つきなお前の 涙の約束》(M5「黒いブーツ ~oh my friend~」)。
M4であれだけ暴れていたギターが、M5では文字通り鳴りを潜めているところも興味深いし、その分、頭打ちのリズムと共に楽曲の中核をベースの旋律も聴きどころと言える。中世宗教音楽のハープシコード風とも、The Doors的サイケデリックロック風とも思えるキーボードの音色も楽曲のポイントであり、バンドサウンドの成熟さを見て取れる楽曲ではある。その点でもSOPHIAの代表曲として相応しいナンバーであろう。
カオスと静謐の対比、歌詞の深み
そうかと思えば、M6「take me away」は打ち込みやエフェクトを多用したデジロック。歌詞は英語な上に、サビ以外はエフェクトが強くて、はっきりと聴き取れない箇所もある。インダストリアルミュージックに近いもので、いわゆるポピュラリティーからは大分遠いところに位置していると言ってよかろう。
そのあとが、アコースティックギターの音色がサウンドの中心を彩るミドル~スローのM7「Birds eye view」と、アコギのみのM8「言葉」というのは随分と極端な並び方ではあるけれど、M7、M8の静謐さといったようなものを際立たせることに寄与しているとは思う。それは、その後のM9「センチメンタリアン・ラプソディ」も同様である。M9は楽曲そのものはポップなロックンロール。軽快なニューオーリンズビートも配されて、普通に演奏したものをそのまま収録しても何ら問題ないと思われるが、ここではラジオエフェクトを強めにかけて、(あえて語弊のある言い方をすると)聴き取りづらくしているようだ。イントロ、アウトロ、間奏では電波が混線しているような作りにしている。この辺りのミックスは歌詞にも関係しているのだろう。
《街角に流れる 誰かのMessage/馬鹿げてると いつから響かない?》《センチメンタルはクセ者さ 一人芝居ならまだましだけど/そうは問屋がおろさないって どうすりゃいいか 分かんないよ もう》(M9「センチメンタリアン・ラプソディ」)。
いずれにしても、M9も言わばカオスなサウンドメイクをすることで、翻ってM7、M8との対比が印象に残るところではある。
そして、その混沌さから続くのがM10「beautiful」である。キャッチーなサビメロのブギー。シンセもピコピコと背後で鳴っている。ここまでの楽曲に比べれば十分にポップである。だが、歌詞は完全に晴れやかかと言われると、どうもそうとは言い切れないようにも見て取れる。
《危ない薬もケンカもしたことないよ Yeah Yeah/“Rockは詳しいぜ"》《過ぎた事ばかりがなぜ眩しく見えるのかな/あの頃よりも少しは大人だろう? Baby/死にたくなる程嫌な事なんて1つもないぜ/だから今日も空っぽで陽が暮れるOh》《永久未来 続くものなどあるはずはないから/これで行くさ僕は僕を壊してく》(M10「beautiful」)。
《永久未来 続くものなどあるはずはない》というのは真理に近いものではあろうし、この楽曲のキラーフレーズともなっているので、それを文字通りの“beautiful=美しい”と見る向きもあろう。ただ、《今日も空っぽ》《僕を壊してく》など、決してポジティブとは言い難い言葉が続くところには、解釈の余地がかなりあるようにも思う。作詞者本人に確かめたわけじゃないので歌詞の意図したところなどは軽々には語れないけれど、単純に答えが示されたものではないことは確か。M4、M5と連動していると思しき部分もあって、映画や演劇で言うところの伏線回収ではないが、アルバム作品としての一貫性を感じさせる。まさにひと口では言い表せない、深みのある歌詞であるとは言える。
個人的にはM9でアルバムを締め括っても良かったような気はするが、それでは投げっ放しになり過ぎると感じたのかどうか知らないけれど、スローなM11「贈り物」を経て、密集感の強いバンドサウンドのM12「material of flower」で、『マテリアル』はフィナーレを迎える。だが、M11では背後でシンセが終始、不穏に鳴っているし、M12はやはり歌詞が開放的ではなく、決して大団円とは言い難い作りではある。とりわけM12は楽曲がカットアウトされる。アウトロがあってカット…ではなく、歌の最後と同時に突然、終わるのである。何かを暗示しているような、独特の余韻を残す終わり方だ。
頭から最後まで、まさに徹頭徹尾、その辺のポップバンドと一線を画す…いや、そればかりではなく、ロックバンドとして独自の哲学を抱いていることを堂々と天下に知らしめているアルバムだと言っていい。もっと言えば、『マテリアル』はジャケ写もなかなか象徴的で、これもまた彼らの哲学を反映しているように思う。一度丸められてしわくちゃになった“マテリアル SOPHIA”と書かれた紙を開いたような画。必要がないと捨ててしまったものを再び取り出した──そんなふうに感じられるアートワークで、もしかすると、それはアルバム全体に流れるテーマにも通底しているのかもしれない。
2013年からの活動休止も永久に続くと考えられる向きもあったSOPHIA。今回、久々に『マテリアル』を聴いて、こういうアルバムを作ったバンドはその活動を葬り去ることができないことを何となく理解した。思考、思想に終わりはなく、その表現に限りはない。それを幸せなことと言うべきか、因果なものと言うべきか分からないけれど(おそらく両方あるだろうが)、簡単にピリオドは打てないのである。聞けば、10月11日の『SOPHIA LIVE 2022 “SOPHIA”』の1曲目は、『マテリアル』の1曲目でもある「大切なもの」であったという。それが彼らの“航海”の再開を告げる楽曲としてベストな選曲であったことは、『マテリアル』を聴けばよく分かると思う。
TEXT:帆苅智之
アルバム『マテリアル』
1999年発表作品
<収録曲>
1.大切なもの
2.航海
3.Place~
4.せめて未来だけは…
5.黒いブーツ ~oh my friend~
6.take me away
7.Birds eye view
8.言葉
9.センチメンタリアン・ラプソディ
10.beautiful
11.贈り物
12.material of flower

















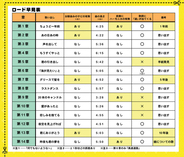



![SCIENCE FICTION (生産限定盤)(3枚組)[Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/31rt4g7gE9L._SL500_.jpg)








