※年齢は2021年当時のものです。
■事故の翌日、父は別人になってしまった
2021年12月8日、93歳の父が車庫入れに失敗する自損事故を起こした。車庫が壊れて使用できなくなり、リアガラスは粉々に飛び散った。車は全損で廃車になることが決まり、父の愛車はもう家にない。
人身事故でなかったことに、家族みんなが安堵した。元々丈夫なおかげで、打撲により胸全体が痛む以外、父にケガはないようだ。
しかし、翌日、父はすっかり別人になってしまっていた。朝は起きられないし、着替えもしない。一日中パジャマで過ごしている。
「車がないからどこにも行けない」
二言目には、しょげた様子でそうつぶやく。もしかしたら、事故を起こしたことを忘れたのではないか。恐る恐る私は聞いた。
「パパ、どうして車がなくなったか覚えている?」
「いや、覚えていない……どこかぶつけたんだったかな」
「そうだよ。車庫入れに失敗して、廃車になるほどひどく壊れたんだよ」
■昨日のことを忘れても「真珠湾」は覚えている
すると父はまた同じことを繰り返した。
「覚えていないな。いつのことだ?」
「もう忘れたの!」と怒鳴りたい気持ちを押さえ、私はやさしい口調で教えた。
「パパ、昨日のことだよ。12月8日」
「あぁ、そうだったな。
出た、出た。これが「取り繕い反応」というやつだ。わかっているように装うこの反応は、認知症の兆候のひとつだという。私がどう返答しようか迷っているのを見て、父の頭に急にスイッチが入った。
「お前は知らないかもしれないが、昭和16年(1941年)の12月8日、ハワイの真珠湾で、日本がアメリカに奇襲攻撃を仕掛けたんだ。俺は13歳だった」
昨日の事故のことは忘れているのに、80年前のことは覚えている。
■さもわかったように返事をする「取り繕い反応」
事故の数年前から私は、携帯電話に知らない着信があると、その度に「父が事故を起こしたのでは?」と、胸がざわざわしていた。
母が亡くなってから40年近く、父が1人で暮らしてこられたのは、車で気軽にスーパーに行けて、食料を調達できていたからだ。札幌市内に住んでいるのだが、地下鉄の通っていない地域だし、バスは1時間に1本しかない。車があったから父の生活が成り立っていたのは確かだ。
車が廃車になったなら、新しい車を買えばいいと考えている父。運転することは年齢的に決して許されないと私は諭した。その度に父は、「人を轢いたら大変なことになる」とか、「晩節を汚せない」だとか、さもわかったように返事をする。たぶんそれも一種の取り繕いだと想像できた。
「取り繕い反応」に騙され、親が認知症になったことに気づくのが遅れるケースは、結構多いのではないだろうか。わかっているように装って、父が正論を言っているのを事故の件以外でも何度か見た。
■認知症を「他人事」と思っている父
例えば、友達に電話して、父は共通の知人のことをこう言った。
「かわいそうに、認知症になったらしくて、私が電話しても、誰だかわからないんだ。それなのに、自分のことは全部自分でやっているって言っているのだから、ご家族は大変だろうね」
私は唖然とした。オーマイ・ダッド!
『何言っているの! それって、パパとまったく同じだよ!』
同様に、高齢ドライバーが人身事故を起こしたニュースを見ても、他人事と捉えた発言をする。
「歳取ると、足が悪くなるし、判断力が落ちるから危ないよな」
私はため息が出た。そして気づいた。自身の判断で「運転免許返納をする」人たちは、正常な思考能力を失っていない方々なのだと。自分の能力を自覚し、人に迷惑をかけないうちに運転をやめるのは、人生に対する想像力と、人への思いやりがあるからだ。もはや父にはそれがない。
■倒れて動けなくなり、救急車で病院に行くはめに
事故から数日後の朝、父は寝室で倒れて動けなくなり、救急車で病院に行くはめになった。脳内出血か心臓発作ではないかと心配したが、救急病院の検査結果では、異常がないと言われた。
倒れたのは、血圧が急に上がったのが原因だったらしい。内科に連れて行かなければならないが、認知症の検査も受けさせたい。地域包括支援センターに相談して、内科と神経内科の両方があるクリニックを紹介してもらった。
医師は脳の画像を、父にも私にも見せて、どこが萎縮しているかを丁寧に説明してくれた。
「黒く写っている部分は海馬と側頭葉です」
父はどういうわけか、張り切った口調で先生に言う。
「海馬、わかりますよ。本当にタツノオトシゴみたいな形ですね」
先生は、優しく、父を尊重して対応してくれる。
「よくご存じですね」
にわかに父の表情が明るくなる。知識があると褒められたのがうれしいらしい。先生は、海馬の部分を指差した。
「ここが萎縮していると、今のことをうまく記憶できないんですよ。歳を取ったら、みんなそうなってきますけどね」
■医師から認知症と言われて「ほっとした」
先生の説明の中の、「みんなそうなってきます」という部分だけが、父の印象に残ったのは明らかだった。自分は年相応に忘れっぽくなっただけだと、都合よく解釈したに違いない。
「私も93ですからね、歳には勝てません」
冗談っぽく答えてから、一礼して診察室を出ようとした父を、先生は引き止めた。
「認知症の検査をしますから、こちらに座ってください。娘さんは外でお待ちください」
漏れてくる声に聞き耳を立てた。父は楽しそうに質問に答えている。どうやら検査を受けている感覚がないらしい。
終了後に先生に呼ばれて、「長谷川式認知症スケール」で検査をした結果を聞いた。30点満点のところ、19点だったという。20点以下は、認知症の疑いが高いとされているそうだ。
父が認知症だと専門医に言われて、私はすごく気が楽になった。この数年間、何度となく父と喧嘩した。どんどん自分本位な性格に変化していく父に、私は怒ったり傷ついたりしてきた。できることなら、優しくて、ちょっとモダンで、「パパ」と呼ばれるのが似合う父に戻ってほしかった。
けれどもそれが、認知症という病気のせいだったなら、「変えよう」と思わずに「合った対応をしよう」と考えれば良いのではないだろうか。ある種の希望を持つことができた。
■自分の時間がなくなり、1週間で息が切れてきた
認知症の父をどう支えれば良いのか、私は真剣に考えた。数年前、父の免許返納問題を警察に相談に行ったときに言われたことを思い出した。
どうアプローチしたら父に免許を返納させることができるかと尋ねた私に、担当者は、これまでと同じ生活ができるように、支える覚悟を持つ必要があると言った。
正直なところ、無理だと思ったのを覚えている。でも、父の年齢からすると、自宅で世話をしてあげられる時間はそう長くはないだろう。できるだけのことをやってやりたい。弟はだいぶ前に亡くなっているので、1人で頑張らなければと私は気負っていた。
小説やエッセイの執筆だけでなく、いくつかの公的機関の委員もしているし、大学院にも通っている。父の家と行き来しながら仕事や勉強の時間を作るには、寝る時間を削るしかない。
まず、朝は電話で安否確認をする。
「パパ、おはよう。元気ですか?」
娘の心配をよそに、父は言う。
「あぁ、俺はいつも元気だ。なんで毎日電話をかけてくるんだ?」
「この間、ベッドの横で倒れていたじゃない。パパ、救急車に乗ったことを、忘れたの?」
少し考えているような間があった後、父は言った。
「いや、救急車に乗ったことはないな」
ともあれ、無事を確認できたことに胸を撫でおろし、慌ただしく仕事をこなしてから夕飯を作りに行く。そして夜中に帰宅して、机に向かう。65歳の私には、かなり堪えるスケジュールだ。1週間ほどで息が切れてきた。
■朝を迎えると、なぜか急に涙が込み上げてきた
折しも、札幌は雪がどんどん降る時期だ。事故から10日後、大雪に見舞われた。私の自宅マンションの駐車場周辺の除雪をしなければ、車は動かせない。これがかなり体に堪える。
へとへとになって車に乗ると、今度は大雪による渋滞で、普段は車だと十数分ほどで父の家に着くのに、片道1時間半もかかるようになってしまった。
父は自分のことは自分でできると思っているので、私が無理して行っても感謝している気配はない。ところが、私のほうが父の様子を気にしてしまい、毎日父の家に向かってしまう。
子育てに例えて言うなら、私は父に対して過保護そのものだ。それがわかっているのに、父の世話をするのは私の役目だという、長女特有の「お姉ちゃんなんだから頑張らなければならない」という責任感を捨てることができない。
父のケアが大変だと友達に愚痴ると、異口同音に「1人で頑張らないで、福祉の手を借りなければ」と言う。しかし、そう簡単に福祉の手を借りられるシステムにはなっていない。年末が近づいているため、居住区の要介護認定審査に来てもらうのは、正月明けまで待たなければならなかった。
睡眠時間が3時間ほどしか取れずに朝を迎えると、外は絶え間なく降り続く雪で、一面真っ白だった。なぜか急に、涙が込み上げてきた。このままでは私がダメになる。辛いときは、辛いと言おうと決意し、私は離れて住む長男に電話をかけた。
■「世話が大変なことと、仕事が忙しいことは、別の話だよね?」
私は息子2人が高校生と中学生のときに離婚した。息子たちが思春期のときに心安まる家庭環境を与えてやれなかった申し訳なさを、ずっと心に抱いている。そのため、彼らに弱音を吐いたことはあまりない。しかし、父の世話をする心身の負担と、仕事や大学院の勉強のすべてが肩にのしかかり、気の持ちようがわからなくなっていた。涙ながらに私は、長男に自分の気持ちを話した。
30代半ばの長男は、私が落ち着くのを見計らって言った。
「問題を整理したほうがいいと思うよ。おじいちゃんの世話が大変なことと、仕事が忙しいことは、別の話だよね?」
「……そういえば、そうだね」
クールで、的を射た助言だと思いつつも、私はなんとなくおもしろくない。
「日に日に壊れていく親を見ている辛さは、孫のあなたにはわからないのよ!」
■「ありのままを受け入れよう」とは考えなかった
まるで嵐が通り過ぎるのを待つような間をおいて、長男は答えた。
「わかるよ。俺だって、おじいちゃんが変わってしまうのを見ているのは、正直、辛かった」
長男は父の自損事故の少し前に、1週間ほど休みを取って話し相手をしに遠方から来てくれていた。認知症の兆候があることを目の当たりにしていたからこそ、私を諭すように続ける。
「事故のことを忘れているけど、ほかのことは覚えているでしょ。それを受け止めてあげなきゃ。俺はおじいちゃんが何回同じことを言っても、『そうだね』って聞いてるよ」
脳の機能が今のことを記憶できない状態になっていたとしても、忘れていないこともあるはずだ。それを聞いてあげるべきだと長男は言う。私は目から鱗が落ちた気持ちだ。
そういえば、この数年、私はずっと父の言動の揚げ足を取り、常に否定していた。ありのままを受け入れようとは、考えもしなかったように思う。もしかしたら、その態度が父を頑なにさせていたのだろうか。
■「褒める介護」を実践すると決めた
長男との電話は、父の姿を客観的に見るきっかけになった。こうするべきであるという、上から目線で父にものを言うのをやめることにしよう。「褒めて良いところを伸ばす」育児法が話題になるが、年寄りにも応用できるかもしれない。
翌日の夕方、父の家に着いて呼び鈴を鳴らすと、父が玄関の戸を開けてくれた。「褒める育児」ならぬ、「褒める介護」を実践すると決めたのだから、私は優しく言葉をかけた。
「あら、パパ、洋服を着ているんだ。偉いね」
せっかく私が褒めているのに、父は呆れたように言った。
「何言っているんだ。寒いのに、裸でいる訳ないだろう」
「違う、そういう話ではない」と言い返したいが、「褒める介護」には忍耐が必要だ。
父は昨日まで、車がなくなって出かけられないから、着替える必要はないという理由で、一日中パジャマで過ごしていたことを、もう忘れてしまったのだろう。
■今度は、お世辞ではなく本当に感激した
言葉を飲み込んで台所に向かうと、炊飯器から蒸気が上がっている。今度は、お世辞ではなく本当に感激した。
「パパ、ご飯を炊いてくれたの! すごいね」
「いや、毎日やっていたことだから、すごくはないけど」
父は照れくさそうにニッコリ笑った。自損事故のショックで1週間以上無気力になっていたが、昔の感覚を取り戻しつつあるのかもしれない。父に役割を持ってもらい、認知症の進行を遅らせることができるのではないかと期待を持った。
父が炊いたご飯を一口食べてみると、とてもおいしい。
「ご飯を炊くのが上手だね。これから毎晩炊いてくれると助かるんだけど」
「いいよ。やっておくよ」
お米を2合研いで水を入れた後に、氷を2個入れてからスイッチを入れるとおいしく炊けるのだと、父流のやり方を教えてくれた。
「私も今度やってみるね」
うなずいた父の柔和な顔を見て、「褒める介護」をこれからも忘れないでいようと思った。
----------
森 久美子(もり・くみこ)
作家、拓殖大学北海道短期大学客員教授
1956年北海道札幌市生まれ。北海道大学公共政策大学院修了。1995年、開拓時代の農村を舞台にした小説で朝日新聞北海道主催の「らいらっく文学賞」に入賞。以来、多数の連載を持つほか、「食」と「農業」をテーマにした講演やラジオ番組のパーソナリティーを務める。ホクレン夢大賞・農業応援部門優秀賞、農業農村工学会賞・著作賞受賞。農林水産省・食料・農業・農村政策審議会委員などを歴任。2022年より、拓殖大学北海道短期大学客員教授。『ハッカの薫る丘で』『古民家再生物語』『優しいおうち』(中央公論新社)など著書多数。
----------
(作家、拓殖大学北海道短期大学客員教授 森 久美子)














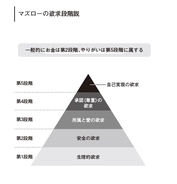

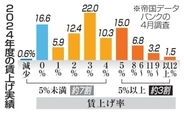








![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








