※本稿は、菅野久美子『母を捨てる』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■孤独死現場で見た「生きづらさ」
私は数年間にわたって孤独死現場を取材し、孤独死の本を立て続けに二冊、出版した。周囲の人たちから「よく、あんな現場に行けますね」と驚かれることも多い。しかし、私が長年にわたって現場に足を運んできたのは、孤独死した人たちに、「生きづらさ」という共通点を見たことが大きい。
その背景には、親によって苦しめられたことが一因でセルフネグレクトに陥り、孤独死した人も大勢いた。
数々の孤独死現場の取材を重ねる中で私が目にしたのは、「毒親の最期」を一手に押しつけられた「子どもたち」の切実すぎる苦しみだ。親が元気なうちはまだいい。しかし、人は残念ながらピンピンコロリで死なない。
毒親に育てられた子どもにとって、成人までの親元にいる期間が苦しみの第一ステージなら、第二ステージは、介護から納骨までのいわば「死までのラストスパート」だ。そしてその時期は、親子がもっとも濃密にかかわらなければならない時期でもある。ここで、二次被害が起きる。
母親と住む場所が違っても、「母」はずっと追いかけてくるのだ。
私はこの頃から、社会にはびこる「毒母問題」と真正面から向き合わなければならないと感じるようになっていった。
絶対に守られるべきは、毒親に苦しんできた子供たちなのではないか、と。親の面倒を見るのが当然とばかりに良識を押しつける社会。そんな大きな社会に対して、彼ら彼女らはあまりに無防備で、そしてそれによって深く傷ついている。
私はそれに腹が立って仕方なかった。悔しくて仕方なかった。彼らの苦しみは、自分の苦しみでもあったからだ。やはり、こうした社会には絶対に立ち向かわなければいけない。もはや一刻の猶予もない。そして彼ら彼女らの姿は、これから訪れる母と私の未来の姿をまさにシミュレーションしているようでもあった。
■いくつになっても、私は母の承認に飢えていた
このとき、私の母は60代だ。この頃の私と母の関係は、傍から見ると人生でもっとも良好な仲を続けていたように見えただろう。
私はこの頃になると、立て続けに孤独死の本を出したこともあり、専門家としてメディアなどで取り上げられはじめた。母からするとそんな私は、いわば社会的な成功ルートを着実に歩んでいるように見えたはずだ。
私の活躍を見て、母は歓喜した。母の望む「一般的な女性の人生」からはちょっと逸れてはしまったが、とりわけ本の出版は大きく、ようやく地元で周囲に自慢できるネタができたと思ったのだろう。
母は気持ち悪いほどに私に媚びへつらい、私を持ち上げ、電話ではいつも上機嫌だった。
では、肝心の私の気持ちはどうだったか。
母と電話で話したり会ったりすると、唐突に母の寵愛を求めたい「幼い子どもの私」が頭をもたげてくる。
母に認めてもらえて、嬉しくなかったと言えば嘘になる。私は、正直嬉しかった。母に褒められ、有頂天になっていたのだ。
■私は母が大好きで、そして大嫌いでもあった
それと同時に、私は焦っていた。これまで見て見ぬふりをしていた母の老い。しかし、母は年々老いてきている。そして、大学を卒業してから東京に住んでいる私。
たった一人のきょうだいである弟も家を出て、責任ある仕事に就いている。何かあったら、弟もおいそれとは仕事をほっぽり出せないだろう。母は宮崎のあの家にいる。もし父が亡くなったら、母はどうなるのだろう。
母はまだ60代で、血圧の薬を常用しているものの身体的に元気ではある。だからこそ、絶妙なバランスの上に、私たちの関係は成り立っている。しかし、今後親が弱ってきたら、私は老いた母を十字架のように背負って、人生を生きていかなければならないのだろうか。
重い、重すぎる――。このときも、まだ私は亡霊のような母の呪縛に苦しめられ、右往左往していた。死ぬほど欲しかった母の愛。いくら求めても足りない母からの承認――。複雑怪奇に絡み合った母と私。絶対にほどけないと思っていた因果。
確かに私は母が大好きで、そして大嫌いでもあった。私はそんな感情をジェットコースターのように行ったりきたりしている。そもそも私はこの歳になっても、母に認めてもらいたいと思っているではないか。幾度となく自問自答する日々が続いた。
何歳になっても、母に認めてもらいたい私が、確かにずっとここにいる。その半面、母から逃れたいという相反する強烈な思いもある。ぐちゃぐちゃに入り乱れた母への感情。それが、私自身をとてつもなく苦しめている。
■「子どもが親の面倒を見るべき」という旧態依然の血縁主義
矛盾だらけの私は、そんな母親への愛憎を抱えたまま、老いゆく母親の介護をしなければならないかもしれない、恐ろしい現実に耐えられるのだろうか。
何度も何度も、母によって傷ついてきた私たち。生きづらさを抱えてきた私たち。
そんな私たちは、死ぬまで苦しめられるのだろうか。苦しめられ続けなければならないのだろうか。
いやもう、自由になってもいいのではないか。最後ぐらいは、自由になりたい。命が尽きるその前に、やっぱり私は母と決別しなければならない。母の承認の奴隷になるのは、もうやめよう。
そのためには母から徹底的に離れることだ。社会において母から「逃れる」ために、「子どもが親の面倒を見なくていい」という選択肢を現実にかたちにしていくことだ。そんな思いに共感し、手を取り合える仲間たちを草の根的に増やしていくことだ。
私が母から激しい虐待を受けていた遠い昔――。あれから月日は流れた。
日本の状況を振り返ってみると、日本の家族はさらに形骸化して、荒廃したといえる。しかし、血縁主義は根強く残り、そこに多くの人たちが苦しめられている。それは私が取材でつかんだ、れっきとした事実だ。時代は、そして私自身、家族に代わって引き受けてくれる何かを切実に、喉から手が出るほどに求めている。
親から逃れたくても、受け皿がないのだ。笑っちゃうほどに、どこにもないのだ。なぜなら、「子どもが親の面倒を見るべき」という旧態依然の血縁主義の社会システムが、日本にはびこっているからだ。
そして、それはけっして遠くない未来に迫りくる、私自身の重大な危機なのである。
■私は母を捨てたい
かつて未成年で無力な私にとっては、『日本一醜い親への手紙』がバイブルだった。たった一冊の本が、私の命綱だった。あれから何十年も経つのに、死までのラストスパートで、多くの人が毒親と直面して苦しんでいる。そんな人が世の中に何万人いるのだろうと想像して身震いがした。
私の役目は、なんとしてでもこうした社会と戦うことなのではないだろうか。無邪気に正しさを押しつける社会に抗うことなのではないだろうか。社会の水面下に押しやられている目に見えない苦しみを、明らかにすることなのではないか。そうして私なりの解決策を、社会に示すことなのではないか。それは当事者で、さらに取材者として、さまざまな世界を横断してきた私だからできることかもしれない。
私は取材を重ねるうちに、本音と向き合えるようになっていった。
なぜここまで私は、親問題にこだわり続けるのか。「私は母から自由になりたい。母を捨てたいのだ――」と。ずっとその感情を押し殺してきたのだ、と。それが叶わない社会だから、どうしようもなくつらいのだ、と。
それからというもの、親を捨てる方法をずっと考えていた。母から自由になるには、いったいどうすればいいのだろう。
そんな中で私が目をつけたのが「終活関係者」だ。運のいいことに、孤独死の取材をはじめてから、葬儀社や事故物件不動産屋などの、いわゆる「終活関係者」と会う機会が多くなっていた。彼らの中には、「おひとり様」の高齢者のサポートをビジネス展開しようと仕掛けている、ベンチャー精神のある人たちがいる。その中に、何か大きなヒントがある気がした。
なんとか、ここに突破口はないものか。
■「家族代行ビジネス」との出合い
「家族代行業」を請け負っている一般社団法人LMNの遠藤英樹さんと出会ったのは、事故物件の取材をはじめた頃だ。家族代行業とは、親やきょうだいと当事者との間に入り、家族の手足となってサービスを請け負っている民間業者だ。その範囲も「介護から納骨まで」と幅広い。
終活関係者には、家族愛について当たり前のように熱弁を振るう人たちも多い。しかし、遠藤さんは彼らとはまったく違い、どこか冷めた目をしていた。そして決まりきった倫理観を押しつけない雰囲気が、やけに印象に残った。何よりもそんな遠藤さんといると、なぜだか気が楽だった。
私は遠藤さんの「家族代行業」に興味を持ち、彼と行動を共にするかたちで取材を重ねた。
遠藤さんから聞いて驚いたのは、終活サポートに申し込むのは、本人ではない点だ。このサービスの依頼主は、「おひとり様」である高齢者本人ではなく、その家族なのだ。つまり端的に言うと、「お荷物」になった高齢者の面倒を見てほしいというものである。しかし、それぞれのケースにそれなりの事情があった。
■修復不可能にまで錯綜した家族関係の根深さ
私は遠藤さんの現場に同行して驚愕した。ある女性は、都内のカフェで遠藤さんと向き合うなり、こうまくし立てた。
「ほんと遠藤さんがいなかったら、どうなっていたかと思うの。私たちの部屋に、いきなり弟の介護ベッドが持ち込まれるなんてことを想像したら、卒倒しそうになったの」
――遠藤さんがいて、本当に助かったわ。
聞くと女性には長年にわたって会っていなかった弟がいた。その弟が倒れたと病院から連絡があったらしい。突然、介護を押しつけられた女性は戸惑うしかない。そこで、遠藤さんを頼ったというわけだ。女性は遠藤さんの存在を知って、心底胸を撫でおろしていた。
これだ! と思った。私は母親の最期を、遠藤さんに請け負ってもらいたい。母が元気なうちはいい。しかし、母は絶対に老いていく。そのとき、私はきっと傷つき、疲れ果てるだろう。私は、やっぱりすべてを手放したいのだ。
私だけではない。多くの終活関係者と違って、遠藤さんは家族の切実な「困りごと」に真摯に耳をすませる。家族が話す言葉の一つひとつに耳を傾け、否定も肯定もしない。その姿勢が、自然でいい。それと同時に、遠藤さんは修復不可能にまで錯綜した家族関係の根深さを理解しているのだろうと確信した。
■毒親の最期を押しつけられた子どもたち
取材を重ねて、親に苦しんでいる人たちがこれだけ世の中にいることは、すでにわかっている。だから遠藤さんにはその人たちの手助けをしてほしい、と強く感じた。どうか毒親の最期を半ば強引に押しつけられた子どもたちに、その現実的な逃げ道を開いてあげてもらえないだろうか。
遠藤さんが手掛けているのは「家族代行ビジネス」なのだ。遠藤さんに、もっともっと親を捨てたい子がマッチングすればいい。このとき、遠藤さんはほぼ一人で活動していて、草の根的でまだほとんど誰にも知られていなかった。そのため私は、何とかして遠藤さんの活動が一般的なものになるよう成長してほしいという願いを、密かに抱いていた。
毒親の最期と向き合うのは、ドン・キホーテの物語のような、途方もない骨折り作業だ。それは、世間に戦いを仕掛けることである。血縁主義の世の中に対して、反旗を翻すことである。どこからどんな弾が飛んでくるかわからない。そこはまさに地獄の戦場で、毒親育ちの私たちはゲリラ戦を戦わなければならないのだ。つねに戦況は思わしくない。
親を敬うことが当たり前だと強いる世間。血縁社会の中で感じる圧倒的な無力さ。それは幼い頃に感じた強大な母を目の前にしたときの無力さに近い。心が折れそうになる。
■親から逃れるために、親の最期を外注してもいい
だからこそ、遠藤さんのような人が必要なことはわかっていた。遠藤さんの活動を世に知らしめること、そして私がその手助けをすること。そのためには、昔のように小さく震えてはいられないのだ。それが母に囚われていた私が今、社会にできる、ただ一つの問題提起なのだから。
それなら、私と遠藤さんで切り開いていくしかない。私自身のために、そして世の中で親に苦しみ、生きづらさを抱えるすべての人のために――。
長崎で出会った、ゴミの中で息も絶え絶えだったゴミ屋敷の女性。父親の教育虐待の末、引きこもり、歯がすべてなくなり孤独死した男性。彼らの姿が、脳裏に浮かんだ。どれも母の虐待の末に引きこもった私自身が辿ったかもしれない道なのだ。
ずっと死にたいと思っていたあの頃の私は、『日本一醜い親への手紙』に支えられて生きてきたではないか。あの本と出合った瞬間、目の前を覆っていた霧がスッと晴れるような感覚になったではないか。
日本の社会では一般的に、逃げることはよしとされない。
しかし、なぜ逃げてはいけないのか。私たちは、ずっと苦しめられてきた。だから苦しければ逃げていい。親から逃れるために、親の最期を外注してもいい。世間の常識に囚われなくてもいい。最後ぐらいは、いや最後だからこそ母と離れていたい。苦しみから、遠ざかっていたい。それを許してもらえない社会と戦いたい。そう感じるようになっていった。
■毒親の介護に苦しんでいる子供たち
幸いにも、いや皮肉にもというべきか、私には書くという武器があった。母に実装された武器が――。今こそこの武器を取って立ち上がるのだ。
私は出版社に「親を捨てたい子」の現実を描きたいと、企画を持ち込んだ。企画は無事に通り、『家族遺棄社会』として出版された。『家族遺棄社会』では、親を捨てたい子のさまざまなリアルな声を拾い集めた。そして本書の中で、遠藤さんの活動を大々的に取り上げた。それは私が半ば意図的に仕掛けたものである。
そんな私の仕掛けに、雑誌「週刊SPA!」が食いついてきた。私はそこでも遠藤さんの活動を売り込んだ。そして、その巻末では、『毒親と絶縁する』の著者である評論家の古谷経衡さんと対談した。
私は内心ビクビクしていた。ここまでいろいろな仕掛けをしてみたものの、世間から冷たい目で見られるのではないかと感じていたからだ。しかし、蓋を開けてみたら、反応は真逆だった。同じ思いを抱える人々から、私や遠藤さんにたくさんの応援のメッセージが届いたのだ。それはとても心強かった。
毒親の介護に苦しんでいる子供たちが、これだけ世の中にいること――。それがはじめて可視化された気がした。そして、そんな「親を捨てたい」「距離を置きたい」という切実な思いも受け取った――。私はその反響の大きさにただただ驚き、今後自分が何をすべきか、考えさせられた。
■親を捨てたい子どもたちから依頼殺到
その後、私はウェブメディアでも「親を捨てたい子」の記事を書いた。もっと多くの人たちに私のメッセージが届くことで、少しでも親から自由になる人たちがいる。そう感じたからだ。それは私なりの小さな反乱であり、世間に投げ込む手製の爆弾であった。そして、それは大勢ではなかったが、確かに一部の人に届いたようだ。
遠藤さんの元には、次から次に親を捨てたい子どもたちからの依頼が殺到したからだ。遠藤さんの活動は世間ではまだ珍しく、潜在的な需要があったのだと思う。
私の著作や遠藤さんの活動は、大手メディアでも取り上げられるようになった。遠藤さんと私は二人三脚だった。私はたびたびテレビ出演を依頼されたが、出演を頑なに断った。ディレクターからは怪訝(けげん)そうな返事がきたが、取材者ではなく親を捨てたい子をサポートする遠藤さんがメディアの前面に立つことにこそ意味がある、そう感じたからだ。
遠藤さんがメディアをジャックすることで、多くの親を捨てたい子どもたちの代弁者となりえるはず。私の強い願いどおり、遠藤さんの活動は一つのムーブメントになりつつあった。たった一人からはじまった遠藤さんの活動は、当初の思惑以上にどんどん大きくなっていったのだ。
----------
菅野 久美子(かんの・くみこ)
ノンフィクション作家
1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。
----------
(ノンフィクション作家 菅野 久美子)














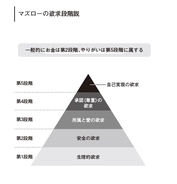

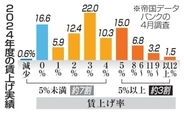









![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








