【動画を見る】『ビリー・アイリッシュ:世界は少しぼやけている 』公式予告編
ここ数年、ジャンルやキャリアを問わず、大物アーティストたちの音楽ドキュメンタリー作品が増えている。昨年はテイラー・スウィフトやブラックピンクやアリアナ・グランデなどのドキュメンタリーが話題を呼んだが、今年に入ってからもビリー・アイリッシュやブリトニー・スピアーズの注目作が公開。リアーナやザ・ウィークエンドもドキュメンタリー企画が進行していることを明かしている。ベテラン勢に目を向けると、近年はボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンのドキュメンタリーが記憶に新しい。
『BLACKPINK ~ライトアップ・ザ・スカイ~』予告編
なぜ今、「ドキュメンタリーのブーム」が加速しているのだろうか。
ひとつには、映像ストリーミングサービスの時代に入って、ドキュメンタリー作品の人気が如実に高まっていることが挙げられるだろう。ビリーのドキュメンタリーはアップルが2600万ドル、リアーナのドキュメンタリーはアマゾンが2500万ドルで買ったという報道からも、そのニーズの高さが伺える。しかも、今は映像ストリーミングのプラットフォームが乱立する戦国時代。契約者増加に繋がるコンテンツの奪い合いが過熱するのは当然だ。
また、2010年代末から顕在化し始めたこのブームは、特にパンデミック以降、ライヴの代わりにアーティストとファンを繋ぐ新たなツールとして役割を果たしているところがある。もちろんライヴストリーミングコンサートも同じ機能を持つが、ドキュメンタリーはよりアーティストの「素顔」を伝えるメディアとしてのニーズがあるのだろう。
アーティスト側が「見せたいもの」
もっとも、前号で取り上げたライブストリーミングコンサート同様、ドキュメンタリー制作も多額の予算を要するため(ビリーのドキュメンタリーは製作費100~200万ドルと言われている)、大物とインディや新人との更なる格差拡大に繋がる恐れがあることは指摘しておかなくてはならない。
それに、基本的に最近のドキュメンタリーはアーティストや所属レーベル発で作られているため、どれだけ監督に自由を与えていると言っても、最終的にはアーティスト側が見せたいものを見せたい形で見せるためのものだろう。そこには本当の「素顔」は存在しない。換言すれば、第三者の視点、つまりジャーナリズムが欠けているので不健康だという言い方もできる(日本未公開のブリトニーのドキュメンタリーはNYタイムズ制作なので例外的)。
だが、そもそも2010年代は、従来のメディアの影響力が低下し、SNSの台頭でアーティスト本人の発信力が強まったディケイドだった。今や大物アーティストは、メディアのインタビューというリスクはあってもメリットが少ないプロモーションにはほとんど応じない(せいぜいアルバム1枚につき1本、よくて2本だろう)。その点から考えても、ドキュメンタリーのブームが起きているのは理に適っている。
その良し悪しの判断は一旦置いておくとして、映像ストリーミングサービスの隆盛というメディア構造の変化、そして2010年代以降のアーティストとファンとメディアのパワーバランスの変化を背景にしているドキュメンタリーの台頭は、しばらく勢いが留まりそうにない。
Edited by The Sign Magazine
【画像を見る】ローリングストーン誌が選ぶ、史上最高のベーシスト50選(写真50点)













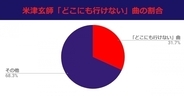











![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








