【写真を見る】空港で見た混乱と絶望
ロシア兵たちが私の車に向かって銃を発砲した瞬間、もうダメだと死を覚悟した。ロシア軍によるウクライナ侵攻開始から8日目のことだ。私と妻のイリーナ・サムソネンコは、大急ぎでスーツケースとふたつのキャリーバッグにありとあらゆる貴重品を詰め込んだ。いまならまだイルピンの駅まで無事にたどり着ける——そう思いながら、運転手を雇った。イルピンはウクライナの首都キーウ(キエフ)郊外の小さな田舎町で、ロシア軍によるミサイル攻撃がはじまってから、私と妻はこの近くで暮らす友人のゲストハウスに避難していた。駅を目指して車を走らせるや否や、私たちの期待とは裏腹にロシア軍の装甲車両と鉢合わせてしまった。
「戦車よ!」。助手席に座っていたイリーナが誰よりも先にロシア兵を見つけて叫んだ。「車をバックさせて! 引き返して!」。イリーナが声を上げると、運転手は必死でギアをリバースに入れようとした。
もはや手遅れだった。ロシア兵たちは何の警告もなく機関銃を構え、私たちのトヨタの「カムリ」に集中射撃を浴びせた。
記憶があいまいで、その後の数秒間のことはよく覚えていない。私と妻は、どうにかして走行中のカムリから脱出して柵を乗り越え、真っ青な仮設トイレの後ろに隠れることができた。運転手を失ったカムリはそのまま猛スピードで傾斜を下り、小さなアパートメントを囲む柵に衝突して止まった。
「出てきなさい——トイレの後ろに隠れていることはわかっているんだ」と、ひとりのロシア兵が叫ぶ。盾としてはまったく役立たずの仮設トイレ(プラスチック製の仮設トイレに防弾機能は期待できない)の後ろから両手を挙げて恐る恐る出ると、自分たちは丸腰の民間人で、駅に行く途中だと説明した。ロシア兵たちが詰め寄り、私たちと妻の顔に銃口を向ける。
だがこれは、迫り来る悪夢の序章に過ぎなかった。”世界最恐”の異名をとる残酷な軍隊に捕えられた私と妻には、拘束と尋問という恐ろしい運命が待ち構えていたのだ。
悪夢は、ひとつの誤算からはじまった。「戦争は起きない」——キーウでは、知識人やその筋に明るいと言われる多くの人がこの言葉を繰り返していた。私と妻がウクライナで暮らすようになってから21年がたつ。私は米国出身の軍事アナリストで、ロシア政治のアナリストおよび航空コンサルタントとしての経歴をもつ。プーチン大統領が武力でウクライナを脅すのは、近年では決して珍しいことではない。
ウクライナの人々を恐怖に陥れて、日常生活を破壊するための戦争
2022年2月14日。私と妻は仕事で会議に出席するため、スウェーデンの首都ストックホルムを訪れていた。ちょうど学校が休みだったこともあり、英国ケンブリッジの寄宿学校に通う息子のアントニオ・ブラジレイロも合流して一緒に休暇を楽しんだ。普段なら、アントニオはキーウの自宅で休暇を過ごす。
アントニオがストックホルムからロンドンに戻ると、私たちは安全なストックホルムに残るという選択肢を捨ててキーウの自宅に戻った。いま振り返ってみると、自分がなぜこのような判断を下したのか理解に苦しむ。だが、当時の私たちにとって自宅から遠く離れた北欧の見知らぬ街でロシアがウクライナに攻め込むかどうかを見守るのは、考えられないことだった。
それに、イリーナのきょうだいとその家族だけでなく、イリーナの母もウクライナで暮らしている。キーウをはじめ、ウクライナのあらゆる街に友人がいた。私は、彼らを残していきたくはなかった。息子を育てた場所、誕生日や休暇を過ごした場所には、人を引き寄せる磁力がある。私たちの場合、その磁力は少し強すぎたのかもしれない。
3日後の午前4時ごろ、ロシア軍によるミサイル攻撃がはじまった。空襲警報が鳴り響き、私と妻は自宅の前を走る大通りの反対側の地下駐車場に避難した。地下駐車場の上はキーウ屈指の近代的な高級ショッピングセンターで、2軒のカフェと地下にはワインバーまで備えた24時間営業のスーパーマーケットも併設されている。ロシア軍による攻撃が続くなか、私たちは固唾を呑んでニュースを見守りながら、その日をやり過ごした。
夕方になると、ようやく自宅に戻ることができた。だが、その数時間後にまたミサイル攻撃がはじまった。私たちは、どうしていいかわからなかった。車でウクライナ西部を目指すこともできなくはないが、道路には車があふれ、何マイルにも渡って渋滞が伸びている。おまけに、キーウからポーランド国境まではどこを探してもガソリンなんて一滴も見つからない状態だ。キーウからの脱出は、もはや不可能だった。
辺りに立ち込める煙硝の臭いが私たちの無力感を募らせた。これはウクライナ軍に対する単なる軍事行動ではなく、ウクライナの人々を恐怖に陥れて日常生活を破壊するための戦争なのだ。具体的な軍事目的の達成は、ロシア軍にとっては二の次に過ぎない。そしてこの戦争は、現在も続いている。
【写真を見る】幸せな日々——家族でフロリダ州フォートローダーデールを訪れたとき。左からイリーナさん、ジョンソンさん、そして息子のアントニオさん。ウクライナで悪夢のような日々が待っているとは、このころは知る由もない。(COURTESY OF REUBEN F. JOHNSON)
誰かに攻撃されている、という感覚を忘れることができない
キーウ中心部の防空壕で2晩過ごした後、私たちは避難を決意した。幸い、中心部から車で1時間くらいで行ける郊外に友人がいる。空襲がひと段落するまでゲストハウスに泊めてもらえないかと相談すると、友人は快諾してくれた。だが当時の私は、郊外の戦況を把握していなかった。振り返ってみると、私はここでも判断を誤ったわけだ。
友人のゲストハウスに到着してから2日もたたないうちに、ロシア軍とウクライナ軍がキーウ周辺で激戦を繰り広げ、ホストメリの空港が閉鎖された。ミサイルや追撃砲による攻撃によって水道網と電力網が破壊された。無事ゲストハウスまでたどり着けたのはいいが、今度はキーウへの帰路を断たれてしまった。首都攻略を目指すロシア軍の進撃を防ぐため、郊外とキーウをつなぐ橋という橋が破壊されたのだ。私たちは安全な場所を求めてキーウを後にしたつもりだったが、逆に身動きがとれなくなってしまった。武装したロシア兵が周辺一帯を取り囲んでいた。ネズミ一匹さえ逃げられない状況だ。
ロシア軍とウクライナ軍の戦いは、その後も数日にわたって繰り広げられた。爆発音が響く回数も増え、戦闘がいつ終わるかもわからない。悪夢から数カ月がたったいまも、私はちょっとした物音に怯え、隠れる場所を探してしまう。誰かに攻撃されている、という感覚を忘れることができないのだ。
英国では、息子のアントニオが不眠不休で戦況を見守っていた。夜になるとウクライナにいる友人や知人と電話で話し込んでは、彼らの防空壕探しを手伝ったり、戦闘地域から逃れる方法を模索したりした。だが、私たちと連絡をとる手段は限られていた。
電力網が破壊されたため、ガソリン発電機が導入された。それでも、1日に供給できる電力はたった3時間。これではスマートフォンもろくに充電できない。仮に充電できたとしても、階段を上ってゲストハウスの上階まで行かないと電波がない。四六時中、いたるところで何かが爆発しているなか、上階に行くのは自殺行為のように思われた。キーウにいたころは、空襲警報が危険を知らせてくれたおかげで地下の防空壕に避難することができた。だが、郊外の田舎で警報が流れることはない。ミサイルや追撃砲が接近するヒューっという高音が聞こえるくらいだ。
3月2日の水曜日を最後に、私たちとアントニオの連絡は途絶えてしまった。その翌日、私はノートパソコンのバッテリーの残量を使ってロシア軍の苦戦に関する記事を書いた。だが、記事を書き終えることはできなかった。ロシア軍の装甲車両が家の外の道路で停車するたび、私とイリーナ、友人とその家族、家政婦、ベビーシッターは地下室に避難しなければならなかった。ロシア軍は、ウクライナの田舎道に迷っているようだった。
やがてロシア軍はいなくなったが、この出来事といくつかの現実によってこれ以上ゲストハウスに留まるのは不可能のように思えた。私たちはトイレに行くたびに懐中電灯を使い、定期的にシャワーを浴びることもできなかった。それに加えて、近隣には食料を調達できる場所もない。私たちは、キーウ中心部の自宅に戻ることを考えた。世間の予想とは裏腹に、キーウはまだ陥落していなかった。自宅に戻れば、少なくともシャワーを浴びることはできるし、スーパーマーケットも営業している。防空壕で寝なければいけないとしても、ここにいるよりはまだマシだ。
そうして私たちはキーウに戻ることにした。その結果、ロシア軍に捕えられた。
手榴弾で脅迫
ロシア兵がカムリを略奪する間、私たちはただただ恐怖に震えていた。廃車同然のカムリを目にした茫然自失の状態から冷めやらぬうちに、私たちは宝物が荒らされ、壊され、盗まれるのをただ見つめることしかできなかった。イリーナは、家族の写真やピアノを弾く息子の姿を収めた動画などでいっぱいのハードディスクを持参していた。イリーナのハードディスクをはじめ、ほとんどのものはこの戦犯たちに盗まれ、どこかに売られてしまった。一生の思い出が一瞬にして失われたのだ。
ふとイリーナを見やると、顔から血が流れていた。奇跡と言っていいかどうかわからないが、私も妻も撃たれずに済んだ。それでも、砕け散ったガラスの破片がイリーナの左の頬を傷つけ、目にも細かいガラス片が入っていた。居合わせたロシア人の衛生兵が処置をしてくれたおかげで最悪の事態を免れたのは、不幸中の幸いだった。それでもイリーナは、いまも頬にガラス片が残っているような感覚があると言う。
ノートパソコンやハードディスクは、すべてロシア兵に奪われた。私の記事や保管していた資料、写真をはじめ、すべてが失われてしまった。その後、私たちを略奪したのと同じロシア兵が何十人もの民間人を拷問したあげく処刑し、無数の人々に性的暴行を加えたことがわかっている。ロシア兵たちは、レイプされた女性や子供たちの半焼けの状態の遺体や目を覆いたくなるほど大量の集団墓地を残していったのだ。
私たちを捕らえたロシア兵には、ノートパソコンの他に思わぬ掘り出し物が待っていた。ノートパソコン用のバッグの中を荒々しく探していたひとりが書類入れを発見した。そこには、私たちが貯めた息子の教育費が入っていた。「外貨だ!」そこにいたロシア兵の中でも一番タチの悪そうな奴が嬉しそうに札束を穴だらけのカムリに叩きつけた。
ロシア兵たちにとっては、人生最高額の宝くじを当てたようなものだ。息子の教育費と車、ノートパソコン、周辺機器、スマートフォン、宝石、カメラ、衣類、個人的な品々など、すべてを合わせると15万ドル(約2050万円)以上の価値があるのだから。
私たちを捕らえた直後、ロシア兵たちは金目のもの探しに注力を注いでいたが、そのうちに私の資料の山を漁りはじめた。ミサイルシステムの歴史に関する記事を書くための資料だ。いつ殺されるかわからない、という恐怖さえなければ、この光景は滑稽に映ったかもしれない。
これらの資料は、誰もが無料で閲覧できるオープンアクセス論文やプレスリリース、全ページの上と下の部分に「非機密扱い」と太文字で記された政府刊行物だった。それなのに、低脳なロシア兵たちは、私が超重要任務に携わる諜報員であると確信した。有頂天になった彼らは私のコートのポケットに手榴弾を入れ、所属している情報機関を明かさないとピンを抜くと言って脅した。
金目のものをすべて盗み終えると、私たちは近隣のビルの暗い地下室へと連れて行かれた。そこには、大勢の民間人が拘束されていた。そのうちのひとりは、ひたすら自分の携帯番号を連呼している。私が番号を記憶して、誰かに報告することを期待しているのだ。民間人がここに拘束されている理由はわからないが、助かる見込みがないことはわかった。実際、彼らの多くは周辺の集団墓地の中から発見された。
装甲車から放り出されたウクライナ人
その後、私と妻は装甲車両の中に押し込められた。続いてふたりのウクライナの民間人が投げ込まれ、脚の上に重なった。ふたりは後ろ手に縛られている。この状態のまま、車は1時間半ほど走った。移動中、ロシア兵のひとりが私の金の指輪を盗んだ。25年間肌身離さず身につけていたこの指輪は、私にとってかけがえのない宝物だ。アントニオが大学を卒業したら譲るつもりでいた。
そうこうしているうちに、車は森の真ん中で停車した。ふたりのウクライナ人は、極寒の泥の地面に放り出された。その後、ふたりがどうなったかは知らない。ロシア兵たちの残酷さを踏まえると、最悪の事態を想像せざるを得ない。
私と妻も車から降ろされ、立つようにと命じられた。座ることは許されず、あたりの気温は急速に下がっていく。夜が訪れるころには、私たちは寒さでぶるぶる震えていた。他のロシア兵が眠りについたら、森の奥に連れて行かれて、そこで射殺されるのだろうか? たしかに、これなら目撃者の心配はない。
私と妻は、向かい合った状態で2時間ほど立っていた。互いの手を取り合って暖をとり、盗まれずに済んだ唯一のものであるイリーナのハンドバッグを交代で持った。すると、私たちを不憫に思った何人かのロシア兵がわずかばかりの温かい紅茶をくれた。気温が更に下がるなか、私たちは運命を左右する命令を待ち続けた。
持っていた資料についていくつか質問された後、ロシア兵は私と妻をワゴン車に案内し、ロシア版のCレーション(訳注:米軍の戦闘糧食)のようなものと水を渡して去っていった。兵士が言うには、私たちは翌日また別の場所に移送されるそうだ。夜は定期的に運転手が様子を見に来ては、10分ほどエンジンをかけて車内を暖め、エンジンを切ってどこかに消えた。私たちはワゴン車の固い後部座席の上で眠ろうとしたが、翌日どんな運命が待っているかもわからない状態で眠ることはほぼ不可能だった。
翌朝、私と妻は四輪駆動車の中に押し込まれた。車は、焼けた軍用車両や民間人の車がそこここに散らばる道路を進む。地面からは、ミサイルの後部が飛び出ている。不発弾だ。見渡す限り、爆発と破壊の跡が広がっている。それは地獄のような光景だった。
目隠しが外されると、そこは狭い部屋だった
やがて目的地に到着した。キーウ北西の郊外にあるホストメリの空港だ。私は、ジャーナリストとしてプーチン政権を批判してきた。こうして空港まで連行されると、ロシアの飛行機に乗せられてグラーグ(訳注:ソ連時代の強制収容所)にぶち込まれるかもしれない、という恐怖が現実味を帯びる。あるいは、もっと恐ろしい運命が待っているかもしれない。だが、空港の滑走路はもはや使い物にならないほど破壊されており、ロシア軍はこの空港を指揮所代わりにしていた。私たちは目隠しをされ、地下の貯蔵庫に連れて行かれた。目隠しが外されると、そこは狭い部屋だった。室内には、引き出しが抜かれた木の机と安物の椅子3脚の他には何もない。
床は汚れていて、空気は冷え切り、湿気でじっとりしていた。肺炎にかかるのは時間の問題だ。助かるかもしれないという希望が消えゆくなか、私とイリーナは息子のことを考えて互いを励まし合った。部屋には時計もなければ、カレンダーもない。そこでイリーナは、フランスの文豪アレクサンドル・デュマの小説『モンテ・クリスト伯』にならって時の計算ができるようにした。1日ずつ壁に1本の縦線を描き、7日目に斜線を引く、という昔ながらの画線法だ。私たちがどれくらい拘束されるかを知るのは不可能だった。誰ひとりとして私たちの拘束の理由、あるいは誰の指示によるものなのかを教えてくれなかった。外の世界の人々は、私たちがここにいることはおろか、生きているかどうかさえ知らないのだ。世が明けると、廊下の反対側の部屋からラジオや電話の音が聞こえてくる。それを聞いて私たちは、捕虜としての1日がまたはじまったことを知った。
英国ケンブリッジでは、息子のアントニオが異変に気づいた。その日は日曜日で、私たちと最後に言葉を交わしてから3日がたっていた。何かがおかしい、と思ったようだ。苦労の末、ようやくアントニオは私たちをゲストハウスに避難させてくれた友人に連絡を取ることができた。息子は、友人の口から恐ろしい事実を聞かされた。
友人は、運転手から私たちがロシア兵に捕えられたことを知った。運転手は私たちと一緒に森に連れて行かれなかったため、翌日ホストメリの空港にも行かずに済んだ。複数の人たちと別の場所に連行されたが、何とか逃げることができたのだ。これは後になって知ったのだが、運転手が友人の家まで戻ってくれたおかげで、友人は私たちがどうなったかを知ることができたそうだ。
アントニオは、私の友人や大学時代の同級生と面識があった。その多くは軍の関係者で、引退後は防衛請負会社や国防総省で働いている。当時息子はまだ18歳だったが、アメリカの官僚制度の仕組みを把握していた。私たちを救出するため、アントニオはすぐに動いた。
まず最初にアントニオは、ロンドンのアメリカ大使館に電話をした。平常心を保ちながら、両親が置かれている状況について話がしたいと申し出たのだ。だが、電話に出た相手は「面会の予約を行なってください」と機械的に突き放した。
そこでアントニオは、私の親しい友人のひとりであるジョン・ショプナー空軍少将に相談した。ショプナー少将は優秀な戦闘機パイロットで、ベトナム戦争では154もの戦闘任務に携わり、カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地の司令官まで務めた人物だ。
ショプナー少将は公明正大な人としても有名で、誤解や誤った解釈、あるいは無視に対してはどこまでもストレートに切り込むことで知られていた。
アントニオから話を聞いた次の瞬間、ショプナー少将の頭の中で警報装置が点滅した——それも5万ルーメンの明るさで。少将は、ロンドンのアメリカ大使館に電話をした。後に少将は、当時のことを「大使館側の意識を自分たちに集中させるための軍事演習」と表現した(アントニオがロシア語で認めたメモには「少将はひどく騒ぎ立てた」と書いてある)。
少将の介入は効果てきめんだった。ものの数分もしないうちにロンドンのアメリカ大使館の役員からアントニオに電話がかかってきたのだ。役員は、アントニオをモスクワのアメリカ大使館につないだ。そして幸運にも、国務省は私たちが置かれている状況をその筋の専門家の耳に入れてくれた。
私たちの健康状態や捕えられた場所、現在拘束されている場所の候補地など、アントニオの担当者はとても几帳面で、次々と的確な質問をした。さらに担当者は、捕虜交換または解放に向けての調整が進められていることも伝えた。
それと並行してショプナー少将は、面識のある国防総省の職員に連絡を取り、事態の深刻さを伝えた。私は長年国防総省のコンサルタントを務めており、ペンタゴンには30年以上出入りしている。職員たちにとっても、私は見ず知らずの他人ではないのだ。
衛生条件は、存在しないも同然だった
その後もアントニオはアメリカ、英国、ウクライナのありとあらゆる政府機関の職員と密に連絡を取り合った。キーウでは、救出作戦がまとまりつつあった。ウクライナ軍の特殊部隊がホストメリの空港を襲撃するのだ。
私と妻は、そんなことは何も知らなかった。アントニオと連絡を取る術もない。アントニオは不安でいっぱいで、1日2時間しか寝なかったそうだ。想像を絶する苦しみを味わったに違いない。心の傷の治癒には、長い時間がかかるだろう。
私たちは、良く言えば情報がまったく届かない”真空地帯”にいた。それでも、この戦争が早々に収束しないこともわかっていた。3月初旬の時点で、すでに誰もが——私たちを監視するロシア兵でさえ——戦争の長期化を覚悟した。拘束から数日がたち、私はロシア兵と言葉を交わせるようになっていた。その際、兵士のひとりは「戦闘は4~5日間だけ。ロシアがウクライナを制圧したら、故郷に帰れる」と、上官に言われたことを明かした。他のロシア兵たちも同じことを言われたそうだ。
私と妻は地下の部屋に拘束されていた。窓はない。ドアはあったが、開けたら撃たれるという恐怖心のせいで開けることはできなかった。部屋はAK-47を抱えたロシア兵によって常に監視されており、数時間ごとに監視役が代わった。ふたりきりでいられるのは、寝ている時だけだった。『冒険野郎マクガイバー』(訳注:1985~1992年までアメリカで放送されたアクションドラマ)の主人公も匙を投げるほど堅牢なダンジョンだ。
私たちは、ひとり分の大きさしかないペラペラのマットレスで眠った。3月初旬のウクライナはまだ寒い。それなのに、与えられたブランケットは1枚だけだ。私のコートを丸めて枕にし、イリーナの毛皮のコートをブランケットに重ねて我慢するしかなかった。床は岩のように固い。この床のせいで、カムリから飛び降りた時の怪我はますます悪化した。身体的外傷から回復したのは、数カ月後のことだ。
衛生条件は、存在しないも同然だった。空のペットボトルをトイレ代わりに使った。それ以外は、部屋の隅にあるバケツを使う。幸い、蓋のおかげでいくらか悪臭を和らげることはできた。戦闘糧食の供給はあったが、手をつけることは稀だった。「何も食べていないじゃないか」と、部屋に入ってきた将校に言われた。拘束された最初のころは、将校が何度かやってきて私たちを尋問した。
カムリを略奪したロシア兵は、私たちが衣類や所持品を持っていくことを禁じた。それでも勇気あるイリーナは、銃口を向ける兵士に立ち向かい、私の薬といくつかの所持品、日記を持っていくことを認めさせた。こうして私は、悪夢の日々をこの日記に記録している。もしここで命を落としても、いつかアントニオの手に渡るという期待を抱きながら。
私は高血圧症を患っているため、薬は必要不可欠だ。血圧を正常な状態に保つため、旅行ポーチに錠剤を入れて常に持ち歩いている。だが、この近代のダンジョンのような貯蔵室での日々が相当なストレスをかけていたのか、私の血圧は危険な数値を示しはじめた。
ロシア兵たちは、貯蔵室の他の部屋で起きていることを必死に隠そうとしたが、私たちには筒抜けだった。隣の部屋は、重傷度や治療緊急度に応じた傷病者の振り分けを行うトリアージセクションだった。トリアージセクションで働く医師の役目は、負傷者の状態を安定させること。その後、野戦病院に搬送するのだ。私は、重症者や死にゆく人々の声をいまも思い出してしまう。彼らがもがき苦しむ声が頭から離れないのだ。他の兵士たちは、意識と無意識の間を行き来しながら支離滅裂なことをつぶやいていた。モルヒネは、痛みを部分的に和らげることしかできないようだ。

絶望との戦い——英国ケンブリッジの学校に通っていたアントニオさんは、両親がロシア軍の捕虜になったことを知り、すぐに行動を起こす。両親を救い出すため、必死になって関係者と連絡を取った。(COURTESY OF REUBEN F. JOHNSON)
次の瞬間、誰かが何かに梱包用のテープを巻きつける音がした。私は、このテープの用途を知っている。兵士の遺体を収納袋に入れる時、遺体の足首を束ねるのにテープを巻くのだ。何ておぞましい音なんだ、と私はひとりごちた。クレムリンの狂気によってまたひとりの命が失われてしまった。
動き始めた救出作戦
拘束中も空爆は毎日のように続いていた。ウクライナ軍は、常に近くでロシア軍と戦っていたのだ。ウクライナ軍は移動と短期間射撃を繰り返す「シュート・アンド・スクート」という戦法で空港を攻撃していたため、ロシア軍が滑走路を修復することは不可能だった。近くで爆発が起きるたび、建物がぐらりと揺れた。真夜中でさえ、ミサイルや追撃砲で攻撃されることもあった。爆発に加えて小銃の音が聞こえるたび、私たちの真上で戦闘が起きているのではないかと不安になった。
ある日、AK-47を抱えて隅に座っていた監視役のロシア兵のもとを別の兵士が訪れ、取引のようなものが行われた。その後、その別の兵士が監視業務についた。その兵士は、戦闘用の防弾チョッキを持って私たちの部屋に入った。建物がウクライナ軍に制圧されるのは時間の問題だった。ロシア軍は、私たちが拘束されている部屋の外で行われるかもしれない最後の銃撃戦の準備に取り掛かった。
ロシア兵たちは、私たちの解放に向けて政府間の交渉が行われていることを知っていたのだろう。それでも彼らは、そんなことは一言も口にしなかった。唯一、私たちのもとを2回だけ訪れたひとりの将校が「ここからの移送を手配中です」と教えてくれたが、事実を話すことを上官から禁じられたのか、二度と彼に会うことはなかった。
ロシア軍の中で私が唯一敬意を抱いたのがトリアージセクションの医師だった。私の治療にあたってくれたのもこの医師だ。知的で誠実で、まともな会話を交わすことができる貴重な相手だった。彼のような人が私たちをこれほど苦しめた軍隊の一員だなんて、半ば信じがたい話だ。
会話を重ねるにつれて、その医師も私と同じ航空史マニアであることがわかった。私たちは、もう博物館でしかお目にかかれないような古い飛行機について延々と語り合った。見たところ医師はまだ28歳くらいだったが、有能で優秀な医師だった。この軍隊にはもったいないくらいだ。
その後の医師の消息は知らない。知っているのは、私たちがホストメリの空港から移送された数日後にウクライナ軍が大々的な攻撃を行い、ロシア軍をせん滅させたことだけだ。この医師もまた、狂気じみた戦争の犠牲者になってしまったのではないかと思うと心が痛む。
私たちが拘束されてから8日がたっていた。その日、首都ワシントン在住の私のウクライナ人の友人からアントニオに連絡があった。友人と私は、キーウで出会った仕事仲間だ。友人は米軍の高官やウクライナと関係のある退役軍人の通訳およびアナリストとして活躍しており、国防総省とも独自のコネクションを持っていた。友人は、解決策があることをアントニオに伝えた。すでにこの件に取り組んでいた国務省の関係者やショプナー少将とも話をしていたのだ。これを機に、救出作戦が動きはじめた。
当時の私たちは何も知らなかったが、実際は多くの人が私たちを救出するために動いてくれていたのだ。
ショプナー少将と妻のマーサ、そしてフロリダ州ボカラトン在住の親友のトッドとレナ・マーケルがトーマス・ガイテンスなどの有力者と連絡を取ってくれた。実業家として成功を収めたガイテンスは、茶会党(訳注:オバマ政権の”大きな政府”路線に反対する保守派の草の根運動)の創設者のひとりだ。ガイテンスはこの件をマルコ・ルビオ上院議員の耳に入れ、トッドのきょうだいのシンディーはテッド・クルーズ上院議員の事務所に連絡した。
その他の友人たちも独自のルートを使って力になってくれた。双胴船のチャーターサービスとクルーズ旅行を展開する会社(レナの勤め先)を営むチャーリー・マウントは、友人のもとを訪れた。チャーリーの友人が誰かに連絡を取ってくれたおかげで——その人の正体は、チャーリー本人しか知らない——チャーリーは「何かが動きはじめる。具体的なことは言えないけど、ここから何かが起きる」と携帯電話を置いて言ったそうだ。
脱出、息子との再会
2日後、見慣れないふたりのロシア兵が私たちの部屋に入り、移動を命じた。私たちはまた目隠しをされ、10日ぶりに地上に出た。空港から別の場所に移送されることになっていたようだが、思わぬ出来事によってこの計画は頓挫してしまった。
私たちを移送するトラックに向かう途中、空港がウクライナ軍の追撃砲によって攻撃された。私たちを連れていたロシア兵は一目散に逃げ出し、私と妻は目隠しされたまま激しい空爆にさらされた。振り返ってみると、あそこで死ななかったのは奇跡としか言いようがない。どのようにして空爆から身を守っていたかは覚えていないが、空爆が止むとトラックの中に押し込まれた。車内には、寄せ集めのガラクタの山に紛れて私たちのキャリーバッグがふたつあった。
私たちは近くの町に連れて行かれ、ロシア軍が指揮所として使っていた小さな建物の中に入れられた。なかに入ると、第2次世界大戦のナチスの強制収容所を舞台にした映画に出てくるようなシャワーヘッドのないシャワールームに案内された。シャワーが終わると、量は少ないが温かい食事を与えられた。温かい食事は2週間ぶりだ。食事が終わると、ベッドがないので冷たいパイプ椅子に座って寝るようにと指示された。
3月15日——翌朝、私たちはまた車に乗せられた。車は数時間かけて北上し、チョルノービリ(チェルノブイリ)の被爆地域を迂回するように走った。道路には、私たちのカムリのように穴だらけの車の破片が散らばっていた。燃えた装甲車両や延々と続く爆撃の跡、大型車両によって破壊された道路の穴などが目に入る。ウクライナのインフラの復旧と復興には、この先何十年という歳月がかかるだろう。
さらに数時間が過ぎ、私たちは突然何もない場所で車から降りるようにと運転手に言われた。運転手は私たちにパスポートを手渡すと、「いま走ってきた道を戻るとウクライナ、この道をまっすぐ行くとベラルーシだ」と言ってベラルーシの方を指した。「ぐずぐずしてないで、歩いたほうがいい」と運転手が言う。遥か向こうには、人気のない野原と森しか見えない。時刻は午後5時。あと2時間で日没だ。私たちは歩きはじめた。
それからしばらくして、私たちはようやくベラルーシ国境の検問所にたどり着いた。自分たちはウクライナからの難民だと説明する。移民局や税関、保安担当者らの質問が終わると、私たちはようやく国境を越えることができた。ベラルーシでは、人生でもっとも感動的な瞬間が待ち受けていた。赤十字社の職員のタブレット端末を借り、メッセージアプリを介してアントニオに無事を知らせることができたのだ。ようやく愛する息子の声が聞けて、私は本当に幸せだった。
翌日は夜行列車でポーランド国境に近いブレストという街に移動した。ようやく悪夢のような日々が終わったのだ。それから数時間後、私たちはポーランドの首都ワルシャワにいた。まずはイリーナが先に飛行機でアメリカに向かい、数日後に私も後を追った。イースターで学校が休みになると、アントニオがロンドンからアメリカに飛んできてくれた。こうして私たちは、待ちに待った再会を果たした。
「パパ、お帰り」。アントニオが言った。感動で震えながら、私は息子を抱きしめた。「パパは帰ってくる。僕はずっとそう信じて待っていたよ」
from Rolling Stone US


















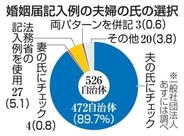













![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)









