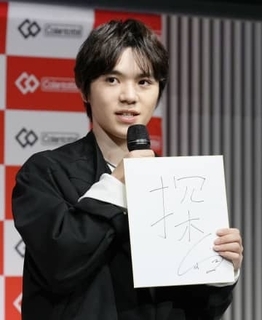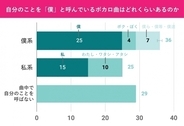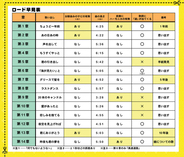現実は今日も続いているという厳粛な事実
──コロナ禍の真っ只中にアルバムを出すのはたまたまだったんですか。
吉野:たまたまですね。去年からずっと決まっていたスケジュール通りです。
──政府の緊急事態宣言が発令される6日前ですね。
吉野:録りながら「なんかおかしなことになってきたぞ」と思っていたら不要不急の外出は控えてくれってことになったけど、俺たちには用があるから外出するしかないよなって。ただ電車には乗らないようにしたし、車で乗り合わせてスタジオに行ったりしました。エンジニアの前田(洋祐)さんも自転車でスタジオまで通ってたし。録音はブースが分かれてるし、基本的にそんなに触れ合うことはないじゃないですか。
──この状況下ゆえに歌詞を変更したとか、そういったことは?
吉野:なかったですね。もう全部出来上がっていました。
──影響を受けていないにせよ、たとえば「今日も続いてゆく」の《俺たちの現実は今日も続いている/人間の毎日は今日も続いてゆく》という力強い歌詞はコロナ禍の状況だろうが何だろうがドッコイ生き抜いてやるという決意の表れのようにも聴こえますね。結果的にですけど。
吉野:現実というのはいつでも続いているものですからね。何がどうなっても現実ですから、それが今日も続いている厳粛な事実なんです。
──それが本作のテーマなのかなと思って。
吉野:あまりテーマというものを考えて作ったわけでもなくて、なるべく引き算、引き算で残った軸みたいなものだけで構築されたものを作りたかったんです。
──以前、吉野さんがツイッターでBAD BRAINSのレコードを取り上げて「俺にとっては曲順から曲間の間合いまで全部で〈1曲〉なのです」と書かれていましたが、今回の『2020』はまさにそんなアルバムだと思うんです。様々な表情を湛えた10曲が結晶化して一人の人間が悪戦苦闘しながら生きる画が浮かび上がるというか。
吉野:そういうコンセプト立てみたいなことは特に考えずに作りましたけど、アルバムはいつも1曲目からの流れとか曲の配置というのをよく考えますね。
──今回も頭から曲順通りに録ったんですか。
吉野:そうです。曲作りもそうですね。1曲目から順番に作って、順番に録っていきました。
──曲作りから録音までの進行は順調でした?
吉野:いやあ、もう身体が壊れるくらいに追い込まれてボロボロでしたよ。録音が終わって足腰が立たなくなったし、4kgくらい体重が減りましたから。タモまで体調を崩しちゃったし。
──とはいえ、制作はいつも難産といえば難産じゃないですか。
吉野:今回は最悪だったですね。才能もなければ引き出しもない、何もないところから無理やり作るので、もうどうしていいのやらという感じでした。
──吉野さんは曲をストックするタイプではないですよね?
吉野:溜めておいてもすぐに色褪せるんですよ。「これはいい歌詞のフレーズだな」と思って温めておこうとメモしても、いざ取り出してきたところでその時の盛り上がりとは違う白々しい感じに聴こえて、だいたいは使えないんです。
──田森さんはいつも新曲を覚えるのに必死だとアルバム発表のたびにおっしゃっていますよね。
吉野:今回も難航したですね、なかなか曲を覚えられなくて。少し拍子をずらして複雑に作ったりする箇所があると、頭がごちゃごちゃになって叩けなくなるんです。アルバムが出来上がって覚えちゃえば叩けるんですよ。ここでまた一個形が出来上がったので、この先はしばらく大丈夫だと思いますけど。
──旧知の盟友・川口潤監督によるMVを作ったくらいですし、1曲目の「今日も続いていく」が本作のリードチューンという位置づけですか。
吉野:まあ1曲目ですし、今回のアルバムを表すには一番わかりやすいかなと思って。
──わかりやすいしパンチがありますよね。バーン! バン! バーン!と放射されるアンサンブルがまさに生きる実感の塊のようで。
吉野:バーン! ジャーン!と明るいものにしたかったんです。全曲通して、内向きになって暗くならないようにしたかったんですよ。もともとワン、ツー、スリー、フォー、ジャーン!で始まったバンドだし、ヘンに内向的になって難しくなりたくなかったんです。というのも、この先アルバムを作る機会もそうはないと思っているんです。今回はそれくらい自分を追い込んで作ったし、追い込んでみてわかったのは、もはやこういう作業はこれからそう何度もできんだろうということで。バンドは一人じゃできないし、俺がやるやるって言っても他の人たちとの関わり合いの中でやれるものですから。だからもしこれが最後のアルバムになったとしたらどういうものにしたいかと考えて、暗くてジメッとしたものはイヤだし、内向きで難しくなるのもイヤだし、やっぱりバーン! ジャーン! ドカーン!で行きたかったんですよ。
雑踏に紛れているのが社会との接点
──2曲目の「存在」は明るい曲調ながら世間から十把一絡げにされるのを明確に拒否する歌で、前作の「同調回路」にも通ずるテーマを軽やかながら毅然と唄い上げているようにも感じましたが。
吉野:普段から感じていることを歌にしたまでです。個人というものが雑に扱われ、存在というものがぞんざいに扱われるようになって、それが露骨になってきたのを近年強く感じるんですよ。弱肉強食が常識化して、弱い奴から順に死んでいけ、強い奴が優先的に生き残ることの何が悪い? みたいな風潮が強まるにつれ、個の存在についてより深く考えるようになったんです。存在を取り戻さなきゃいけないし、取り戻してやり返すんだって気持ちが強いんですよ。そうたやすく力を持ってる奴らの思うようにされてたまるか、そんなことのために俺は生まれてきたわけじゃないんだ、っていう。
──中盤でモノラルっぽい音質になって、アコギとハーモニカと共にサビを唄う部分が絶妙なアクセントになっていますね。
吉野:あそこだけあんなふうに録ってみたんです。マイク一本で。
──「カゲロウノマチ」はこれぞ正調イースタンユース節というか従来のリードチューン的というか、サンダルのゴム底が焼けた道路に溶けてくっつくような今の酷暑の季節を切り取ったような曲ですね。
吉野:真夏のギラギラ感、イヤになるくらいギラギラした感じ。そういうイメージで書いた曲ですね。
──「雑踏に紛れて消えて」は「街頭に舞い散る枯葉」の弟分みたいな曲だと感じましたが、〈雑踏〉はイースタンユースの歌詞の頻出単語ですよね。雑踏は吉野さんに曲作りのインスピレーションを与えてくれるものですか。
吉野:そうですね。雑踏の中で生きているという自覚みたいなものもありますし、雑踏に紛れていたいという気持ちもあります。それが俺にとって社会との接点というか。友達はあまりいませんけど、人はいるわけですよね。駅前とかに行くといろんな人たちがいて、俺もその中の一人で、その中に身を潜めることによって世の中を感じるっていう。
──有象無象の人間がごった返す雑踏の中で孤独を感じたりは?
吉野:しますね。雑踏の中の孤独は強く感じます。山の中で一人きりの孤独っていうんじゃなくて、こんなに人間がいっぱいいるのに誰一人として接点がない。接点がないまま、雑踏の中にいることによって接点を保っているみたいな。そういうことを感じますけどね。
──「夜を歩く」、「それぞれの迷路」とミッドテンポでメロディアスな曲が続くのが中盤の聴かせ所ですが、雑踏の中をそぞろに歩く道が迷路につながるイメージですか。
吉野:あまりそういうことは考えてないですけど、みんな迷路の中ですよね。それぞれがそれぞれの迷路の中を生きていく。出会いたい人には出会えないし、人がこんなにいるのに出会いたい人が一人もいない。これだけいっぱいの人とすれ違っているのに誰ともすれ違っていない。みんな迷って明後日の方向に歩いていっちゃう。そういうニュアンスはあると思います。
──「それぞれの迷路」に《暗い通路抜けて 嫌いな通り避けて/坂道の先にある 海の方へ》という歌詞がありますが、イースタンユースの歌に〈海〉という言葉が出てくるのが珍しいなと思って。既発曲でいえば「裸足で行かざるを得ない」の《夢は海の底に沈み行く》くらいしか思い浮かびませんし。
吉野:特定の景色を想定したわけでもないし、〈海〉が何かを象徴しているわけでもないんです。ただ、迷路みたいな所を歩いていると突然ワーッと視界が広がることがあるんですよ。海がその一番顕著なものだと思ってるんです。俺は海のない所で育ったので、海を初めて見た日のことを覚えてるくらいなんです。ずっと山間の道を歩いていると突然現れるような、それまでチラッチラッと見えていたものが突如としてワーッと目の前に飛び出してくるような感覚。ああ、抜けたなあ…っていうか。そういうイメージが海にはあるんです。
──北海道は地形的にそういう所が多いですよね。積丹でも留萌でも、坂道をくだると突然海が現れたりしますし。
吉野:そうそう、イメージ的にはそんな感じです。北海道に限らず、鎌倉のほうに行っても山間みたいな所を歩いているとワーッと海が出てくるじゃないですか。道がいきなり海になるみたいな。そういうのはいろんな比喩になるのかなと思って。出口なんてないんだと思っていたものがバーッと広がる時もあるし、海は広がっているけど実は行き止まりだったりもするし。その先に舟はないし、茫洋と空漠としているっていうか。
──なるほど。つい口ずさみたくなるような「それぞれの迷路」のサビは旋律が美しく悠然としていて、これぞ吉野さんの曲作りの真骨頂だと感じましたが、メロディを生み出すのは歌詞の推敲よりも煮詰まることが少ないものですか。
吉野:どうなんでしょうね。コードを考えてどうにかこうにかやってますけど。あまりに必死だったので、一個一個の細いことは忘れましたよ。さっきも話した通り、もう死ぬんじゃないかと思うくらい過去最悪に追い込まれたので。
──ちょっと話が逸れますが、アルバム制作中にずっとヒゲを伸ばしていたのは願掛けみたいなものがあったんですか。
吉野:いや、失業者といえばヒゲでしょう(笑)。録音も無事終わって晴れて失業者になったので、そのアピールです。一種のコスプレっていうか(笑)。
──MVもヒゲを剃らずでしたよね。
吉野:このマスクを取ると今もヒゲですよ。絶賛ヒゲ継続中です。ナショナルのヒゲバリカンを買って、伸びると刈ってます。1週間もするとすぐボーボーになるので。一度定着すると、ヒゲがないとなんとなく収まりが悪くなってしまって。「この帽子、ヒゲがないと似合わんなあ」みたいな(笑)。
──当初は痒かったり、食べ物がヒゲにまとわりついて気持ち悪いとおっしゃっていましたよね。
吉野:そうなんですよ。でも慣れると、ヒゲを伸ばしてる人はヒゲに愛着があるんだなというのがわかりました(笑)。今のところ飽きるまで伸ばすつもりですけど。
出会いをあきらめていないから合図を送り続ける
──「明日の墓場をなんで知ろ」は従来の単孤無頼を貫く歌の系譜に連なるものだと思いますが、このタイトルは北原白秋の「あかい夕日に」の一節から引用したものですよね?
吉野:そうです。パクりました(笑)。
──「あかい夕日に」は働きもせずに昼から酒を飲む自分を《どうせわたしはなまけもの》と嘲笑う詩だったと思いますが、どこか吉野さんの生活と重なるようにも思えますね。
吉野:俺の人生なんてずっと失業中みたいなものですから。そこをどうにかこうにか、ライブをやったり音源を作ったりすると心優しい人たちがお金を払ってくれるので、その善意で今日まで生き延びてこれましたけど、ちゃんと働いたことはないですからね。日雇い労働しかしたことないですし、全然使いものにならんのです。ずっと綱渡りで生きてきたし、北原白秋の詩の通り〈なまけもの〉なんですよ。
──何ものにも縛られず、寄りかかることもなく自由に生きてきたからこそ、コロナ禍でライブができずに無収入になるのは仕方のないことだと腹を括っているところもありますか。
吉野:個人的にはそう思ってますね。ライブがやれないのはコロナの影響をもろに受けてますけど、自分が危機に陥るのは何もそれに限ったことじゃないですから。バンドが解散してしまえば即座に収入は絶たれるし、ライブができるなら一人で日銭を稼ぐこともできるかもしれないけど、それだってみんなに愛想を尽かされちゃったらゼロですよ。いつでもすぐ無収入になってしまう危機の中で生きてきたし、それを選んで生きてきたので、すべてがゼロになってしまう日が来たら来たで仕方ないとは思っています。
──でも、どれだけ追い詰められた現状であれ何ひとつあきらめないのが吉野さんのスタンスですよね。
吉野:あきらめてはいませんね。まだまだあの手この手で生き延びてやるぞと思ってます。
──震災後の自粛ムードもそうでしたけど、まずは衣食住が最優先で音楽が必要とされるのは一番最後という風潮がありましたよね。今回もそれと同じで致し方ないという認識ですか。
吉野:必要ない人には必要ないんでしょうね。ライブハウスなんかなくなったって痛くも痒くもないと言ってる人を見かけたりしますけど、そうでしょうよ、お前にとってはな、と思うだけです。ただ、お前とは友達にはなれん、とは思いますけど。
──我々には励みになる言葉です。しっとりとした序盤から一気に熱を帯びたアンサンブルへと加速していく「月に手を伸ばせ」は本作における屈指の名曲だと思いますが、決して届かない月に懸命に手を伸ばそうとするのも何ひとつ現状をあきらめていない姿勢の表れのように思えますね。
吉野:「月に手を伸ばせ」っていうのはあれですよ、「月に手を伸ばせ、たとえ届かなくても」っていうジョー・ストラマーの名言のパクりですよ。
──そんなあっさりと種明かしを(笑)。
吉野:わかる人にはすぐわかりますから。でもさすがいいこと言うなあと思って。自分がその曲で言いたかったことと言葉の言い回しがぴったり合ったので、勝手にパクらせてもらいました。
──力漲るサビの歌詞とは対照的にセンチメンタルな平歌や中盤の歌詞がとてもいいんですよね。《君に会えそうで会えない帰り道》という、そこだけ抜き出したらラブソングの一節にも聴こえる歌詞も真新しいですし。
吉野:出会いをあきらめてるわけじゃないんですよ。出会いたいんですよ、いろんな人に。〈君〉というのは男でも女でも誰でもいいんですけど、面白い出会いをあきらめてないんです。だけど新たなに出会ったり知り合ったりする機会がいよいよなくなってきたんですよ。それはコロナの影響というよりも、人とあまり接しない俺の生き方がそうさせるのかもしれませんけど。会社に行くわけでもないですし、友達と誘い合ってワイワイやることもないですから。そもそも友達もあまりいないので。でも、面白い出会いって嬉しいものじゃないですか。だからあきらめてはいないんだけど、空振りなんですよ、毎日。一人で出歩いて、結局は一人で帰ってくる。それをしみじみと噛み締めているわけですよ。
──面白い出会いを求めて『極東最前線』をやり続けてきたところもありますよね。
吉野:そうですね。それが縁になって長々と付き合いが始まるってこともないんですけど。それも自分から深入りできない俺の性格上の問題なのかなと思ってますね。
──吉野さんのほうにここから先は深入りしないでほしいという部分があったりは?
吉野:どうなんですかねえ。そんなに構えて人と付き合ったりはしてないんですけど。まあ、みんな大人になればなるほど各々事情がありますから。若い頃みたいなつるみ方はもうできませんしね。
──「合図を送る」は吉野さんの静と動を対比させたギターワークが冴え渡っていて、何より中盤以降の火を吹くようなギターソロが絶品ですね。この曲に限らず、本作はどの曲も情感溢れる音色が素晴らしいですが、「合図を送る」は特にそれを感じます。
吉野:静けさから始まって、あるところからギターがバーン! スパーン!と炸裂してまたふっとなくなるような曲を作りたかったんですよ。音に関しては一曲ごとにとにかく今やっておきたいこと、「こういう感じなんだよ」というイメージを詰め込んだっていうか。エンジニアの前田さんと2人でああでもないこうでもないと音作りをしました。「こうやってみたらどうですか?」「うーん、ちょっと違うっすねえ」「じゃあこんな感じは?」「ああ、いい感じっすね!」みたいな感じで一個一個作っていったので、狙いというよりもこつこつと積み重ねていった結果が音に表れているんじゃないですかね。今回はあまりに必死すぎて覚えてないことが多いんですよ(笑)。
──「合図を送る」というタイトルや歌詞を読んで、bedside yoshinoの「念力通信」という曲を個人的に連想したのですが、思いの丈はSNSやネットを使わずに合図を送ったり念力で伝えるというのが吉野さんらしいと思ったんですよね。
吉野:世の中に気の合う人って本当にいるのかな? って思うんです。俺の場合、気に食わない人がほとんどなんですけど(笑)、それでもどこかにちゃんと話ができる人がいるはずだと思ってるんです。だから合図を送り続けたいんですよ。ボヤーっとして見えないんです、その人たちは。だけど合図を送り続けていればどこかで出会えるかもしれないなと思って。
危機一髪の状況は今に始まったことじゃない
──最後の「あちらこちらイノチガケ」で唄われていることも、今後アルバムを制作する機会が少なくなっていくかもしれない中でとりわけ言い残しておきたいことを歌詞にしたということですか。
吉野:というよりも、いつだって命懸けなんですよ。今までもそうだったし、これからもそうなだけっていうか。人生は一回きりだし、元手は命しかないし、張れるのは命しかない。才能も能力も何もないけれど、命だけはある。それで生きていくしかないんです。自分の思ったようにはなかなかなりませんけど、自分の力で思った方向に行くには自分の命を張っていくしかない。誰も責任を取ってくれないし、そう易々とお膳立てはしてくれませんよね。だけどお膳立てされたものに自分らしさみたいなものはないと思ってるし、自分の力で掴み取るしかないじゃないですか。
──直に掴み取れ、ですね。これまで吉野さんが唄い続けてきたことを現況に反映させたようにも思えます。
吉野:唄いたいテーマみたいなものがそんなに多くあるわけじゃないですからね。どの曲も結果的にこうなりましたとしか言いようがないんですけど。
──アルバムタイトルは『2020』しかないと当初から決めていたんですか。
吉野:録音しながら、ですね。だんだん世の中がおかしなことになってきて、歌を作って録音している今の状況を一発で表現できるのは『2020』しかないと思ったし、それしか思い浮かばなかったんですよ。
──後年、2020年の盛夏を振り返った時に今回のアルバムの真っ赤なジャケットと「カゲロウノマチ」を思い出しそうな気がすでにしています。
吉野:2020年、俺は生きていましたよ、ってことですよね。〈2020年〉はもう歴史上の記号だと思うんですよ。人類の歴史に残る記号。だからアルバムのタイトルに付けてもいいなと思って。
──ジャケットに道路の写真を使ったのは、吉野さんがいつもヘトヘトになるまで歩き倒していることと関係がありますか。
吉野:あるかもしれませんね。ジャケットは日常とつながっている場所というか、日常の風景にしたかったんです。写真はウチの近所の環八ですし。
──こうして話を伺ってきて、吉野さんがコロナごときで何ひとつあきらめないのは強さというよりも必然であること、人類の歴史に残る年に発表された『2020』というアルバムが現況を吹き飛ばすように爽快でカラッとした作風に仕上がった理由がよくわかりました。
吉野:綱渡りだったり危機一髪の状況は何も今に始まったことじゃないんですよ。最初からそういう生き方を選んでここまで来たし、ちょっと風が吹けば倒れてしまうような生き方は元からなんです。コロナのお陰でそれを思い知らされることになりましたけど、仮にコロナがなかったとしても俺の人生はやっぱり危機一髪であり続けるんですよ。何か起こればあっという間にゼロだし、コロナ参ったなあ…と途方に暮れてはいますけど、覚悟を決めて生きてきたのでそんなにうろたえてはいませんね。ああ、やっぱり来たか、って感じです。
──これまでもアメリカのツアー中に移動車が高速道路で横転事故を起こしたり、心筋梗塞で倒れて緊急手術を受けたりと九死に一生を得たことが何度かありましたけど、そのたびに吉野さんはドッコイ生き延びて元気な姿を見せてくれましたし、このコロナ禍でもしぶとく図太く、転んでもただでは起きないところをぜひ見せていただきたいものです。
吉野:生きてさえいればまだその先がありますよ。死んでしまえばそこでおしまいですけど、生きているならあきらめる必要もないし、継続して先へ行くだけです。
──そしてライブもまたあきらめていませんよね。東名阪のツアーが晩秋から初冬にかけて行なわれる予定ですが。
吉野:やるつもりですよ。できるかどうかわかりませんけど、やると決めないと進めないので。
──バンドとしては去年の12月14日の新宿ロフトでのライブが今のところ最後なので、かれこれ8カ月もライブをやれていない状況ですよね。
吉野:若い頃からだいたい月一くらいでやってきたし、こんなに長い時間ライブをやれてないのは初めてですね。
──outside yoshinoとしては6月に無観客の有料配信ライブを新代田FEVERで行ないましたけど、バンドとして配信ライブをやることを考えたりはしませんか。
吉野:バンドとしてはどうだろうなあとは思いますけど、いいタイミングがあればやる気はありますね。やってみるかという機会があればやってみようとは思ってますけど、まだそういう機会が訪れていないというか。
──自身の経験として初だった配信ライブを実際にやってみていかがでしたか。
吉野:いつも通りでしたよ。お客さんがいないのでリアクションがなくて寂しかったし、どれだけ唄ってもシーンとするばかりで侘しいなとは思いましたけど。それにスタッフの皆さんはパソコンを見たりカメラを見たりして作業をしているので誰も聴いちゃいないんですけど、いつも練習スタジオでギャーギャー唄ってる時だって誰もいないし誰も聴いちゃいないので、それと一緒だと思えばいいやと思って。
──カメラの向こうにたくさんの人が見ているという実感はなかったですか。
吉野:意識はありましたけど、実感は湧かないですよね。レンズが一個あるだけですから。どうなんだろう? と思いながらやってました。
──従来のライブをやれるのはまだだいぶ先でしょうし、今は配信と人数制限した有観客ライブの二毛作にならざるを得ないですよね。
吉野:これまで通りのライブはこの先まだできないだろうなとは思いますね。なんせまだワクチンも開発されていないし、軽症者のほうが多いから大丈夫なんだとか言う人もいますけど、重症になって亡くなる人も多いし、どんな病気でも重症になれば死ぬんだみたいな言い方をする人もいるけど、そういう付き合い方でいいのかどうかすらまだわからないじゃないですか。だからまだ「これで大丈夫だ」と自分で判断する段階ではないんじゃないかなと俺は思ってますけど。
行けるとこまで行く、やれるだけのことをやる
──当面の食い扶持として、ご自宅の六畳間から生まれるbedside yoshinoの音源制作を10年ぶりに復活させてみるお考えは?
吉野:録音はずっとしてるんですよ。前はMTR(マルチトラックレコーダー)を使ってたんですけど、暇なのでコンピュータで録音するようになりました。もはやコンピュータで録らなきゃダメだと思って、マッキントッシュの中にソフトを入れて録ってますよ。だからアルバムを録り終えた後もずっと曲作りは続いているんです。作っては録っての繰り返しなんですけど、機械のことがよくわからんのですよ。あ、止まった! クルクルクルってなってる! 何だこれ? 再起動しなきゃいけないのか? パンチインはどうすんだ!?みたいな感じで時間がかかって、なかなか前に進めないんです。
──そこまで苦労するのなら、使い慣れたMTRで録ってやろうとはならないんですか。
吉野:最初のうちはそうしてたんですけど、編集能力は圧倒的にコンピュータのほうが高いんですよ。目で見えるのでやりやすいし、すごく優秀なプラグインが廉価で手に入るし、可能性がMTRよりもいっぱいある。当然のことですけどね。これからあの手この手で何とか生きていかなきゃいけないわけですから、コンピュータのスキルみたいなものを少なからず手に入れておかなきゃいかんだろ、っていうか。せっかくの無職で時間だけはいっぱいあるので、いろいろと勉強しながら震える手で作業してますよ(笑)。
──順調にスキルアップを果たせば年内のリリースを期待しても良さそうですか。
吉野:年内に出せるなら出したいと思ってますけどね。
──吉野さんの場合、やむにやまれぬ事情で歌が生まれてしまうといった感じでもなさそうですよね。
吉野:いやあ、もう無理やり作ってます。そうしないとなまけものなので一生出来ませんよね。今までもだいぶ作ってきたので、10時間くらいはライブがやれるストックがあるんですよ。これ以上要りますか? って思ってる上でもっと作るってことですから、もうやらなくていいんじゃないの? ってラインを乗り越えてまた同じことをやろうとするわけで、その乗り越えがけっこう大変なんです。
──今回のアルバムが通算18枚目ということは、シングルやコンピレーションの収録曲、ソロ楽曲まで含めると250曲くらい発表してきたことになりますよね。
吉野:細かいことはもう全部忘れましたよ(笑)。
──ライブで披露されなくなる曲もたくさんあるし、残る曲は精選されていくので、それを補う意味でも新曲は必要だという以上にイースタンユースは常に現在進行形のバンドなので新曲がベストであってほしいという気持ちも個人的にありますけど。
吉野:昔の曲をまた引っ張り出してきてやってみると、意外と良かったりするんですよね。ずっとやってなかった曲、ライブで一度もやらなかった曲をいざやってみると新鮮だったり、ちょっとアレンジを変えてやってみるとグッと気持ちも上がったりして。メンバーが替わったのもあるんでしょうけどね。
──それは去年の9月の野音でも実感しました。17年前に同じ場所で聴いた「歌は夜空に消えてゆく」が格段に良くなって聴こえましたし。
吉野:村岡さんはちゃんとモチベーションを持ってバンドに取り組んでくれてるので、同じ曲でもそれまでとはまた全然違う感じでやれるんですよ。世界観もある人だし、テクニックもあるのでとても新鮮にやれるんです。メンバーが替わるのは良かれ悪しかれの部分がなくはないですけど、それによって曲が更新されていく、ずっと続いて先に進んでいくところはありますよね。前とはまた違う形にはなっていくけど、どんどん変わったっていいんじゃないかと思うし。
──変化を恐れず、イースタンユースはこの先もやれるところまでやっていくということですよね。
吉野:行けるとこまで行く、やれるだけのことをやる。回せるところで回していく。それしかないですよ。不安定なのは宿命みたいなものですけど、〈待てば海路の日和あり〉という言葉もあるし、チャンスはまだあると思う。俺には唄うことしかできないし、生きてることの実感や発露を曲として形にし続けることしかできないけど、それで何とか生き残ってやろうと思ってます。そのためにもまずは宅録の機械をちゃんと覚えるところから始めますよ(笑)。