東西冷戦期、アメリカ本土で24時間、即応待機していた戦闘機F-106「デルタダート」。「究極の迎撃機」ともいわれる機体ですが、アメリカ以外では運用されませんでした。
いまから66年前の1956(昭和31)年12月26日、アメリカのコンベア社(現ロッキード・マーチン)が開発したF-106「デルタダート」が初飛行しました。
F-106は日本ではあまりなじみのない機体です。実際、同機はアメリカ以外で運用されていません。生産数も340機で、同時期に開発され、日本を始めとして世界中で運用された傑作機F-104「スターファイター」の約2600機と比べると、かなり少ないです。このように他国に輸出されることなく終わった戦闘機ながらも、1959年から1988年までの約30年にわたり、アメリカ本土の防空を担い続けた“知られざる名機”でもあります。
そんな、F-106「デルタダート」を筆者(細谷泰正:航空評論家/元AOPA JAPAN理事)は1980年代初頭にアメリカで見てきました。同機の誕生の経緯と、実機に触れた率直な感想について振り返ってみます。
飛行するカリフォルニア州空軍第144戦闘要撃航空団のF-106「デルタダート」戦闘機(細谷泰正撮影)。
そもそも、コンベア社は1950年代に2種類のジェット戦闘機を開発・生産しています。1953(昭和28)年に初飛行したF-102「デルタダガー」と1956(昭和31)年に初飛行したF-106「デルタダート」です。
この2機種は、3年違いで生まれただけでなく、よく似た外観をしているため、まるで「兄弟」といった感じを覚えますが、それもそのはずF-102Aの発展型として計画されたF-102Bが、後に新たな型式を与えられF-106となったからです。
このように2段回に分けて新型機が開発・導入されたことには1948(昭和23)年ごろの国際情勢が色濃く反映しています。米ソ対立に端を発する冷戦下の切迫した状況下、アメリカにとってソ連(現ロシア)の爆撃機から本土を守ることが最重要であり、高性能戦闘機の配備は急務でした。そのために採用したのが2段階の配備計画です。
第1段階として、まず全天候戦闘機F-102A「デルタダガー」の配備を急ぎ、第2段階として地上の警戒・管制システムを含めた総合的な防空システムを構築する。その防空システムと連携する究極の迎撃機としてF-102B、後のF-106「デルタダート」を調達するという計画が立てられました。
最初に造られたF-102Aでは、アメリカ空軍が定めた、ひとつの指針に沿って設計が進められました。まず、火器管制装置の開発を先に進め、その火器管制装置の搭載を前提に機体を設計するという方針です。これに沿って、火器管制装置にはヒューズ社の「MC-3」が採用され、それを搭載する機体としてコンベア社の無尾翼デルタ翼案が採用されます。

アメリカ空軍のF-102A「デルタダガー」戦闘機(画像:アメリカ空軍)
ただ、この機体はF-102Aとして完成したものの、飛行性能は速度、上昇力ともに計画値に届きませんでした。そこで取り入れられたのが、当時発見されて間もない「エリアルール」でした。これは機体の断面積の変化をなだらかにすることで音速突破時の抵抗を小さくするというもの。
そしてF-102Aの生産、配備と並行して、さっそく発展型F-102Bの設計がスタートします。後発のF-102Bは最初からエリアルールを採用し、エンジンは強力なJ75に変更されることになりました。J75エンジンは空気の流量を多くするために形状も大きくなっていたため、胴体の延長、翼面積の拡大、新しい空気取り入れ口など変更点は機体全体に及びました。
ここまで改良を加えると、近似する外観とはいえ、もはや別機といえます。そのため、F-106という新しい型式が付与されたのです。
敵爆撃機の侵入を阻止するには、なるべく早い段階で発見し迎撃機の発進命令を出す必要があります。それと同時に敵機の進路を計算し、最適な迎撃地点を割り出して迎撃機をそこへ誘導することが必要です。全天候下で確実な迎撃を目指したアメリカ空軍では、早期警戒レーダー網、飛行経路の予測、最適要撃地点の算出、戦闘機の誘導に関する全てをコンピューター化した統合システムを構築しました。
本土防空システムの1端末として完成した巨大なシステムは「SAGE」(Semi-automatic ground environment:半自動式防空管制組織)と呼ばれます。F-106「デルタダート」は、いうなればこのシステムの一部として開発されたのです。

ウェポンベイからAIR-2「ジニー」空対空核ロケット弾を発射するF-106「デルタダート」戦闘機(画像:アメリカ空軍)。
なお当時の全天候戦闘機では、パイロットの他にレーダー操作要員を搭乗させた2人乗りも存在しましたが、F-102とF-106はともに1人のパイロットがレーダー操作も行いました。そのため、操縦しながらレーダーの操作を容易に行うために採用されたのが特殊な形状の操縦桿です。両機の操縦桿は上端がU字型の特殊な形状をしています。
U字の左側にはレーダーのセレクターなどのスイッチがあり、右側はオートパイロットなどの操縦系の操作スイッチが取り付けられていて、パイロットは操縦桿から手を放すことなくいろいろな操作を行うことが可能になっていました。これは現代の戦闘機では一般化しているHOTAS(Hands On Throttle And Stick)の概念を先取りしたデザインでした。
敵機を撃墜するためにF-106が装備した主武装は核弾頭搭載のAIR-2「ジニー」ロケット弾です。核爆弾を搭載し編隊を組んで飛来して来るソ連の爆撃機の編隊ごと核弾頭の力で破壊することを目指していました。この「ジニー」核ロケット弾の携行能力は前型のF-102「デルタダガー」にはなかったため、その点を見ても最初からF-106配備までのツナギの存在であったといえるでしょう。なおF-106「デルタダート」では、「ジニー」核ロケット弾以外にもAIM-4「ファルコン」空対空ミサイルの運用が可能でした。
超厳戒態勢下にあった冷戦下のF-106飛行隊ただ、このようにF-106「デルタダート」は当時としては超ハイテクだったため、高コストでした。前型のF-102が当時の価格で1機120万ドル(1ドル360円換算で約4憶3200万円)だったのに対し、F-106は1機330万ドル(同11憶8800万円)と倍以上もしたのです。そのため、アメリカ空軍は当初、F-102とほぼ同数の約1000機調達を目指していたものの、最終的に340機しか調達できませんでした。
なお、同時期にNATO(北大西洋条約機構)諸国が採用した戦闘機F-104「スターファイター」の価格が1機142万ドル(1ドル360円換算で約5憶1120万円)とされていたので、当時の航空自衛隊がF-104を選択したのは機体価格の点からも妥当といえるでしょう。

編隊飛行するカリフォルニア州空軍第144戦闘要撃航空団のF-106「デルタダート」戦闘機(細谷泰正撮影)。
筆者が実機に触れたのは1982(昭和57)年8月のことです。このとき、F-106「デルタダート」を運用していたカリフォルニア州空軍第144戦闘要撃航空団を見学し、写真撮影はAIR-2「ジニー」核ロケット弾と一部の電子機器を除き許可されました。同航空団は民間機も発着するフレスノ空港の一角を基地として使用しています。そのためか、ランプの一部には制限区域が設定されており、自動小銃を持った兵士がアラート待機の機体を警備していました。
周囲を市街地に囲まれた空港の片隅に核兵器を装備したF-106戦闘機が出撃準備を整えて24時間、即応待機していたのです。それが東西冷戦の現実で、筆者は市民生活のすぐ隣に核兵器が共存していることを実感しました。
ロシアによるウクライナ侵攻が長期化しつつある今、ロシアのプーチン大統領は核兵器使用の可能性を何度もほのめかしています。フレスノ市で待機していたF-106「デルタダート」のように、核兵器が一般市民にとって“身近な存在”にならないことを望むばかりです。


















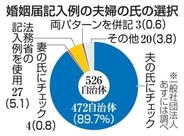













![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








