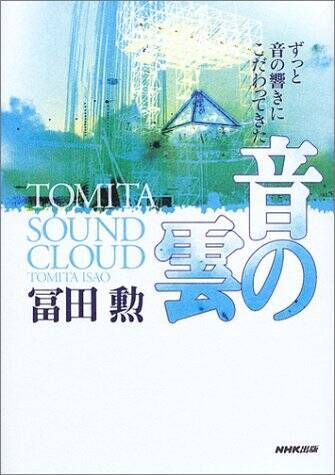
通常のドラマとは違う大河の音楽づくり
ドラマの劇中に流れる音楽を「劇伴」という。たいていのドラマの劇伴は「悲しい曲」や「楽しい曲」など何パターンかつくって使いまわすのが常だ。しかし、NHK大河ドラマは違う。作曲家は、ドラマの演出家から音楽を入れたい箇所をいちいちその時間とともに指定されたうえ――たとえば「この人物が顔を上げた瞬間から相手のセリフが終わる1分4秒間」という具合に――、曲をつけていく。こうなると録音は毎週ある。したがって作曲者はほぼ1年にわたってNHKに拘束されることになる(「SPA!」2001年9月5日号、「フィルハーモニー」前掲号を参照。なお、NHKのドラマでは大河にかぎらず基本的にこの方法がとられているという)。
作曲にあたっては、収録したドラマの映像を演出家と作曲家が一緒に見て打ち合わせしたのち、作曲家はそのビデオを持ち帰って見ながら曲を書くという。だが、冨田が「花の生涯」や「天と地と」を手がけたころにはまだビデオなどというものはなかった。その代わりに、制作側から示された絵コンテによるラフ案などを手がかりに音楽の構想を練ったという。
演奏者が集まらない!――大河第1作「花の生涯」
大河ドラマ(そもそもこの名称はあとになってつけられたもの)はそもそも「映画に匹敵するような大型番組」として企画された。それだけに、その音楽も少なくとも30人は演奏者が必要とされた。しかし当時、内幸町(うちさいわいちょう)にあったNHKの放送会館にはそれだけのオーケストラを収容するスタジオは少なかった。しかもそうした広いスタジオは昼間は公開番組で独占されているので、録音に使えるのは深夜からというのがざらであった。
いまでこそ大河ドラマの音楽はNHK交響曲が演奏している。しかし、それは3作目の「太閤記」(1965年)以降の話で、当初は演奏者をいちいち集めて録音していた。もっとも先に書いたとおり、録音は深夜、遅い場合になると午前2時から始めることもあったため、メンバーはなかなか集まらなかったようだ。演奏者は、昼間の仕事を終えて一旦帰宅してから、終電に乗ってスタジオに駆けつけるか、なかには帰宅するのが時間的に中途半端で、一杯飲み屋かどこかで時間をつぶし、アルコールの入った状態でスタジオに来る人もあったとか。冨田に言わせれば、それでも来てくれるだけましだった。
そんな苦労のなかで録音されたテーマ曲は、その後の大河ドラマの手本となるものだった。作曲家の青島広志は《混沌とした序と鄙(ひな)びた主要部の対比、そして漠とした結尾という構成は、以後多くの用いられた》と同曲を評している(「フィルハーモニー」)。
映像に音楽のイメージが合わない!――大河初のカラー作品「天と地と」
冨田が「花の生涯」の次に大河ドラマを担当したのは6年後、1969年の「天と地と」だった。原作は海音寺潮五郎の同名小説で、越後の戦国武将・上杉謙信の生涯を描いたものだ。
大河ではこの間、音楽をNHK交響楽団が演奏するようになっていたものの、劇伴などN響のやる仕事ではないという意識も強かったらしい。録音するにも練習の合間ならということで、都内の伊皿子(港区三田)のN響の練習場までわざわざミキサーとともに録音機を運んで収録していたという。
しかし、これに冨田は不満を抱く。音響にかなりのこだわりのある彼としては、練習場で録るような音は許せず、「引き受けた以上は仕事としていい音で最大限協力するのはプロのオーケストラとして当然ではないか」と「天と地と」のチーフ・プロデューサーの禅野圭司に訴えたのだ。これを受けて禅野はN響に掛け合い、NHKの渋谷移転にともない新設された509スタジオをN響の練習場として一日明け渡し、そのうち大河ドラマのため2時間を割いて収録をしてもらうようにした。苦肉の策ではあったが、《それ以降大河ドラマの音はよくなったのではないか》と冨田は振り返っている(「フィルハーモニー」)。
「天と地と」では、テーマ音楽を録音し終えてから、「映像に音楽のイメージが合わない」とスタッフ側から言われるというハプニングもあった。冨田としては、台本を読んだりシリーズの内容を聞いたりするだけでなく、この仕事に入る前に出かけた世界一周旅行の途上、越後から日本海、さらにはシベリアあたりまで延々と続く雪雲を見たり、帰国後に実際に越後に赴いた体験から、「雪の降りしきるなか毘沙門天のお堂から上杉謙信の弾く琵琶の音が聞こえてくる」というイメージをふくらませていた。テーマ曲もそれにもとづいてつくったものだ。
だが、編集する前の映像を見せてもらったところ、そこには雲一つない青空に、きらびやかなのぼりや旗や鎧がキラキラと映えていた。聞けば、日本海側ではなく太平洋側の茨城でロケをしたという。
彼としてはいまさら映像のイメージに発想を変えて曲をつくり直すことは無理だった。結局、ディレクターに判断を任せたところ、音楽はそのままに、映像に霧のようなフィルターをかけることになった。これで、色がわからなくなるほどではないが、越後のイメージに近づいたという。
曲の録音中、“ノイズ”が入った!――絢爛たる絵巻「新・平家物語」
大河ドラマ10作目にあたる「新・平家物語」(1972年)では、節目にふさわしく主人公の平清盛役の仲代達矢をはじめ、その脇を緒形拳や北大路欣也ら歴代の大河ドラマの主演者たちが固めるなど豪華キャストが結集した。
絢爛たる絵巻のイメージから、冨田はそのテーマ音楽に和楽器を多く用いることにし、このうち筝を鬼才・桜井英顕が演奏した。その録音の際、桜井は曲の盛り上がっていくところで、天ぷら屋からもらってきた鉄製の箸で筝の弦を乱打し続けた。ところがそれが勢い余って、弦を支える駒がポーンと飛び上がり、カチャカチャカチャと床を転がってピタッと止まる音が入ってしまう。
録音を担当したミキサーは「ノイズが入ったからNGだ」と録り直しを求めたものの、冨田としては、桜井をはじめみんな二度とできないほどのよい演奏をしてくれたし、例の音は結果的にはよい効果になっていると思えた。そこで、「ストラヴィンスキーの作曲した『ペトルーシュカ』では一つの演奏法としてタンバリンを床に落とすところがある。だから、この曲も駒をポーンと弾いて転がすように自分が譜面に書きこむので、この演奏をOKにしてもらえないか」と頼んで、承諾を得たという。
なお「新・平家物語」の放送された1972年、冨田はアメリカからシンセサイザーを個人輸入し、操作マニュアルのないなか試行錯誤しながら音づくり、演奏までマスターする。
脚本家と主演が途中降板!――曲のイメージが揺らいだ「勝海舟」
1974年の「勝海舟」もある意味、大河ドラマ史上特筆すべき作品である。脚本は当初、倉本聰が手がけたものの演出陣との対立から途中降板してしまう。さらに主演も渡哲也が病気になったため第10回から松方弘樹に交代する。
冨田が戸惑ったのは、この主役交代劇だった。劇中音楽をすっかり“渡”海舟のイメージで固めていたため、それが急に代わると主役のテーマ・メロディがそぐわないのだ。だが、《回を重ねて慣れてくると、“松方”海舟も日本を植民地化しようと企む仏人をはぐらかすあたり、なかなかの名演技だと思った》という(「フィルハーモニー」)。松方と海舟のイメージがハマることで、音楽もそれに合わせられるようになったということだろうか。
なお、「勝海舟」は全52話のうちNHKには3話分しかビデオテープが保存されていなかったが、同作で坂本龍馬を演じた藤岡弘、が11話分を個人的に録画しており、最近になってNHKアーカイブスにビデオテープを提供している(「NHKアーカイブス 番組発掘プロジェクト「発掘ニュース」2016年5月20日付)。
冨田自身のルーツともかかわりの深かった「徳川家康」
最後に冨田の携わった大河ドラマは、「勝海舟」から9年後、1983年の「徳川家康」である。大河ドラマの放送開始から20年を迎え、翌年からはしばらく近現代を舞台とする作品が予定されていたため、NHKとしてはこれがある意味、時代劇としての大河の集大成という位置づけであった。そこで音楽にも第1作の作曲者である冨田が起用される。
冨田は作曲にあたって演出の大原誠と家康について語り合った。
冨田には徳川家康に対して特別の思い入れがあった。生まれは東京ながら、父と祖父母は家康と同じ三河・岡崎(愛知県)の出身であり、冨田もまた少年時代の大半をここですごしているからだ。とりわけ祖母は家康に信仰にも近い崇拝をしており、「怒るな怒るなけっして怒るな」という家康の言葉をよく孫たちに言って聞かせたという。また、冨田家の先祖の墓は、家康が幼少期に一時預けられた法蔵寺の境内にあり、そこには幼き家康の書や日用品などが所蔵されていた。それだけに「徳川家康」の仕事の依頼を受けて、冨田はとてもうれしかったようだ。
「徳川家康」の音楽を手がけたとき、冨田は劇伴についてこんなことも語っていた。
《ドラマと音楽とのむすびつきは、ドラマを構成していくためのいろいろな要素の中でもかなり重要な部分でありながら、いちばん極め手のはっきりしにくい不確実な部分であります。したがって、演出者やシナリオライターと音楽についての打合せはしても、だいたいは雲をつかむような話をして終ってしまいます。中にはたいへんこまかい人もいて、まず作曲者に原作を熟読させ、脚本のできているところまでをことこまかに説明し、自分の演出意図を何時間にもわたって論じ、あげくのはてはロケ現場まで、なんていうことがたまにあります。
冨田はビデオもない時代から大河ドラマの音楽を手がけ、映像と音楽が合わないということも「天と地と」と「勝海舟」で経験した。《何の予備知識もなく、いきなり編集済みのビデオを見た時の直感が意外と正解なこともあります》とは、彼が経験の末に導いた理想のあり方ではなかったか。
メロディよりも音の響きに強い関心を抱いていた冨田は、後年にいたって広大な空間を音響で包みこむ「トミタ・サウンドクラウド」という大規模なイベントを世界各地で開催している。音響でつくりあげた劇的な空間は、彼が大河ドラマをはじめ多くの映像作品の音楽を手がけてきた経験の延長線上にあったと見ることもできるのではないか。
(近藤正高)






























