「美女ジャケ」とは演奏者や歌っている歌手とはまったく無関係な美人モデルをジャケットにしたレコードのこと。1950年代のアメリカでは良質な美女ジャケに溢れており、ギリギリセーフなエロ表現で“ジャケ買い”ユーザーを魅了していたという。
■脚フェチも脚フェチじゃない人も、人生には気づかないほうが幸せなこともある
この連載も14回目。当初10回の予定で、10回分テーマ出しして始めたものだから11回目以降は、その都度テーマを考えている。さすがにもう出尽くしたのではないか? と思ってきたが、そうだ! 女性のエロティシズムの最も重要な武器、あれを取り上げてなかったではないか。
脚である。
以前から書いているように美女ジャケというのは、美女の顔のアップがともかく多い。
脚をあまりフェティッシュな視線で撮ると、エロくなってしまうからだろうか。美女ジャケというのは、60年代後半から日本で盛んにリリースされたエロジャケとは違うし、筆者が集めてきた1950年代は、あまりにエロいものは市場に出せなかったという理由もある。
とくにメジャーなレコード会社では、セクシュアルなジャケにもそれなりの「品」を漂わすことが重要視された。ムード音楽のレコードなんて、メインの購買層はサバービア(郊外生活者)の中産階級なのだから。
Capitolレコードの、撮影にも、フォントにも、デザインにもこだわった美女ジャケは、そんな「品のあるセクシュアリティ」を追求した精華といえるだろう。
Capitolレコードの洗練された1枚にジョージ・シアリングの「burnished brass」がある。この連載でもシアリング作品は何枚か取り上げてきたが、ともかく美女ジャケが多い。しかもほとんどがCapitolレコードからのリリースだからゴージャスでセンスが良い。
この「burnished brass」もモデルの素晴らしい美脚以上に、地に敷いたゴールドの布、ラメ入りの深紅のドレスなど、ブラスからイメージされるきらびやかさを見事に表現したアート・ディレクションに唸った。
そしてモデルのロングドレス。
マニアックな話になるが、モデル嬢は、南洋エキゾ・ミュージックの第一人者、マーティン・デニーのほとんどのアルバムのモデルを務めたサンドラ(サンディ)・ワーナー。
連載第2回でサンディがジャケのモデルをしているデニー作品を紹介しているので、ぜひ見て欲しい。デニー作品でも同一モデルとは思えぬほど七変化の彼女だが、こちらもまた別人かのようで、このモデルがサンディと気づいた人は美女ジャケ愛好者でもそう多くはないはずだ。
ともあれこんな太ももに深くスリットが入ったドレスが似合う女性なんて、やはりボディの良い欧米系でしょう。と、筆者の世代では思っていた。
でも、最近はなにか違ってきている。
映画ではなく日常で見る欧米女性は、太り気味の人が多いが、一方、インスタの脚フェチ向け投稿で数万のフォロワーを稼いでいるのは、中国か韓国系の女性。欧米パツキン女性崇拝世代ながらも、何人かアジアの美脚女性をフォローしてしまっている次第です。
同じような深いスリットのドレスを着ているのが、ジュリー・ロンドンの「London by night」。歌っているご本人がモデルで、素晴らしい美女で、しかもとてもハスキーな独特の声。
高校生のときに知って以来のファンで、拙著『Venus on Vinyl 美女ジャケの誘惑』では、彼女のレコードだけで6ページの論考を書いた。もっとも、ずいぶんと大人になってわかったことだが、彼女は美女だが、あまりスタイルが良いほうとは言えない。極端に背が小さいこともある。
若いときは美人というだけで惹かれるし、男というのはドレスから垣間見える太ももだけで欲情する単純な動物だ。だが、ジュリーさんがあるジャケでレオタードのような服でポーズを取っている写真をよーく見ると、どうにもいまひとつなのに気づいてしまった。
それ以来、ドレスのスリットから太ももを出したこのイカしたジャケも、さほどソソらないものになってしまった。
脚を露出させているからといって必ずしもセクシーになるわけではない。ケニー・ドリューの「I LOVE JEROME KERN」は、ジャズ・ファンには人気の高いアルバムで、センスも悪くないが、なぜか惹かれるところが少ない。モデルは半裸だというのに。
品良くまとめすぎているのだろうか? ボーイッシュな短髪も好みが分かれるところだ。そして……足の爪先あたりの組み方というか、この足先のポーズ、これはまったくセクシーではないでしょう!
エロティシズムというのは「繊細な技巧」のことなのだ。ほんの数センチの位置関係が、エロティックか否かを大きく左右してしまうこともある。
そういう点で、このジャケのモデルのポーズは、エロティシズムから遠ざかってしまっているのだ。前掲の拙著では、迷ったすえに掲載しなかったが、そのあたりが理由だった。
似たように膝を屈曲させたポーズを取るジャケにポール・スミスの「By the Fireside」がある。この連載第3回目で一度掲載しているが、再掲をお許し願いたい。
こちらはネグリジェで上半身を隠しているが、よほどエロい。いや、エロ過ぎると言ってもいいだろう。脚の曲げ方なぞは、もうエロの王道ポーズで、いわばこのポーズではこの脚の曲げ具合しかないでしょ! というくらい完璧だ。
エロ顔と美脚で攻めるこのモデルは、さらにミュールを履いているところもポイントが高い。欧米ではふつうに室内履きとして履かれるミュールは、その簡単に脱げ落ちそうなところがエロティックだ。
そう、脚(足)フェチ人種は、女性の足からハイヒールだのミュールだのが脱げ落ちそうなところにひときわ興奮する。
1950年代後半にアメリカで最初の脚フェチ専門誌を創刊したエルマー・バターズは、心底、脚フェチだったので、自ら写真を撮り、編集をこなし、さらに雑誌を刊行するために出版社までつくった。
やがて彼の写真は忘れ去られてしまうが、1990年代に写真集としてまとめられる。そのなかの1枚、“フルファッション・ストッキング”と呼ばれる、うしろにシームが入ったストッキングを穿いたモデルの足から、いまにも落ちそうなハイヒール。これぞバターズの最高傑作であり、足フェチの望む最高のエロティシズムと思ったものだ。
■完璧な脚は“それで終わり”。脚も未完成のものがイイ
と、ここまでで筆者自身がけっこうな脚フェチであることを吐露してしまっているが、ついでに書くと、昔、J-WAVEのフリーペーパーの編集/デザインをやっていたときに、「性格の良い脚、悪い脚」という半ば冗談のような企画を誌面で展開したことがある。
どういうことかというと、完璧な美脚の女性は、なぜかあまり性格が良くない。高飛車だったりする。それに比してちょっと太めくらいの女性のほうが母性が強く家庭的で優しい、ということだ。
もちろんそんな研究も統計資料もあるわけはなく、筆者が長年(と言っても当時、30代前半)の経験と観察と分析によってたどり着いた論だ。ちょっと妄想も入っていたけれど……。
この企画では、飛び抜けた美脚の友人にモデルになってもらって、写真を撮って掲載した。もちろん「性格の悪い脚」として。そのコはとてもワガママだった。付き合ってそれを知ったのだが。
性格を取るか、美脚を取るか、脚の美醜は人の人生を変えるほど重要な問題なのかもしれない。
性格はわからないが、完璧な美脚のジャケがある。こちらもジャズ・ファンに人気の高いデイヴ・ブルーベック・カルテットの「Anything Goes!」。
デイヴ・ブルーベックはすでに一流だったから、セクシーなジャケで売る必要はなかった。だから多作であるにもかかわらず、ほぼ美女ジャケはない。1枚、ハイファッションの超一流モデル、スージー・パーカーを起用したものがあるくらいだ。
だからこの脚ジャケは、ブルーベック作品のなかでは異色なのだが、脚のポーズからフォントの配置まで、完璧なセンスで一級だと思う。そうは思うのだが、どこか面白みがない。調和が取れすぎているのだ。
脚も完璧に美しいのはわかるが、それで終わり。エロティシズムとかセクシュアリティというのは、完璧な調和のなかにあるのではなく、もう少しギザギザした感じとか、瑕疵があるとか、何かが欠けているとか、そういうものの中で醸しだされるような気がする。
よくよく見れば、このモデルの脚の屈曲具合は、前掲のポール・スミスの「By the Fireside」のエロいモデルとそっくりである。真上から俯瞰するか、横から見るか、あるいはボディがあるか、ないか。それだけでもエロティシズムは違ってきてしまうようだ。やはり「繊細な技巧」が醸しだすものなのだろう。
完璧ではない、という点で惹きが強いのが、カル・ジェイダーの「San Francisco Moods」だと思う。カルはラテン・ジャズ系のヴィブラフォン・プレイヤーで音楽性も最高なのだが、ジャケはヘンなのが多い。
これもどう見てもちょっと気が抜けている。まずフォントがダサい。女性の脚も悪くはないが、完璧な美脚とまでいかない。履いている靴、これもダサい。
では、良いところはないのか? というと、そういういまひとつ感が積み重なったところが、なぜか惹くという妙な良さがある。
さらにヌケているのか、セクシーだと思ってやったのか、女性の下着、シュミーズがスカートの内側に見えているのだ。リアルなのか、エロいのか、ダサいのか、なんとも言えない感じがこのジャケの良さである。
たぶんデイヴ・ブルーベックの完璧な美脚よりも、カルのモデルの庶民性のほうが、男性は惹かれるでしょう。リアルなものとして。
とはいえ、リアルでありながらもう少しセンスの良いものはないのか? とも思う。
そうだ、極めつけの脚ジャケ、パット・モランの「this is Pat Moran」があった。
パット・モランは1950年代後半から長く活躍した女性ジャズ・ピアニストで、人気があり評価も高かった。
それにしてもピアノの鍵盤の上にぞんざいに投げ出された脚!
赤いパンプスがアクセントとなった美しいおみ足はモラン本人だろうか? それともモデルだろうか? そのあたりはわからないが、フォントの配置からなにからともかく洗練されている。
あぁ、ピアノを弾こうとして鍵盤に向かったら、突然、真っ赤なパンプスを履いた美しい脚が目の前に投げ出される。もちろん迷うことなくそれに頬ずりするのだ。
そんな夢想をさせるこのジャケット……と夢想する筆者が極度の脚フェチというだけか。いやはや女性の脚というのは魔物である。
と書いてきて気づいたが、今回取り上げたジャケはすべてジャズであった。美女ジャケはムード・ミュージック(イージーリスニング)が圧倒的に多く、ジャズはそう多くない。だからジャズファンは、美女ジャケのジャズ・レコードのオリジナル盤とかには、何万円ものお金を払ったりするのだ。
それにしても、巨乳のジャズ・レコードとかはあまりないが……胸元の谷間を垣間見せる程度のものはあるが……脚を強調したジャズ・レコードが案外多いことも意外である。
女性の美しい脚って、どこか「神聖」さがあって、男はそこに跪拝したくもなる。
そんな心理の根底については哲学者のジョルジュ・バタイユが「足の親指」という論考を書いているが、長くなるので紹介のみで。邦訳も出ている『ドキュマン』という著作に収載されてます。
















![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)
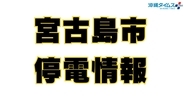











![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






