東京と地方の相互関係が崩れた、いびつな「東京ひとり勝ち」。その延長線上には、東京の中でも「勝ち組」と「負け組」が二極化していく危険性が潜んでいる。
図表1は、国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の推計(2018年値)における2040年の23区別の未来予測結果を、高齢化率と総人口の増加率という2つの軸に基づき整理したものだ。
国連の定義では高齢化率21%以上を「超高齢社会」と呼ぶが、すでに我が国の高齢化はこの物差しでは測れないレベルに達している。そこで、高齢化率25%以上をイエローゾーン、30%以上をレッドゾーンと考えることにした。ちなみに、2015年の我が国全体の高齢化率は26.6%で、すでにイエローゾーンに入っている。
もうひとつの軸とした総人口の増加率は、将来の高齢化の動向を占う指標となる。
上記を踏まえた上で、改めて図表1をご覧いただきたい。圧倒的な「勝ち組」のAグループは都心3区。高齢化率はやや高いが、人口が伸びているBグループと、高齢化率がそれほど高くなく、かつ人口増加傾向も堅調なCグループを含め23区の中心部と下町が、社人研推計による「勝ち組」となる。
一方、人口が減る東部3区のGグループ、高齢化がきわめて深刻化する目黒区以外の西部山の手地区(Fグループ)は「負け組」。人口が伸び悩み、高齢化率がイエローゾーンにある豊島区や中野区などの副都心区も「負け組」予備軍に入る。
ただし、過去から未来を予測する社人研の推計は、「このままだと、どうなりそうか」を示したもので、「どうなろうとしているか」「どうしようとしているか」という「現在」は反映されていない。豊島区や中野区で、戦略的なまちづくりの成果によって、出生率が上昇し子どもが増えていることは、「負け組」からの脱却がすでに進み始めていることの表れである。
同様に、Gグループの東部地区やFグループの西部山の手地区にも逆転の可能性がある。繰り返し述べてきたように、それは30代を中心とした若いファミリー層をいかに惹きつけることができるかにかかっている。
2010年と2015年の『国勢調査』の結果から、23区をサンプルにして65歳以上人口の増加率と高齢化の進展度(5年間の高齢化率の増加数)の関係を見ると、その相関係数は0.01。高齢者が増えても高齢化率が上昇するとは限らない。
筆者が考えるに、逆転具体化の可能性がより高いのはGグループの東部3区。マイナスイメージの払拭には戦略的な取り組みが不可欠だが、都心への交通アクセスの優位性、地価の安さ、古い団地をはじめとする、まち再生のタネの多さなど、ファミリー層を惹きつけ得る条件が整っている。
これに対して、交通の便に難があり、地価も高い西部山の手地区はハードルが高い。だが、逆転の芽はある。
社人研推計で「勝ち組」とされた区も、「負け組」とされた区も、それぞれがその個性を生かした戦略的なまちづくりに取り組めば、東京の活力は維持されていく。しかし、それだけでは東京の悩みは解決しない。各区が努力すればするほど、「東京ひとり勝ち」が進み、東京と地方との正常な関係への改善が遠のくという、皮肉な結果すら招きかねない。
これを回避する唯一の方策は、地方が正当にがんばることしかない。
遅々として進みそうにない地方創生の動きの評価は本稿の対象から逸脱するが、目先の課題に目を奪われ、枝葉ともいうべき方法論に埋没しているようでは、効果は自ずと限定的だ。しかも、その内容が「成功事例に学べ」「隣まちに遅れを取るな」の果てに金太郎飴状態に陥ってしまうと、なおさら期待は薄くなる。
15年ほど前、国も地方もこぞって騒ぎ立てた中心市街地活性化という言葉を、最近トンと耳にしなくなった。その一方で、地方だけでなく大都市の郊外部でも、シャッター通り化はとどまることなく進み続けている。同じ過ちが繰り返されないとは言い切れない。
では、どうすればいいのか。ひとつ問題提起をしたい。
図表2は、47都道府県の出生率ヒストグラム(度数分布図)を東日本と西日本別に示したものだ。「西高東低」の傾向が一目瞭然だろう。
西日本の出生率が高いのは、若い女性が多いから。20~40代前半のいわゆる「結婚・出産適齢期」の性比は、東西日本で真っ二つに分かれている(図表3)。
しかし、これだけではまだ50点。なぜ、西日本は若い女性が多いのだろうか。 17歳までは東西日本で差がなかった性比は、西日本で18歳~20代前半にかけて急減し、20代後半になると動きが収まる(図表4)。
グラフには記していないが、30~40代前半も20代後半と大差なく推移する。その理由は、事実上ひとつしか考えられない。西日本では進学、就職の時期に女性が地元に残る傾向が強いということだ。
以前指摘したように、どこに住むかを男性は実利重視で選び、女性はブランド重視で選ぶ。東日本であれ西日本であれ、実利主義者の男たちは、「より有利な学歴」「より良い就職」を求めて東京に集まる。一方、女性はブランド評価に東西の差が表れてくる。
東日本は東京というナショナルブランドが絶対で、男性と同じように東京を目指す。これに対して「我が故郷こそが誇り」と考える西日本の女性は地元に残る人が多い。ブランド論に違和感があるなら、長い歴史の中で培われ、家庭や学校、地域での生活を通して育まれたベーシックな地域文化の存在が、両者の差の根底にあると言い直してもいい。
観光振興も特産品の開発も祭りやイベントも、いずれも大切なことではある。しかし、地域の本質まで変えることはできない。それは方法論にすぎないからだ。プロ野球の広島東洋カープを応援するカープ女子を思い浮かべたほうが、はるかに実態に近い。カープ女子に、地域を変えるための本質的な要素が潜んでいる。筆者は本気でそう考えている。
「東京ひとり勝ち」の恐ろしい末路東京も地方もがんばったとしても、まだ未来への悩みは残る。人口減少が進む我が国は、どこかが伸びればどこかが縮むという「ゼロサム社会」への道を否応なく進んでいかざるを得ない。世界を見渡すと、処方箋は2つある。出生率を上げるか、移民を増やすかだ。
我が国の出生率が、人口が増えも減りもしないボーダーラインとなる「人口置換水準(おおむね2.1)」を継続して下回るようになるのは1974年のこと。以後、半世紀近くにわたり、有効な手が打たれないまま今日に至っている。
しかし、海外には低出生率を克服した国もある。その代表はフランス。多様な子育て支援策の展開や、社会の仕組みの変革などを同国の出生率回復の要因に挙げる説もあるが、これらもまた枝葉だ。もっとも本質的なことは、今や婚外子が6割にのぼることに象徴されるように、法律婚と事実婚の差を完全に撤廃したことにある。「結婚の概念を変える」という政府が発したメッセージを受け取った若者たちが、「時代が変わる」と共感したからこそ、出生率のV字回復をなし遂げることができた。
筆者は若い人と会うたびに、「なぜ結婚しないのか」「なぜ子どもを産まないのか」と問いかけ続けている。経済的な余裕、保育所不足、イクメンが許されない社会の中での女性の過負担。答えはさまざまだが、共通しているのは未来に対する漠たる不安だ。それは、東京に人が集まり続ける理由とも根を同じくしている。
政府の調査でも賛成が反対を上回る選択的夫婦別姓すら、政治の壁も司法の壁も厚いのが我が国の現状である。同性パートナーに寛容な自治体は徐々に増えつつあるが、事実婚の容認となると途端に腰が引けてしまうという実態もある。この閉塞状態を打ち破るには、政治が強いリーダーシップを発揮するしかない。
「東京ひとり勝ち」が許されないのは、地方が疲弊するからだけではない。やがて、回り回って東京も地盤沈下を始め、その結果として我が国全体が沈没しかねないからだ。Xデーに向けたカウントダウンはすでに始まり出している。もう、時間は残されていない。
(文=池田利道/東京23区研究所所長)


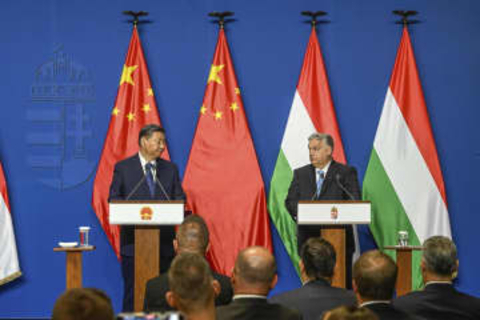










![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)








