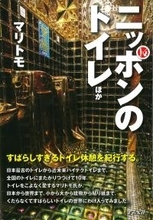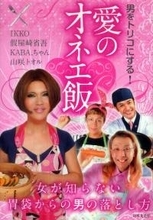そんななか、ちょっと異色の“世界の妖怪”を扱った本をご紹介したい。
その名も『水木しげる 世界の妖怪大百科』(小学館)。これは『小学館入門百科シリーズ版 妖怪「世界編」入門』として1978年に刊行されたもので、自分が子どもの頃は何度も何度もしつこく読み込んだものだった。
そのおどろおどろしい点描の迫力ある絵と、妖怪の解説文ののんきで飄々とした文体が綴る“残酷さ”は、大人になったいま見ても衝撃的である。
一時期絶版になっていたが、2005年に復刻版として蘇り、求めやすくなっているのは嬉しい限りだ。
ところで、「世界の妖怪」として紹介されているものには、おなじみのフランケンシュタイン(スイス)、狼男(イギリス)、ドラキュラ(イギリス)から先住民の精霊などまで幅広くいるが、なかには水木しげるの戦争時代の実体験に基づくものも含まれている。
『ゲゲゲの女房』においても、しげるが南の島に戦争へ行った体験などが語られているが、この本のなかにも、こんな記述がある。
「日本以外に妖怪がいるというのでおどろいたのがニューギニアだ。戦争せずに妖怪のことばかり考えていた。なにしろむこうは妖怪が多い。まあ、妖怪だらけといっても過言ではない。先住民のところに行くと話は妖怪だらけで、もう夕方になると“妖鳥”が鳴き、道は“妖虫”でうまる」
自分にとっての「妖怪」の原体験はというと、まさにこの本だったのだが、「妖怪の住み家」「妖怪の性格」などを読み込んで、自分なりの傾向と対策を立てたこともあった。
「髪の毛が蛇になり、にらまれた人間は石になる=ゴーゴン」を初めて知ったのも、この本だったが、「逃れるには、ゴーゴンのまなざしを鏡で反射させる」といった方法に影響を受け、鏡をしばし持ち歩いた経験もある。
また、夜中にもぼんやり光っている近所の食品工場のあかりを見ては、「ドラキュラの住み家」と思いこみ、夜店で買ってもらった十字架ネックレスをつけて寝ていた日々もあった。
個人的にいちばん怖かったのは、中央アフリカの「アシャンティ」。
「顔や手足がさかさについており、この妖獣に声をかけられたら、なんでもあべこべに答えないと、バラバラにされたうえに魂を食べられてしまう」というのが、心配性の自分にとってはこの上なく恐怖で、あべこべに答える練習をひそかに繰り返したものだった。
とはいえ、世界各国の妖怪たちが陽気に集う「妖怪のドライブ」「妖怪のダンス」「妖怪のマーケット」などの絵は本当に楽しそうで、憧れを感じ、自分も加わりたいとすら思った。
幼少時の自分に、後まで延々と続く恐怖や憧れなどの強烈な印象と感情を刷り込んでくれた「世界の妖怪」たち。いまの大人にも、もちろん子どもにも読んでほしいです。
(田幸和歌子)