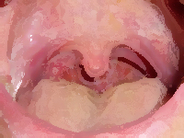秋の行楽シーズンまっただ中。
冬が近づくにつれ、ますます温泉が恋しくなる季節ではないでしょうか。
『蒲団』や『田舎教師』でおなじみの、田山花袋が全国の温泉について書いた、『温泉めぐり』という作品がある。
書き出しの、
<温泉というものはなつかしいものだ。>
という一文。これだけでなんだか、温泉につかった時の開放感とか、情景が浮かんできて、「温泉行きてえなぁ~」という気になってくる。と同時に、作品が出版された大正7年の時点ですでに温泉は「なつかしい」という、郷愁スポット扱いになっていることに驚く。
作品には伊豆や箱根、草津や別府など、全国各地の温泉を訪れた花袋の目を通した印象や感想が綴られているのだが、この花袋の語り口がまたなんというか、いろいろと正直な感じなのが、いちいち楽しい気がする。
<無論設備は、熱海、箱根、修善寺などには及ばない。女中も気がきいていない。料理も旨いという方には行かない。(略)ただすぐれているのは温泉だけである。>
とか、
<草津のあの烈しさ、またあの分量の豊富さ、いかにも温泉はこうなくてはならないような気がする。その熱度の烈しいのも、体にヒリリと来て心地が好い。
とか、
<何方と言えば、陰気である。>
とか、
<一言にして言って見れば、著しくリファインドされた温泉場である。>
とか、
<多少ゴタゴタした嫌いはあるけれども、また設備に田舎臭いところがないではないけれども、海の温泉場としては、其処は日本でも十指の一を屈すべきところであった。>
とか。
もちろん、温泉そのものの描写だけではない。訪れた場所での人とのふれあいや、景勝を絶賛したかと思えば、<評判の女夫岩の小さく平凡なのに失望しないものはなかった>と、今でいう「がっかりスポット」のような描写もあったり、花袋の目を通した当時の各地の温泉地の手触りが伝わってくる。
本を読みながらの全国の温泉めぐり。日本国内ばかりでなく、番外編的に台湾や満州の温泉まで紹介されていて、その行動範囲の広さにもまた驚く。そして終盤近く、別府温泉が登場する。
<しかし何と言っても、温泉は別府だ。>
と、のっけから、言い切りでの絶賛。俗な面もあるとしながらも、
<別府から受けるような感じが、一番温泉場らしい気分と言って然るべきであろう。
<城の崎が好いとか、道後が好いとか、有馬が好いとか言うけれど、足一度此処に入ると、そうした温泉などは何でもなくなってしまう。>
そこまで言われるなら、是非にとも別府に行かなきゃいけないという気分にさせられてしまう。
温泉旅行に出かけるときには、ガイドブックとセットで持って行くと、より温泉が楽しくなります。
目指す温泉が近づいてくる。
<そこに今夜は静かにゆっくり湯に浸って寝ることができると思うほど、旅の興を惹くものはない。>
なんか、ワクワクしてくる。
(太田サトル)
冬が近づくにつれ、ますます温泉が恋しくなる季節ではないでしょうか。
『蒲団』や『田舎教師』でおなじみの、田山花袋が全国の温泉について書いた、『温泉めぐり』という作品がある。
書き出しの、
<温泉というものはなつかしいものだ。>
という一文。これだけでなんだか、温泉につかった時の開放感とか、情景が浮かんできて、「温泉行きてえなぁ~」という気になってくる。と同時に、作品が出版された大正7年の時点ですでに温泉は「なつかしい」という、郷愁スポット扱いになっていることに驚く。
作品には伊豆や箱根、草津や別府など、全国各地の温泉を訪れた花袋の目を通した印象や感想が綴られているのだが、この花袋の語り口がまたなんというか、いろいろと正直な感じなのが、いちいち楽しい気がする。
<無論設備は、熱海、箱根、修善寺などには及ばない。女中も気がきいていない。料理も旨いという方には行かない。(略)ただすぐれているのは温泉だけである。>
とか、
<草津のあの烈しさ、またあの分量の豊富さ、いかにも温泉はこうなくてはならないような気がする。その熱度の烈しいのも、体にヒリリと来て心地が好い。
>
とか、
<何方と言えば、陰気である。>
とか、
<一言にして言って見れば、著しくリファインドされた温泉場である。>
とか、
<多少ゴタゴタした嫌いはあるけれども、また設備に田舎臭いところがないではないけれども、海の温泉場としては、其処は日本でも十指の一を屈すべきところであった。>
とか。
もちろん、温泉そのものの描写だけではない。訪れた場所での人とのふれあいや、景勝を絶賛したかと思えば、<評判の女夫岩の小さく平凡なのに失望しないものはなかった>と、今でいう「がっかりスポット」のような描写もあったり、花袋の目を通した当時の各地の温泉地の手触りが伝わってくる。
本を読みながらの全国の温泉めぐり。日本国内ばかりでなく、番外編的に台湾や満州の温泉まで紹介されていて、その行動範囲の広さにもまた驚く。そして終盤近く、別府温泉が登場する。
<しかし何と言っても、温泉は別府だ。>
と、のっけから、言い切りでの絶賛。俗な面もあるとしながらも、
<別府から受けるような感じが、一番温泉場らしい気分と言って然るべきであろう。
>
<城の崎が好いとか、道後が好いとか、有馬が好いとか言うけれど、足一度此処に入ると、そうした温泉などは何でもなくなってしまう。>
そこまで言われるなら、是非にとも別府に行かなきゃいけないという気分にさせられてしまう。
温泉旅行に出かけるときには、ガイドブックとセットで持って行くと、より温泉が楽しくなります。
目指す温泉が近づいてくる。
<そこに今夜は静かにゆっくり湯に浸って寝ることができると思うほど、旅の興を惹くものはない。>
なんか、ワクワクしてくる。
さあ、温泉へ。
(太田サトル)