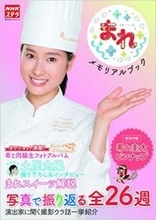今回の展覧会は完全予約制。一日に入場時間を数回に分け、最大で4時間、会場に滞在することができる。実際に行って、これはいいシステムだと思った。人の流れがはっきり見えるのだ。時間が進むにつれ、順路に沿って人の波が移っていくので、特定の場所に人が集中し、ほかの場所は結構空いていたりする。だから自分のペースで観たいという人は、順番に観ていくのではなく、空いているところから観ていくとよいと思う。
ただ、ゆっくり観ていると会場を一通りまわるまでやっぱり2時間ぐらいはどうしてもかかる。とくに全ページの原画が、ガラスケースのなかに何層にも分けて並べられている『AKIRA』はストーリーを追いながら観はじめると大変だ。
宮城県出身である大友克洋が、昨年の震災で被災した人たちのため《私なりの復興支援》として企画した今回の展覧会。申し訳程度にやっては意味がないと、自身の代表作でもっとも長編である『AKIRA』の原画をすべて出すなどして《現在の私自身が最高と思えるものを提示する》ことを目指したという(会場で配布されている「Think the Earth Paper」Vol.10)。
膨大に並べられた原画を観るにあたり、ぼくがもっとも注目したのは「スクリーントーン」だ。そう、絵に網目をかけるときなどに使うアレである。これというのも、むかし雑誌でマンガ家の久住昌之が大友について書いた記事を読んでいたからだ。いまから30年ほど前、久住は大友と一緒に仕事をすることが結構あり、よく仕事場に出入りしていたという。くだんの記事では、原稿執筆中の大友が次のような作業をしていたことが証言されていた。
《スクリーントーンを貼って、それをカッターをペンのように使って削り、その上にもう1枚トーンを貼り、削り、また貼り……という「スクリーントーン三枚削り重ね」は、今までの漫画に見たことのない質感を与えた。
間近で見た大友さんの手先の動きには、ため息が出るようだった》(「PENTHOUSE」1995年1月号)
もちろん、大友以前からスクリーントーンはマンガ家たちのあいだで使われていた。ただ、そのほとんどは画面にアクセントをつけるといった程度の使い方だった。そもそも出始めの頃のスクリーントーンは高価であり、マンガ家はトーンを貼る場所を青鉛筆で指定して、あとから編集者が貼りつけることが多かった。手塚治虫などの原画を観ると、青鉛筆を塗った跡がトーンの下に透けて見えたりする。
だが、そういう跡は大友の原画には一切ない。彼はデビューまもない70年代前半から、トーンを自らの手で貼り、さらに加工することでより画面に効果をもたらしていたのだ。今回の展覧会では初期作品も単行本未収録のものも含めていくつか展示されているが、それでいえば「傷だらけの天使」という連作シリーズでは、夜の街を車が行き交う風景がトーンを削ったり重ね合わせたりして表現されている。
スクリーントーンのテクニックはその後も進化を続ける。雲や海などをさりげなく表現しているのも目を惹くが、何よりも圧巻は『AKIRA』での月の描写だ(単行本第5巻に出てくる)。ペンとスクリーントーンだけで月面のクレーターをここまでリアルに描写できるのかと、ついつい見入ってしまった。
大友の絵はシャープで、無機的にも思えるが、それは職人的ともいうべき手のこんだ作業により生み出されたものだった(いまならパソコンで比較的容易に表現できることなのだろうが)。これは同時代に世界を席巻したYMOの楽曲が、コンピューターでプログラミングしたものではなく、じつはドラムなりベースなりちゃんと楽器を演奏してあの音を出していたというのとどこか似ている。
ちなみに前出の久住昌之は、大友の代表作のひとつ『童夢』の原稿を原寸大で収録した部数限定の豪華版のデザインを手がけていたりもする。日本のマンガは雑誌でも単行本でも原寸より縮小して掲載されるのがほぼ常識で、マンガ家からしてもよっぽど絵に自信がなければ、原寸大で発表しようとは思わないだろう。今回の展覧会で原画を目の当たりにして、単行本の通常版で見る以上の迫力を感じた。とくに超能力を持つ老人と少女が巨大団地の上空で対決するシーンは、観ているこちらまで宙に浮かんでいる気分にさせられる。
本当に絵がうまい人というのは、どんな絵も描けるのだなーと思ったのは、今回初めて観る人も多いであろう『饅頭こわい』というシリーズ。これは「バラエティ」という雑誌で連載されたもので、大友のパロディ趣味がうかがえるユニークな作品だ。そこでは、赤塚不二夫の『天才バカボン』のウナギイヌがリアルに描かれたり(ウナギイヌの両親まで出てくる!)、サイボーグ009や鉄腕アトムの構造がどうなっているのか断面図などで図解されていたり、はたまたつげ義春の作品世界をテーマパーク化した回(タイトルは「パノラマねじ式遊園地」)なんてのまである。完全にお遊びなんだけど、けっして手を抜いていないのがすばらしい。このシリーズが一部を除きいまだに単行本未収録なのは、おそらく版権の問題があるからだろうが、それにしてはあまりに惜しい気がする。
GENGA展のみどころをいまひとつあげるなら、『AKIRA』の原画のなかには、似たようなページがちらほら見つかる。たとえば、作中2度目の東京壊滅のシーンで(単行本では第4巻に登場)キノコ雲が街を覆う様を描いた見開きのページは2点ある。雑誌連載時に描かれたものが、単行本化にあたりべつのものに差し替えられたためだ。どちらが雑誌に載ったのか考えるのも一興かもしれない。
……と、じつにみどころ満載の展覧会で、時間いっぱい楽しむことができる。ただし展覧会場内にはトイレがない。途中で行きたくなって会場の外に出てしまうと再入場できないので要注意。