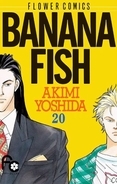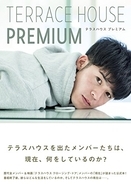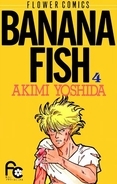漫画の実写化は山ほどあるが、「泣くな、はらちゃん」は、漫画から登場人物が飛び出して実物化するという、ファンタジックなお話。
毎回、漫画(作画ビブオ)が、2次元と3次元の中間のシュールな空間を通って人間として立ち上ってくるアニメーションが挿入される。主演で、はらちゃん役・長瀬智也が、漫画のキャラクターから人間になってギューンッと飛び出てくるところにワクワクさせられた。
はらちゃんの漫画を描いているのは、海辺のかまぼこ工場で働く女性・越前さん(麻生久美子)。彼女はかわいいのに自己評価がやたらと低く、内にこもった性分で、漫画を描くことだけが唯一の楽しみだった。現実世界の鬱憤を漫画の中で晴らしているのだ。
その漫画は、彼女が大ファンだった漫画家・矢東薫子の作品がベースになっている。
越前さんがオリジナル漫画を描いているわけではなく、いわゆる「2次創作」をしているところが実に今日的である。
ある日、漫画から、越前さんのお気に入りキャラクター・はらちゃんが現れる。
はらちゃんは越前さんを、自分たち漫画のキャラを創ってくれた「神様」と崇め、慕いまくる。
漫画の中の世界しか知らないはらちゃんは、見るもの聞くもの何もかもに感動して、まるで純真な子供のよう。
ドラマの序盤は、はらちゃんが、厭世的な越前さんに世界の楽しさを気づかせていく話かと思ったが、そんなイージーなものではなく、回を追うごとに深い話になっていく。
最初のきっかけは中盤、かまぼこ工場の玉田工場長(光石研)がふいに亡くなってしまうこと。
深い悲しみにくれながら越前さんは、漫画ノートに玉田を描いて漫画の世界で彼を蘇らせてしまうのだ。
誰もが抱えるどうしようもない喪失感に、救いの手を差しのべるようなエピソードだった。
以後、はらちゃん以外のキャラクターも人間界に出てくるようになることに伴って、玉田も漫画のキャラクターとして共に出てくる。
出てきた漫画のキャラクターたちは、越前さんだけでなく、他のかまぼこ工場の人々の心の欠けた部分を埋めていく。
越前さんは、はらちゃんの恋する気持ちを受け入れ、「両思いです」と宣言。他者の思いを受け止めることができて、ようやく、越前さんも自分を好きになる一歩を踏み出せたのだ。
はらちゃんの漫画のキャラクター仲間たちも、かまぼこ工場の人たちも、越前さんの家族もみんなチャーミングで(最初の頃の、長瀬智也と、彼のジャニーズの後輩に当たる丸山隆平による、世間知らずと現実派のズレがある会話が軽妙で楽しかった)、このまま、永遠に好きな人たちと楽しく暮らせたらどんなにいいだろう。
……と思わせて、このドラマの神様(創造主)は、登場人物たちを次第に厳しい現実へと向き合わせていく。
漫画のキャラクターたちは、世界は楽しいことばかりではないことを目の当たりにしはじめる。
まずは、自分たちが一度死んでいる、という事実を突きつけられる。
かまぼこ工場の先輩社員・矢口百合子(薬師丸ひろ子)は、実は消えた漫画家・矢東薫子だった。
突然漫画が描けなくなった彼女は、登場人物たちを漫画の中で殺し、漫画家を引退したのだ。
この事実によって、越前さんもまた、一度描きはじめたキャラクターや物語とどう向き合うか問われるが、彼女は、はらちゃんたちを「決して殺さない」と誓う。
面白かったのが、キャラクターのひとりユキ姉(奥貫薫)が、矢東薫子のほうが、たくさん服を着せてくれたし台詞もいっぱい書いてくれた、と越前さんの描く物語に若干の不満を述べるところ。(だって、越前さんの漫画は2次創作だから無理もないよなあ……)
けれど、はらちゃんだけは越前さんを第一に思っていることもちゃんと描かれていて微笑ましかった。
そして、問題はまだまだ続く。
キャラクターたちはテレビで世界で起きている悲劇(戦争、飢餓など)ニュースを見て恐怖を覚える。世界はキラキラと輝いているだけではなかったのだ。
はらちゃん自身、近隣の人たちのいわれない暴力にさらされ、巻き込まれた越前さんを守るため暴力をふるってしまう。
自分の中にあった荒ぶる心に驚くはらちゃん。
再びこの世は悩ましいという現実を立ち戻ってしまった越前さんは、自分自身を漫画に描いて、漫画の世界に入り込んでしまう。
このまま完全にフィクションの世界に閉じこもってしまう生き方を選択しちゃうのか? ってところで9話が終了。
残る10話でどんな決着がつくのか、はらはらします。はらちゃんだけに。
このドラマは、漫画の世界と対比することで、改めて現実を認識させる構造になっている。
漫画をうまく使った作品だが、その反面、漫画や引いてはドラマというフィクションに対する批評にもなっているのだ。
思えば、昔の子供ドラマは、ヒーローや魔法少女など夢の世界のキャラクターは最終回で、去っていくものが多かった。
脚本家の故・市川森一はその代表で、創作者として、大人として、視聴者の子供たちが現実に立ち返らせるような配慮があった。
押井守は、いつまでも夢の世界に留まり続ける人たちを、永遠に文化祭の準備を繰り返している物語(「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」(84)として皮肉った。
けれど、昨今は、例えば人気ドラマは続編が延々と作られ、スピンオフまで生まれ、パラレルワールドにまで発展し、それこそ2次創作が当たり前のようになり、ひとつの作品がいつまでたっても終わることがなく、増殖を繰り返している。
大切な物語は、一度お別れしても、長い年月を経ても忘れることなく記憶に残り続ける。ずっと執着し続けることと、忘れないこととは、別の問題だと思うんだけどなあ……。
もちろん、受け継がないといけないこともあるし、どんな形であれ続けることで、新たに優れた創造につながることもある。
けれど、「泣くな、はらちゃん」は、気に入った物語といつまでも一緒にいたいと願う心に、それでいいのか? と問いかけた久々の作品のような気がするのだ。
「泣くな、はらちゃん」の結末は、現代の物語との向き合い方を示唆する重要な
ものになるのではないか。
脚本家・岡田惠和の選択に期待している。