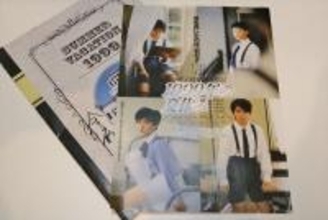清水五条にある、450年以上続く日本一歴史ある飴屋、「みなとや本舗」さんの看板商品、「幽霊子育飴」である。こぢんまりした店内に入ると、なんと商品はこれ1種類だけで、幕末から変わってなさそうなパッケージにもそそられるものが…。第20代目店主という段塚きみ子さんに、「幽霊子育飴」という妖しい名前の由来など伺ってみたところ、話は慶長4年に遡るという!
「その頃、この飴屋はすでにあったんですが、毎日、夜中に一文持って飴を買いにくる女性がいたらしいんですね。当時は、現在のような固形ではなく、棒に巻いた水飴状の飴だったんですけれども。ちょうど7日目の朝、当時の店主が銭函を開けてみたところ、銭ではなくシキミの葉っぱが入っていて。これはおかしいと思って、女性のあとをつけていったところ、鳥辺山にある墓場に帰っていったということです。
そして、その女性が消えた墓の中から泣き声が聞こえたため、僧侶に頼んで墓を掘り返してもらったところ、生後まもない赤ん坊が見つかって。妊娠中に亡くなった女性が、墓場で生んだ子だったんですね。自分はもう亡くなっていて母乳が出ないため、赤ちゃんの命を長らえさせるために幽霊となって、飴を買いにきていたんです」
そして、赤ん坊が発見された後、女性はふっつり姿を見せなくなったという。なお、6日分の銭は、死者が三途の川を渡るためにお棺に入れる六文銭で、それを毎日一文ずつ使っていたが、7日目には底をついてしまった。そこで、昔、京都ではお墓にシキミの葉を供える風習があったため、自分の墓に供えられた葉っぱを持って飴を買いにきていたのでしょう、とのことだった。
なお、実はこの飴、若き日の水木しげる氏が知り合いから京都みやげにもらったところ、墓場で生まれた赤ん坊という伝説にインスピレーションを受け、鬼太郎というキャラクターを生み出すきっかけともなったのだとか。
ちなみに、この赤ん坊はしばらく飴屋さんで育てられていたのだが、やがて成長し、日審聖人という偉いお坊さんになったそうな。そのため、「幽霊子育飴」は妊娠中や子育て中の女性が赤ちゃんの健やかな成長を願って買いにくるほか、「出世飴」とも呼ばれ、仕事での成功を願う人へのおみやげとしても喜ばれているそう。
飴の原料は麦芽糖とザラメ糖のみで、中に鉄を張った特製のたらいで固めた後、のみと金槌でたたき割るのだそう。飴をつくる職人さんは別にいるそうだが、割って袋詰めするという作業は、段塚さんがすべておひとりでされているそうだ。添加物など一切ない素朴で優しい味わいなので、まさに小さい子どもにも安心して与えられるおやつなのである。
さらに、段塚さんの話でダメ押し的にインパクトがあったのが、お店の立地について。「六道の辻」という曲がり角のちょうど前に建っているのだが、なんとこの場所は古来より骸骨の捨て場で、「あの世とこの世の分かれ道」といわれた場所なのだとか。以前はもう少し、山寄りにお店があったそうだがそこが立ち退きになったところ、ちょうどうまい具合にこの場所が空き、あたかも「呼ばれるように」移ることになったのだという。やや背筋が寒くなりつつ、こういうお店がひっそりと残っているところがさすが京都だなあ、と感心した次第…。
また、「幽霊が街中をうろうろするわけにはいかないから」というので今のところ、「幽霊子育飴」は卸売りなどは一切していないそうで、冥界の入り口であるこの場所のみで販売。ゆらゆらと影がゆれる真夏の強い日差しの下、「六道の辻」に立っていると、まるで歴史の裂け目に立っているような不思議な気持ちに。