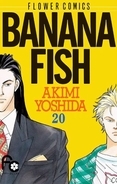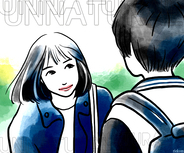こんなふうに書くと、ウォーホルのことが嫌いのように思われそうだが、むしろ好き、いや大好きである。いまから20年ほど前の田舎の高校生にとって、アメリカン・ポップアートの旗手であるウォーホルは、おしゃれカルチャーの象徴的存在だった。当時購読していた講談社の「現代美術」という全集のうち、とくにウォーホルの巻はよく開いて眺めていたし、その数年後、1996年に東京都現代美術館で開催された回顧展にももちろん足を運んだ。
あと、ウォーホルのシルクスクリーン作品を真似して、自分でもプリントごっこを使い(原理はシルクスクリーンと同じなので)、小渕恵三のポートレートをつくったこともある。なぜ小渕恵三だったのかというと、このとき亡くなったばかりだったから。ウォーホルも、女優のマリリン・モンローが死んだ直後にその肖像を制作したりしていたので、手法だけでなくその題材選びにもオマージュを込めたつもりだった(オマージュって便利な言葉!)。
……で、結果からいえば、森美術館で久々にまとめて見たウォーホル作品は新鮮だった。前出の「マリリン・モンロー」のほか、“キング・オブ・ロックンロール”プレスリーの肖像「エルヴィス」、映画女優のエリザベス・テーラーをモデルにした一連の作品のひとつ「シルバー・リズ」、あるいは「花」のシリーズなど、いずれも絶妙な配色に加え、おそらく計算して出したのだろう色のズレもインクのかすれも、抜群のセンスを感じさせる。写真を用いたシルクスクリーン(版画の一種)作品でありながら、そこにはウォーホルの見事な手さばきがありありとうかがえるのだ。
たとえ絵のモデルになった人物を知らなかったとしても、見た者の心をつかむような作品としての強さがウォーホルの絵にはある。そのオーラは、どこか宗教画に似たものがある……とは、言いすぎだろうか。思えば、プレスリーやモンローなどの大スター、1960年代の作品から、その後の「毛沢東」「ドル記号」など、ウォーホルの描いたものには人々の熱狂や信仰の対象であるものが少なくない。
ウォーホルは1963年から68年にかけて、ニューヨークに「シルバー・ファクトリー」というスタジオを開設し、絵画だけでなく映画の制作、また美術関係者のほかさまざまなジャンルのクリエイターを招いては交流している。
今回の展覧会ではこの時代につくられた映画のほか、一つの空間を作品として提示したインスタレーション的作品も展示されている。窓の下に東京の街並みが広がる一室には、「銀の雲」という銀色の風船状のものがいくつも、フワフワと部屋中に浮いている。
「銀の雲」は、金属化プラスチックフィルムにヘリウムガスを充填させたもので、3M社のスコッチパックという製品から着想を得たものだった。「牛の壁紙」には当時まだ一般的ではなかった蛍光色が用いられている。新素材を積極的に作品に採り入れたことは、まさにファクトリーの名にふさわしい。
ウォーホルは1987年に58歳で急逝しているが、もしいまも生きていたら、どんなことをしていただろうか。影武者がいたというウォーホルのことだから、Twitterで別人にアカウントをとらせて、いかにも自分の言いそうなことを投稿させていたかもしれない。
とにかく新しもの好きであったウォーホルは、1950年代から60年代にかけてはテレビにハマり、多いときで同時に4つのテレビと遊んだと自ら語っている。その後、1964年にテープレコーダーを入手してからは、毎日自分のしたことを語って録音したりと常に手放さず、“妻”と呼ぶほどだった。会場には、1980年代にアップル社のマッキントッシュの広告のために制作したシルクスクリーン作品も展示されていたが、長生きしていたら、いまでもアップルの新製品のPRに一役買っていたかもしれない。
今回の展覧会の見どころとしてはまた、ウォーホルが「タイム・カプセル」と名づけたボックスをずらりと並べた一室をあげておきたい。これらボックスには、写真やら雑誌やらチケットやらパンフレットやら土産物やら、彼がその時々で興味を抱いたものが収納されている。
(近藤正高)