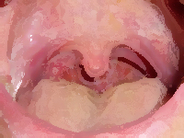“マリエ"という同じ名前を名乗る、2人の女の子を主人公にした斬新なストーリーに、実験的な映像、おしゃれな衣装や音楽のセンスなど、いつ見ても新しく、アートやファッションに敏感な女性たちを中心に絶大な人気を誇るこの作品。1990年代に流行した渋谷系カルチャーの源流のひとつとも言われている。
私も15年くらい前に見て、斬新さに驚いたのだが、正直なところ、深いところまでは理解できていなかった。『ひなぎく』が今も変わらず人気があるのはなぜなのだろうか。配給会社チェスキー・ケーのくまがいマキさんに、この映画に関するお話を伺った。
――まず、60年代に制作された映画『ひなぎく』が、日本で今も多くの人に人気があるのは、なぜだと思われますか?
私が『ひなぎく』を初めて見た80年代は、日本が右肩上がりの時でした。劇場初公開の1991年はバブルがはじける直前、そして、平成不況が始まり、2001年にはツインタワー爆破、ぬれぎぬ的なイラク攻撃、自衛隊派遣と、日本がだんだんキナ臭くなる。ある意味で残念なことですが『ひなぎく』が社会性・政治性の面でも理解されやすくなっているように思います。また、時代とは関係ないことですが、「女の子」には社会的に居場所がないものなんです。母や妻、キャリアを積んだ職業人としての女性には、居場所があります。でも『ひなぎく』の主人公2人のような人間には居場所なんてなく、彼女たちも実はそのことに気付いているし、気付きながら闘い、脅えてもいる。
――では、くまがいさんご自身が思う、この映画の魅力はどんなところでしょうか?
まず、圧倒的にかっこいい映画だと思います。ヴェラ・ヒティロヴァー監督はもちろんですが、共同脚本、美術、衣装を担当したエステル・クルンバホヴァーのセンスはすごい。カメラワークと音楽や効果音の使い方も絶妙で、映像と音の力で75分を突っ走っているところが、みずみずしさを失わない理由なのではないかと思います。そして、主人公の2人の魅力。プロの俳優ではなく、オーディションで選ばれた2人だそうで、動きや表情、笑い方など、彼女たちの周囲を固めるプロの映画人が作る完成度と、彼女たちの新鮮さ、スラプスティック・コメディにも通じる繰り返しやズレの面白さなど、ストーリーの起承転結ではなく、シーンごとの瞬発力やキレで見せる映画だと思います。
くまがいさんによると、『ひなぎく』が最初に日本で上映されたのは1980年代。池袋にあった「スタジオ200」で、くまがいさんのお父様、故・粕三平さんが、自主上映に近い形で数回のみ、他のチェコスロヴァキアのヌーヴェルヴァーグの作品と共に上映したという。
それから、くまがいさん自身が1989年のチェコのビロード革命後、『ひなぎく』を劇場上映したいと、いくつかの映画館に打診。吉祥寺バウスシアターの故・本田耕一社長に気に入られ、1991年に6週間のロードショーが始まる。すると口コミで観客が増え、以来、90年代はバウスシアターの定番として、定期的に上映され続けることに。その後もシネセゾン渋谷、早稲田松竹や、新文芸坐など、本当に何度も上映されてきた。
――リピーターの方々も多そうですね。
『ひなぎく』が描く「自由」に含まれる両義性・多面性が、この映画の入り口を多様にしていると思います。私自身、見る度に心が動くシーンが違いますし、自分の体験や状況によって、以前は笑っていたシーンで気持ちがぐらぐらしたり、逆に、悲しかったシーンで薄皮が剥けるようにさらさらした感触になったりと、繰り返し見ることで変化する面白さがあります。5月の上映初日にモデルのAMOさんが見に来てくださって、そのことをご自身のブログに書いてくださっています。初めて見た時の『?』の感覚、何度もDVDで見て、スクリーンで見て、チェコの状況や監督の置かれていた状況も知っていきながら、この作品を受け止めてくださっていて「ありがたいことだな」と思いました。
――ちなみに、今年5月の上映に来た観客の方々は、どのような層が多かったのでしょう?
女子率8~9割でしょうか。劇場初公開の時からそうですが、女性2人で来られるケースが多く、渋谷でも神戸でも京都でも、ひなぎくの花輪をかぶった女性2人組や、Aラインのワンピースを来た女性など、映画の2人をほうふつとさせる方もちらほらいらっしゃったそうです。また、リピーターの方もたくさんいらっしゃいますし、60年代のヌーヴェルヴァーグに興味のありそうな世代の男性もいらっしゃいますが、デザイナーやスタイリストの方々にもファンが多く、女性ファッション誌などで、ファッションやインテリア、スタイルが何度も取り上げられてきたこともあり、確実に世代更新していて若い女性の方が多くみられます。そういう意味でも今回、3度目のリバイバルは以前よりも勢いを感じました。TwitterなどのSNSが新しい「口コミ」になっている感じもします。男性にももっと見に来てほしいですし、中高生の方などは、母娘で一緒に見るというのも、なかなか面白いと思います。
――ところで、チェコではどういった存在の映画になるのでしょうか?
『ひなぎく』は1960年代のチェコスロヴァキアのヌーヴェルヴァーグ作品の中でも特別な映画と捉えられていると思いますし、ヒティロヴァー監督が2014年3月12日に亡くなられた際、追悼記事で「チェコ映画のファースト・レディー」と呼ばれています。
――当時の政治的な背景が反映されているのですね。
「プラハの春」というのは、60年代の世界的な自由を称揚するうねりと連動したチェコスロヴァキアにおける1968年の一連の改革運動を指します。この春は短く、第二次世界大戦後のアメリカとソ連とそれぞれの同盟国が対立する冷戦構造の中で、政権批判・共産党批判に危機を覚えたソ連により、その年の8月、集団的自衛権の名のもとに軍事介入が行われ、ソ連率いるワルシャワ条約機構軍がチェコスロヴァキア全土を占領下に置きました。これにより、多くの芸術家、例えば『存在の耐えられない軽さ』を書いたミラン・クンデラや、『カッコーの巣の上で』や『アマデウス』を撮ったミロシュ・フォルマンなどの映画人が国外に亡命しました。国内に残ったヒティロヴァー監督やヤン・シュヴァンクマイエル監督は国のブラックリストに載り、1970年代にはほとんど映画を作る機会を与えてもらえませんでした。『ひなぎく』は1966年の作品ですが、この「プラハの春」とその後の悲劇の予兆のようなものがあり、そうした文脈からも、チェコ映画の中で特別な地位を与えられている作品だと思います。
――やはり日本での受け入れられ方とは違うようですね。
清少納言の時代から連綿と続く「かわいい(Kawaii)」ものを愛でる日本人の感覚が、『ひなぎく』が受容される大きな要素だということは間違いないと思います。でもチェコでは『ひなぎく』という作品を単に「かわいいもの」とは捉えていない。
政治的な背景をひも解いたり、おしゃれさ、かわいさにときめいたり、作品をどうみるかはもちろん自由。私も今もう一度見たら、きっと以前とは全く違う印象を受けるのだろう。
7月12日(土)の『ひなぎく』上映後には、チェコ蔵(CHEKOGURA)のペトル・ホリーさんのトークも決定。1960年代のチェコスロヴァキアの社会的・政治的背景や、『ひなぎく』撮影時のバックステージのことなど貴重な話が聞けそう。
ずっと色褪せることのなく、今なお刺激的で斬新な映画『ひなぎく』。この機会に、映画館でぜひ。
(田辺 香)